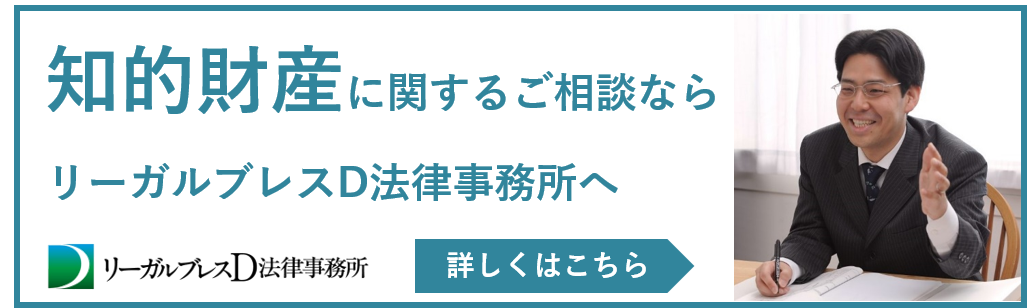プログラムは著作権法でどこまで保護されるのか。注意点とポイントを解説
Contents
【ご相談内容】
最近になって、プログラムが著作権の保護対象になっていることを知りました。
そこで、当社が開発したビジネスソフトを模倣したと思われる同業他社に対し、プログラムの著作権を根拠に、販売の差止めや損害賠償請求などを行いたいと考えているのですが、どこまで実効性があるのでしょうか。
【回答】
プログラムの著作物は、著作権法第10条第1項第9号で著作物の例示として規定されています。したがって、ソースコード等のプログラムが著作権の保護対象となることは間違いありません。
しかし、プログラムの著作物は、他の著作物のような表現の鑑賞や享受を目的とするものとは言い難く、やや異質であることは否めません。
この観点から、著作権法はプログラムの著作物について、①そもそも著作物となりうる場面が限定されていること、②著作権の行使が制限される場面が多いこと、③著作権侵害の判断手法がやや特殊であること等のいくつか注意するべき事項があります。
本記事では、まずはプログラムの著作物とは何を指すのかを検討したうえで、著作権者を判断する上での注意事項、権利行使が制限される場面、プログラムの著作物の侵害判断に関するポイントにつき、解説を行います。
【解説】
1.プログラムの著作物
(1)プログラムとは
プログラムという用語は日常的に用いられているので、何となくイメージはつくかと思うのですが、著作権法では、第2条第1項第10号の2で次のように定義されています。
| 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの |
上記定義にある「電子計算機」はいわゆるコンピュータのことです。著作権法上の定義規定はありませんが、演算、判別、照合などのデータ処理を高速に行う電子機器を指すと考えられます。
また、「一の結果」とは、何らかのデータ処理の結果を出すという意味であり、データ処理の内容や目的に限定はありません。このため、オペレーションシステムやアプリケーションプログラムはもちろん、プログラムを構成するルーチンやモジュールなどもプログラムに該当することになります。
さらに、「指令」については、いわゆる高級言語、機械言語によるかを問わないとされています。ただし、指令が組み込まれていることが前提なので、単なるデータだけを記録したファイルはプログラムに該当しないことになります。
ところで、日常用語で「プログラム」という言葉が用いられる場合、システム設計書や説明書、フローチャート等を含むことがあります。しかし、これらは著作権法第2条第1項第10号の2の定義からは明らかに外れますので、著作権法上は「プログラム」に該当しません。
もっとも、プログラムの著作物に該当しないだけであって、システム設計書や説明書は言語の著作物(著作権法第10条第1項第1号)として、フローチャートは図形の著作物(著作権法第10条第1項第6号)として、それぞれ保護される場合があります。
(2)プログラムと創作性
上記(1)で、著作権法上の「プログラム」の意義を解説しましたが、プログラムに該当すれば直ちに著作権法上の保護対象になるわけではありません。あくまでも「プログラムの『著作物』」に該当する必要があります。
この点、著作物については、著作権法第2条第1項第1号で次のように定義しています。
| 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの |
ここでポイントとなるのは、第2条第1項第10号の2に定める「プログラム」に該当しても、「創作性」がないプログラムであれば著作権法上の保護対象から外れるという点です。
では、プログラムの場合、何をもって「創作性」の有無を判断するのか、ここが現場実務では非常に重要な検討事項となります。
この点につき、いくつかの裁判例を引用します。
【東京高等裁判所平成元年6月20日決定】
| プログラムはこれを表現する記号が極めて限定され、その体系(文法)も厳格であるから、電子計算機を機能させてより効果的に一の結果を得ることを企図すれば、指令の組合わせが必然的に類似することを免れない部分が少なくないものである。したがって、プログラム著作物についての著作権侵害の認定は慎重になされなければならない… |
【東京地方裁判所平成15年1月31日判決】
| プログラムは、その性質上、表現する記号が制約され、言語体系が厳格であり、また、電子計算機を少しでも経済的、効率的に機能させようとすると、指令の組合せの選択が限定されるため、プログラムにおける具体的記述が相互に類似することが少なくない。仮に、プログラムの具体的記述が、誰が作成してもほぼ同一になるもの、簡単な内容をごく短い表記法によって記述したもの又は極くありふれたものである場合においても、これを著作権法上の保護の対象になるとすると、電子計算機の広範な利用等を妨げ、社会生活や経済活動に多大の支障を来す結果となる。また、著作権法は、プログラムの具体的表現を保護するものであって、機能やアイデアを保護するものではないところ、特定の機能を果たすプログラムの具体的記述が、極くありふれたものである場合に、これを保護の対象になるとすると、結果的には、機能やアイデアそのものを保護、独占させることになる。したがって、電子計算機に対する指令の組合せであるプログラムの具体的表記が、このような記述からなる場合は、作成者の個性が発揮されていないものとして、創作性がないというべきである。 |
【知的財産高等裁判所平成18年12月26日判決】
| 法2条1項1号が、「著作物」の意義について、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定していることからすれば、法によって保護されるのは、直接には「表現したもの」自体であり、思想又は感情自体に保護が及ぶことがあり得ないのはもちろん、思想又は感情を創作的に表現するに当たって採用された手法や表現を生み出すもとになったアイデア(着想)も、それ自体としては保護の対象とはなり得ないものというべきである。また、ある表現物を創作したというためには、対象となる表現物の形成に当たって、自己の思想又は感情を創作的に表現したと評価される程度の活動を行ったことが必要であり、当該表現物において、その者の思想又は感情を創作的に表現したと評価される程度に至っていない場合には、法上の創作には当たらない、言い換えると、著作物性を有しないものと解すべきである。そして、この点は、当該表現物がプログラムである場合であっても何ら異なるところはないが、小説、絵画、音楽などといった従来型の典型的な著作物と異なり、プログラムの場合は、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(法2条1項10の2)であって、元来、コンピュータに対する指令の組合せであり、正確かつ論理的なものでなければならないとともに、プログラムの著作物に対する法による保護は、「その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。」(法10条3項柱書1文)ところから、所定のプログラム言語、規約及び解法に制約されつつ、コンピュータに対する指令をどのように表現するか、その指令の表現をどのように組み合わせ、どのような表現順序とするかなどといったところに、法によって保護されるべき作成者の個性が表れることとなる。したがって、プログラムに著作物性があるといえるためには、指令の表現自体、その指令の表現の組合せ、その表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅が十分にあり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性が表れているものであることを要するものであって、プログラムの表現に選択の余地がないか、あるいは、選択の幅が著しく狭い場合には、作成者の個性の表れる余地もなくなり、著作物性を有しないことになる。そして、プログラムの指令の手順自体は、アイデアにすぎないし、プログラムにおけるアルゴリズムは、「解法」に当たり、いずれもプログラムの著作権の対象として保護されるものではない |
【知的財産高等裁判所平成23年2月28日判決】
| 著作権法が保護の対象とする「著作物」であるというためには、「思想又は感情を創作的に表現したもの」であることが必要である(同法2条1項1号)。思想又は感情や、思想又は感情を表現する際の手法やアイデア自体は、保護の対象とならない。例えば、プログラムにおいて、コンピュータにどのような処理をさせ、どのような指令(又はその組合せ)の方法を採用するかなどの工夫それ自体は、アイデアであり、著作権法における保護の対象とはならない。
また、思想又は感情を「創作的に」表現したというためには、当該表現が、厳密な意味で独創性のあることを要しないが、作成者の何らかの個性が発揮されたものであることが必要である。この理は、プログラムについても異なることはなく、プログラムにおける「創作性」が認められるためには、プログラムの具体的記述に作成者の何らかの個性が発揮されていることを要すると解すべきである。もっとも、プログラムは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(同法2条1項10号の2)であり、コンピュータに対する指令の組合せという性質上、表現する記号や言語体系に制約があり、かつ、コンピュータを経済的、効率的に機能させようとすると、指令の組合せの選択が限定されるため、プログラムにおける具体的記述が相互に類似せざるを得ず、作成者の個性を発揮する選択の幅が制約される場合があり得る。プログラムの具体的表現がこのような記述からなる場合は、作成者の個性が発揮されていない、ありふれた表現として、創作性が否定される。また、著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約、解法には、著作権法による保護は及ばず(同法10条3項)、一般的でないプログラム言語を使用していることをもって、直ちに創作性を肯定することはできない。 |
【知的財産高等裁判所平成24年1月25日判決】
| プログラムは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」(著作権法2条1項10号の2)であり、所定のプログラム言語、規約及び解法に制約されつつ、コンピュータに対する指令をどのように表現するか、その指令の表現をどのように組み合わせ、どのような表現順序とするかなどについて、著作権法により保護されるべき作成者の個性が表れることになる。
したがって、プログラムに著作物性があるというためには、指令の表現自体、その指令の表現の組合せ、その表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性、すなわち、表現上の創作性が表れていることを要するといわなければならない。 |
裁判所の判断傾向をつかんでもらうため、あえて5つの裁判例を取り上げました。
ここでつかんでほしいのは、裁判所はプログラムの著作物について、意識的にその範囲を限定していることです。なぜ、範囲を限定しているのかですが、
・プログラムは一定の“機能”を提供することが本来であるところ、一方で“機能”は表現ではない。プログラムの“機能”を前提に創作性を主張することは筋違いである。
・もともとプログラムは特定の言語と規約に従って表現される。このため、ある機能を実現するためのプログラムの表現は自ずと似通うことになる。
・ある機能を実現するためのプログラムの表現について、誰が作成してもほぼ同じようなものになってしまう場合、ありふれた表現と言わざるを得なくなる。
といった点が考慮されていると思われます。
いずれにせよ、現場実務で対応している執筆者個人の感覚として、企業の担当者が念頭に置いている「創作性」と、弁護士等の法律家が想定している「創作性」には大きなズレが生じていることが多いというのが実情です。
ある範囲のプログラムの表現に創作性があると主張したいのであれば、最低限、他人であればどのようなプログラムの表現を行うのか、当該表現は容易に思いつきかつ合理性があるのかを準備しないことには、検討を進めることさえ難しいという点を知っていただければと思います。
(3)プログラムの著作物から除外されるもの
第2条第1項第10号の2に定める「プログラム」に該当し、かつ著作権法第2条第1項第1号に定める「創作性」を満たした場合、プログラムの著作物として保護されることになります。
しかし、著作権法第10条第3項では、次のものについてはプログラムの著作物に該当しないと定められています。
| 第1項第9号に掲げる著作物(※筆者注:プログラムの著作物のこと)に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
①プログラム言語…プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。 ②規約…特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。 ③解法…プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。 |
プログラム言語が除外されるのは、例えるなら、我々が文章を書き、話をするために“日本語”という言語体系を用いるのですが、この“日本語”が誰かの独占的権利となってしまうと、我々は日本語を用いて文章を書く、話をすることができなくなってしまいます。このような観点から、プログラム言語はプログラムの著作物に該当しないとされています。
なお、プログラム言語の具体例ですが、C言語、COBOL、BASICなどです。
次に規約が除外されるのは、例えるなら、日本語で文章を書き、話をするための“文法”が誰かの独占的権利となってしまうと、やはり日本語の文章を書く、話をすることができなくなります。このような観点から規約はプログラムの著作物に該当しないとされています。
なお、規約の具体例ですが、protocol、interfaceなどです。
さらに解法が除外されるのは、例えるなら、印象的な表現にするために倒置法を用いるというアイデアを思いついたところ、この倒置法が誰かの独占的権利となってしまうと、倒置法というアイデア自体を用いることができなくなってしまいます。このような観点から解法はプログラムの著作物に該当しないとされています。
なお、解法の具体例ですが、アルゴリズムなどです。
(4)プログラムと画面表示との関係
上記(2)で解説した通り、プログラムの表現に創作性がないことにはプログラムの著作物として保護されません。
そこで、プログラムを実行した結果として、ディスプレイ等に表示される画像が著作物に該当することを念頭に置いた論法が取られることがあります。
この点、一般論としては、画像(相互に牽連関係のある各表示画面の集合体たる全画面を含む)について著作物に該当する場合があるとされています。
しかし、次のような判断傾向があることにも注意を要します。
【東京地方裁判所平成16年6月30日判決】
| コンピュータのディスプレイ上に表示される画面については、〈1〉所定の目的を達成するために、機能的で使いやすい作業手順は、相互に似通ったものとなり、その選択肢が限られること、ユーザーの利用を容易にするための各画面の構成要素も相互に類似するものとなり、その選択肢が限られること、〈2〉各表示画面を構成する部品(例えば、ボタン、プルダウンメニュー、ダイアログ等)も、既に一般に使用されて、ありふれたものとなっていることが多いこと、〈3〉特に、既存のアプリケーションソフトウェア等を利用するような場合には、設計上の制約を受けざるを得ないことなどの理由から、表示画面の創作性の有無を判断するに当たっては、これらの諸事情を勘案して、判断する必要がある。 |
結局のところ、画像についても創作性があるのかという点が重要なポイントになるところ、機能性を追求すればするほど、自ずと表現の選択の幅が狭くなり、著作物として保護されない可能性が高くなるというジレンマを抱えることになります。
2.プログラムの著作物の著作権者
(1)原則論
プログラムの著作物について、上記1.で解説した通り、著作物として認められる範囲に特殊性がありますが、著作権の帰属については特別なルールがあるわけではありません。
原則通り、著作物を創作した者が著作者であり(著作権法第2条第1項第2号)、著作権が原始的に帰属することになります(著作権法第17条)。
(2)職務著作
原則論は上記(1)の通りですが、著作権法では重要な例外として「職務著作」に関する定めが置かれており、現場実務ではむしろ「職務著作」であることを前提に運用されているところがあります。
この職務著作については、著作権法第15条で次のように定めています。
| 1. 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2. 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 |
職務著作の一般的な成立要件は第1項で、プログラムの著作物に関する特例は第2項で定められています。第1項と第2項の相違は、「法人等が自己の名義の下に公表する著作物であること」という要件の有無であり、プログラムの著作物における職務著作の成立において当該要件は不要としています。
したがって、プログラムの著作物において、職務著作が成立する場合の要件は次の通りとなります。
・著作物が法人等の発意に基づいて作成されたものであること
・法人等の業務に従事する者が作成したものであること
・従事者が職務上作成した著作物であること
・著作物作成のときにおける契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと
上記の要件で注意を要するのは、「法人等の業務に従事する者」の意義です。
すなわち、この要件があるため、法人等との間で雇用契約がある従業員及び法人等の役員を意味し、雇用関係のない者(請負や委任などの業務委託に基づく作成者)は含まれないことになります。
したがって、一般的なシステム開発契約等に基づき、受託者がプログラムの著作物を創作した場合、職務著作の規定は適用されず、受託者に著作権が帰属したままとなります。よく勘違いがあるのですが、システム開発にかかる報酬を支払ったから著作権が当然に移転するわけではありません。
委託者において著作権を取得することを希望する場合、別途著作権の譲渡に関する取り決めを行う必要があることに注意を要します。
なお、著作権譲渡契約に関するポイントについては、次の記事をご参照ください。
著作権に関する契約(利用許諾・ライセンス、譲渡、制作)のポイントについて解説
(3)派遣社員が創作した場合の処理
労働者派遣契約に基づき派遣されてきたプログラマーがプログラムの著作物を創作した場合、派遣先に著作権が帰属するのかという問題があります。
形式的に考えれば、派遣先と派遣社員との間には雇用関係がない以上、「法人等の業務に従事する者」に該当しません。もっとも、解釈論として、派遣先と派遣社員との間には指揮命令関係がある以上、実質的には「法人等の業務に従事する者」に該当するという考え方も有り得るところです。
ただ、解釈論に過ぎないことを踏まえると、現場実務では、労働者派遣契約を締結する際に、派遣社員が創作した著作物にかかる著作権の帰属等について、契約書に明記しておくことが重要になると考えられます(派遣元の職務著作と解釈される場合に備えて、派遣元が派遣先に対して著作権を譲渡するという取り決めを労働者派遣契約に定めておくこと等)。
(4)職務発明との相違
職務“発明”の場合、従業員等に発明が帰属するとされており、法人等が当該発明の権利を取得したいと考えた場合、相当対価を支払う等の対応が必要となります。
しかし、職務“著作”の場合、法人等に原始的に帰属する以上、相当対価の支払いは不要です。
この点は勘違しないよう、きっちり押さえておきたいところです。
3.プログラムの著作物の著作権とその特殊性
プログラムの著作物も著作権として認められる以上、原則として他の著作物と同様に著作権法第21条から第28条までの権利は付与されます(もちろん、著作権法第26条のような特定の著作物のみに認められている権利は除きます)。
もっとも、プログラムの著作物の特性により、次のような例外的取扱いが著作権法に定められています。
(1)同一性保持権の適用除外
プログラムの著作物の著作者は、著作者人格権を有します(公表権につき著作権法第18条、氏名表示権につき著作権法第19条、同一性保持権につき著作権法第20条)。
しかし、同一性保持権については、著作権法第20条第2項第3号で次のような例外が定められています。
| 前項の規定(執筆者注:同一性保持権のこと)は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。
(1号、2号省略) ③特定の電子計算機においては実行し得ないプログラムの著作物を当該電子計算機において実行し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機においてより効果的に実行し得るようにするために必要な改変 |
利用者において、例えば、バグの修正、処理速度向上のための修正、機能追加、バージョンアップ等を著作者に無断で行っても、同一性保持権侵害とはならないということが定められています。
この例外規定により、プログラムの著作物の著作者は同一性保持権を有していないのと等しい状態になりますが、一方で著作権者が有する翻案権の侵害問題は残りますので、この点は注意を要します。
(2)複製物の所有者による複製・翻案
上記(1)で指摘した翻案権侵害の問題については、著作権法第47条の3第1項で次のような手当てが行われています。
| プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算機において実行するために必要と認められる限度において、当該著作物を複製することができる。ただし、当該実行に係る複製物の使用につき、第百十三条第五項の規定が適用される場合は、この限りでない。 |
ところで、著作権法第47条の3第1項の適用範囲は、今の時代にはやや合致しないことに注意が必要です。
すなわち、利用者において、例えば、バグの修正、処理速度向上のための修正、機能追加、バージョンアップ等を著作者に無断で行っても翻案権侵害とはならない要件は、利用者が「プログラムの著作物の複製物の所有者」である場合に限定されています。
一昔前のプログラムが書き込まれたCD-ROM等を購入している場合であれば、著作権法第47条の3第1項が適用されますが、最近多いASPやSaaS方式の場合、利用者は複製物を所有していませんので、著作権法第47条の3第1項は適用されません。
したがって、近時のプログラム利用形態を考慮すると、著作権者は翻案権侵害を主張できる余地があることになります。利用者視点で考えた場合、利用者は著作権法第47条の3第1項で対処するのではなく、プログラムの著作物の著作権者との間で、著作権を譲渡してもらう、適切なライセンスの付与を受ける等の対策を講じる必要があることに注意を要します。
(3)電子計算機による情報処理およびその結果の提供に付随する軽微利用
この規定はプログラムの著作物に限ったものではないのですが、機械学習や深層学習の研究開発が進む今後において、重要な制限規定になると考えられることから取り上げています。
さて、著作権法第47条の5第1項第2号では、次のように定めています。
| 電子計算機を用いた情報処理により新たな知見又は情報を創出することによって著作物の利用の促進に資する次の各号に掲げる行為を行う者(当該行為の一部を行う者を含み、当該行為を政令で定める基準に従って行う者に限る。)は、公衆への提供等(公衆への提供又は提示をいい、送信可能化を含む。以下同じ。)が行われた著作物(以下この条及び次条第二項第二号において「公衆提供等著作物」という。)(公表された著作物又は送信可能化された著作物に限る。)について、当該各号に掲げる行為の目的上必要と認められる限度において、当該行為に付随して、いずれの方法によるかを問わず、利用(当該公衆提供等著作物のうちその利用に供される部分の占める割合、その利用に供される部分の量、その利用に供される際の表示の精度その他の要素に照らし軽微なものに限る。以下この条において「軽微利用」という。)を行うことができる。(但書省略)
(第1号省略) ②電子計算機による情報解析を行い、及びその結果を提供すること。 |
要はディープラーニングを実行するにあたり著作物を記録媒体に複製などする場合は、著作権侵害に該当しないと定められています。
AI技術の進展に寄与する規定と言われていますが、一方で何をもって「軽微利用」というのか現時点でははっきりしないところがあり、今後の動向を押さえておく必要がある条項となります。
(4)みなし著作権侵害
これは、プログラムの著作物の著作権が強化されている意味での例外となるのですが、いわゆる海賊版のプログラムであることを知りながら使用した場合、著作権侵害が成立するというものです(著作権法第113条第5項)。
どの点で強化されているのかと言いますと、例えば言語の著作物である漫画の単行本につき、著作権者に無断で複製され、無断で複製されたことを知りながら当該複製物を取得した利用者が、当該複製物を使用(漫画を読む)したとしても、著作権侵害は成立しません。
しかし、プログラムの著作物の場合、取得時点で無断複製されたことを利用者が知っていた場合、著作権侵害が成立することになります。
4.プログラム著作物の侵害判断の特殊性
「プログラムの著作物」につき注目が集まる場面と言えば、当方のプログラムと相手方のプログラムが類似する場面、すなわち著作権侵害の紛争が生じた場合です。
ここでは、プログラムの著作物の侵害判断に当たり、特に留意しておきたいポイントを解説します。
(1)権利者のプログラムと著作物性
上記1.の「プログラムの著作物」で解説した通り、「指令の表現自体、その指令の表現の組合せ、その表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性、すなわち、表現上の創作性が表れていること」が必要です。
現場実務で対応していると、この点に関する勘違いが非常に多いと感じますので、十分に検証したいところです。
(2)侵害判断基準に特殊性
プログラムの著作物については、
・もともとプログラムは特定の言語と規約に従って表現される。このため、ある機能を実現するためのプログラムの表現は自ずと似通うことになる。
・ある機能を実現するためのプログラムの表現について、誰が作成してもほぼ同じようなものになってしまう場合、ありふれた表現と言わざるを得なくなる。
という特徴があります。
このため、侵害の判断についても、上記の点を意識したものとなります。例えば、知的財産高等裁判所平成23年2月28日判決は次のように述べています。
| 後に作成されたプログラムが先に作成されたプログラムに係る複製権ないし翻案権侵害に当たるか否かを判断するに当たっては、(省略)、プログラムの具体的記述の中で、創作性が認められる部分を対比し、創作性のある表現における同一性があるか否か、あるいは、表現上の創作的な特徴部分を直接感得できるか否かの観点から判断すべきであり、単にプログラム全体の手順や構成が類似しているか否かという観点から判断すべきではない。 |
要は、機能や処理手順が類似していたとしても、それだけで著作権侵害が成立するわけではありません。また、創作性がない部分をどんなに多く模倣していたとしても、やはり著作権侵害は成立しません。
プログラムの具体的記述内容から創作性が認められる部分を特定し、相手方のプログラムと対比することが重要となります。
(3)相手方プログラムの入手困難性
一般的な著作権侵害の場面では、相手方の著作物が公表されていることから、その入手は比較的容易です。
しかし、プログラムは一般的に公表されているものではなく、入手することに一苦労します。また仮にも入手できたとしても、機械言語で作成されたオブジェクトコードであり、侵害の有無につき判断のしようがないという場面に遭遇することもしばしばです。
この問題については、現場実務での工夫が必要となりますが
・相手方に対して任意での開示を要請する
・ソースコードへの変換を試みる
・証拠保全手続きを利用する(民事訴訟法第234条以下)
・書類提出命令の申立を行う(著作権法第114条の3)
等々が考えられます。
ただ、残念ながら一長一短があり、確実に入手可能とは言い難いのが実情です。弁護士等の専門家と十分協議しながら対処したいところです。
5.当事務所でサポートできること
プログラムの著作物は、著作権法の中でもその取扱いが極めて特殊であり、正確な理解はもちろん、現場実務での慣行や運用状況などを加味しながら対処しないことには、思わぬリスクを抱え込むことになります。
また、上記までで解説した通り、プログラムの著作物に該当する場面は狭いことからすると、むしろ著作物ではないプログラムの保護の在り方についても気配りが必要となります。
当事務所は、顧問契約をしていただいている取引先のうち、約3分の1がIT企業であり、プログラムに関連する様々な問題を日々取扱っています。そして、こられの対応により蓄積された知見・ノウハウ等は相当なものになっていると自負しています。
当事務所をご利用いただく皆様に対して、これらの知見・ノウハウを最大限活用したサービスをご提供することが可能です。
プログラムの著作物に関するご相談があれば、是非当事務所をご利用ください。
<2023年7月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。