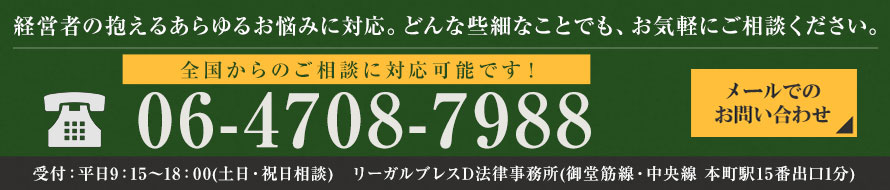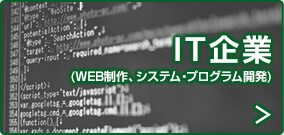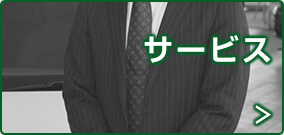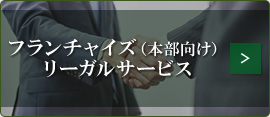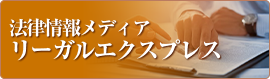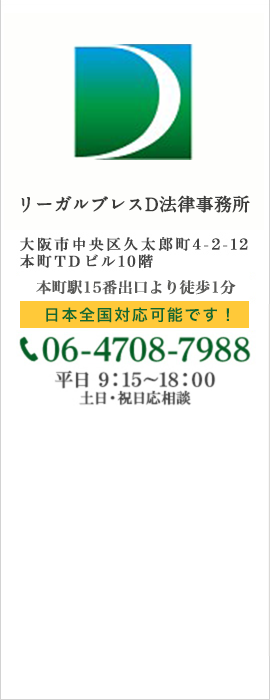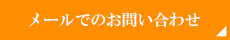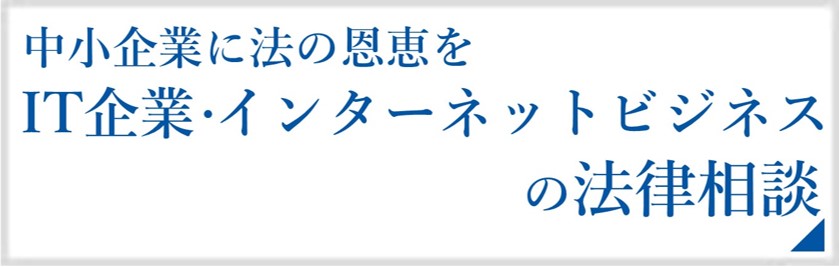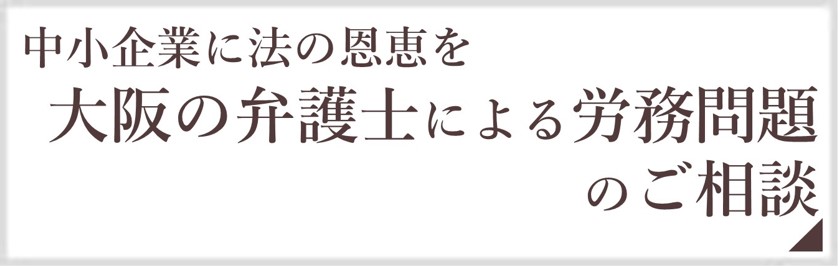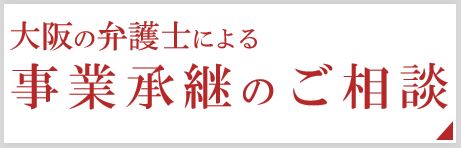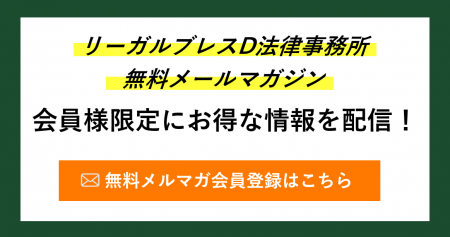取締役の解任手続きと正当理由の有無~会社が負う責任とは?
株主総会の普通決議で取締役を解任できる…これは会社法に明記された原則です。
しかし、現場実務では、その「簡単なはずの解任」が、後に無効主張、仮処分、損害賠償といった深刻なトラブルへと発展するケースが少なくありません。
たとえば、招集通知に解任議案が正しく記載されていなかった場合、決議自体が取消や無効とされる可能性があります。また、正当な理由なく任期途中で解任すれば、会社が損害賠償請求を受けるリスクもあります。さらに、解任対象の取締役が仮処分を申し立て、総会の開催や議決権行使が差し止められる場面も想定されます。
本記事では、取締役の解任をめぐる法的基礎と実務上の注意点、想定される紛争の類型を体系的に整理しています。
「解任する側」「される側」いずれにとっても、軽視できない要点を網羅していますので、取締役人事やガバナンスに関与する経営者、法務責任者、管理部門の皆様にとって、意思決定の判断材料となる実務ガイドとしてご活用ください。
1.取締役を解任する場合の要点
取締役の意思に反してでも、会社が一方的に地位を剝奪するのが解任です。この“一方的”という点を意識してか、あるいは会社のために業務遂行する点では労働者と類似することを考慮してか、解任するには正当性などの要件が必要と考える方もいるようです。
しかし、法律上何ら要件は課されていません。
すなわち、株主総会で決議さえすれば、取締役を解任することは可能と定められています(会社法第339条第1項)。
したがって、会社法のルールに従って株主総会を招集し、適法に株主総会を開催する…といった手続きさえ順守すれば、取締役を解任することは可能となります。
もっとも、正当性がない場合、解任の効力は失われないものの、会社は取締役に対して損害賠償義務を負担することになります(会社法第339条第2項)。
【取締役と労働者との相違】
| 取締役 | 労働者 | |
| 法律関係 | 準委任契約 | 労働契約 |
| 地位を剥奪する理由 | なし | 客観的に合理的な理由があり、かつ当該理由が社会通念上相当であること(労働契約法第16条) |
| 理由の開示要請 | なし | 証明書の交付を通じて要請可能(労働基準法第22条) |
| 手続き | 株主総会での決議 | 30日前の解雇予告又は30日分以上の解雇予告手当の支払い(労働基準法第20条) |
| 地位剥奪後の清算 | 正当性がない場合は損害賠償を通じて清算 | なし |
2.取締役を解任する手続き(取締役会設置会社)
上記1.で解説した通り、取締役を解任するに当たりその理由は問いませんが、会社法が定めた手続きに従う必要があります。
現場実務を見ていると、特に中小企業ではこの手続きに従っておらず、結果的に取締役の解任が無効になってしまうというパターンを数多く見かけます。
そこで、以下では、取締役を解任するために必要となる手続きの概要を確認しつつ、現場実務で見落とされがちな事項を指摘します。
なお、本記事では非公開会社を念頭に置きつつ、2.では取締役会が設置されている会社における手続きを、次の3.では取締役会が設置されていない会社における手続きを解説します。
【手続き①】取締役会の招集
取締役を解任するための株主総会を開催するためには、まずは取締役会で株主総会開催を決める必要があります(会社法第298条第4項)。
このため、まずは取締役会を開催するための招集手続きを実施する必要があります。
多くの会社では、招集手続きルールについて定款に何らかの規定を設けているため、まずは定款を確認する必要があります。定款に特に規定がない場合は、次のような会社法が定めるルールに則って招集手続きを実施することになります。
■各取締役が招集する(会社法第366条第1項)
■招集通知を発送する
(※招集通知記載事項は法定化されていませんが、最低限日時と場所は記載するべきです)
(※発送方法は法定化されていませんが、履歴が残る手紙やメール等を用いることをお勧めします)
(※解任対象となる取締役に対しても招集通知を発送する必要があります)
■取締役会開催の1週間前までに招集通知を発送する(会社法第368条第1項)
(※この「1週間」のカウントですが、発送日と開催日を除く期間が1週間という意味です。例えば、6月15日に取締役会を開催する場合、6月7日までに招集通知を発送する必要があります)
【手続き②】取締役会での決議
取締役会にて、(臨時)株主総会開催を決議する必要があります。
この際、「株主総会の日時及び場所」、「株主総会の目的である事項があるときは、当該事項」など会社法第298条第1項に定める内容を決議対象とする必要があります。
なお、決議に際しては、定足数や決議要件等について、定款で何らかの規定(法律より要件が加重されていないか等)が設けられていないかを確認する必要があります。
定款に特に規定がない場合は、次のような会社法が定めるルールに則って取締役会決議を実施することになります。
■議決に加わることができる取締役の過半数が出席しているか確認(定足数、会社法第369条第1項)
(※解任対象となる取締役は、特別利害(会社法第369条第2項)があるものとして取扱うのは一般的です。この場合、解任対象となる取締役は定足数から外すことになります)
■出席方法の確認
(※委任状や代理による出席は認められません)
(※いわゆる書面決議(持回り決議)は、会社法第370条の要件を充足しない場合が多いことに注意を要します)
(※オンラインシステムを用いて参加することは可能ですが、通信状況を確認する必要があります)
■出席取締役の過半数となるのか確認(会社法第369条第1項)
(※同様に解任対象となる取締役は、特別利害(会社法第369条第2項)があるものとして取扱うのは一般的です。この場合、解任対象となる取締役は出席取締役数から外すことになります)
(※なお、決議には参加させないものの、事後の損害賠償問題を見据え、解任対象となる取締役を審議に参加させ弁明させるといった、現場実務の工夫も見られます)
■「過半数」の意味内容の確認
(※例えば、取締役が4人の場合、過半数とは3人以上の場合を指し、2人では過半数に達したことにはなりません)
■取締役会議事録の作成
【手続き③】株主総会の招集
取締役会にて、(臨時)株主総会の開催が可決された場合、株主総会の招集手続きを実施する必要があります。
なお、招集手続きルールについて定款に何らかの規定を設けている場合も多いため、まずは定款を確認する必要があります。定款に特に規定がない場合は、次のような会社法が定めるルールに則って招集手続きを実施することになります。
■各取締役が招集する(会社法第299条第1項)
■招集通知を発送する(会社法第299条第2項以下)
(※招集通知記載事項は法定化されています。取締役会の招集とは異なり、要件が厳格であることに注意を要します)
(※発送方法は原則書面とされています。やはり取締役会の招集とは異なることに注意を要します)
(※解任対象となる取締役が株主である場合、招集通知を発送する必要があることは、取締役会の招集の場面と同様です)
■株主総会開催の1週間前までに招集通知を発送する(会社法第299条第1項)
(※この「1週間」のカウントですが、発送日と開催日を除く期間が1週間という意味です。例えば、7月15日に株主総会を開催する場合、7月7日までに招集通知を発送する必要があります)
【手続き④】株主総会での決議
いよいよ取締役の解任決議を行うことになります。
なお、決議に際しては、定足数や決議要件等について、定款で何らかの規定(法律より要件が加重されていないか等)が設けられていないかを確認する必要があります。
定款に特に規定がない場合は、次のような会社法が定めるルールに則って株主総会決議を実施することになります(累積投票制度により選任された取締役を解任する場合は、次に記載するルールの一部が変更されること、ご注意ください)。
■議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席しているか確認(定足数、会社法第309条第1項)
(※取締役会は人数でカウントしますが、株主総会は議決権数でカウントすることに注意を要します)
(※解任対象となる取締役が株主である場合、当然に出席することが可能です。取締役会決議での特別利害関係問題は生じないことに注意を要します)
■出席方法の確認
(※委任状や代理による出席が認められます。取締役会決議とは異なることに注意を要します)
■議事進行方法の確認
(※議長の選任、動議があった場合の対処法、想定問答の準備などを含めたシナリオを策定することをお勧めします)
(※解任対象となる取締役が株主である場合、質問権を行使することが可能です。会社はこの質問に答える義務があります)
■出席株主の過半数となるのか確認(会社法第309条第1項)
(※定足数と同じく、出席株主が保有する議決権でカウントすることに注意を要します)
(※解任対象となる取締役が株主である場合、議決権を行使することができます。取締役会での決議とは異なることに注意を要します)
■「過半数」の意味内容の確認
(※例えば、出席した株主が有する議決権が1000個である場合、過半数とは501個以上の場合を指し、500個では過半数に達したことにはなりません)
■株主総会議事録の作成
【手続き⑤】解任登記など
株主総会で取締役の解任が決議された場合、必要書類をそろえて、会社の本店所在地を管轄する法務局に解任登記の申請を行います。
解任決議より2週間以内に登記申請を行わなかった場合、過料の制裁など不利益処分を受けるので注意を要します。
■解任された取締役への通知
法律上の通知義務はありません。
ただし、解任された取締役が株主ではない場合、株主であっても株主総会に出席していなかった場合、解任されたか否か対象者が認識できていないこともありますので、念のため通知したほうが無難です。
3.取締役を解任する手続き(取締役会非設置会社)
取締役会が設置されていない会社は、上記2.と比較して、手続きが簡素化されているのが特徴です。
【手続き①】株主総会の招集決定
取締役会非設置会社では、取締役会が存在しない以上、取締役会の招集手続き及び取締役会の決議という手続きがありません。
このため、原則的には、取締役が株主総会の日時及び場所、目的事項を定め(会社法第298条第1項)、招集することになります(会社法第296条第3項)。
もっとも、取締役の解任が問題となる場合、一般的には複数の取締役が選任されている場合となるため、次のようなルールに従う必要があります。
■取締役の過半数による決定(会社法第348条第2項)
(※取締役2名、内1名を解任対象としたい場合、解任対象となる取締役が反対すれば、過半数の決定ができません。この場合、少数株主による株主総会招集手続き(会社法第297条)を利用するなど別手段を講じる必要があります)
■「過半数」の意味内容の確認
(※例えば、取締役が2人の場合、過半数とは2人の場合を指し、1人だけでは過半数に達したことにはなりません)
■特別利害関係は非適用
(※取締役会設置会社の場合、特別利害(会社法第369条第2項)があれば決議に加わることができないのですが、取締役会非設置会社にはそもそも適用がありません。このため、会社法第348条第2項に基づく決定の際に、特別利害関係を理由に排除することはできないことに注意を要します)
【手続き②】株主総会の招集手続き
取締役の過半数の決定があった場合、株主総会の招集手続きを実施する必要があります。
なお、招集手続きルールについて定款に何らかの規定を設けている場合も多いため、まずは定款を確認する必要があります。定款に特に規定がない場合は、次のような会社法が定めるルールに則って招集手続きを実施することになります。
■各取締役が招集する(会社法第299条第1項)
■招集通知を発送する(会社法第299条第2項以下)
(※招集通知記載事項は法定化されています)
(※発送方法は書面に限定されません。取締役会設置会社とは異なることに注意を要します。もっとも、履歴が残る手紙やメール等を用いることをお勧めします)
(※解任対象となる取締役が株主である場合、招集通知を発送する必要があります)
■株主総会開催の1週間前までに招集通知を発送する(会社法第299条第1項)
(※この「1週間」のカウントですが、発送日と開催日を除く期間が1週間という意味です。例えば、7月15日に株主総会を開催する場合、7月7日までに招集通知を発送する必要があります)
【手続き③】株主総会の決議
株主総会での決議に際しては、定足数や決議要件等について、定款で何らかの規定(法律より要件が加重されていないか等)が設けられていないかを確認する必要があります。
定款に特に規定がない場合は、次のような会社法が定めるルールに則って株主総会決議を実施することになります(累積投票制度により選任された取締役を解任する場合は、次に記載するルールの一部が変更されること、ご注意ください)。
■議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席しているか確認(定足数、会社法第309条第1項)
(※株主総会は議決権数でカウントすることに注意を要します)
(※解任対象となる取締役が株主である場合、当然に出席することが可能です)
■出席方法の確認
(※委任状や代理による出席が認められます)
■議事進行方法の確認
(※議長の選任、動議があった場合の対処法、想定問答の準備などを含めたシナリオを策定することをお勧めします)
(※解任対象となる取締役が株主である場合、質問権を行使することが可能です。会社はこの質問に答える義務があります)
■出席株主の過半数となるのか確認(会社法第309条第1項)
(※定足数と同じく、出席株主が保有する議決権でカウントすることに注意を要します)
(※解任対象となる取締役が株主である場合、議決権を行使することができます)
■「過半数」の意味内容の確認
(※例えば、出席した株主が有する議決権が1000個である場合、過半数とは501個以上の場合を指し、500個では過半数に達したことにはなりません)
■株主総会議事録の作成
【手続き④】解任登記など
株主総会で取締役の解任が決議された場合、必要書類をそろえて、会社の本店所在地を管轄する法務局に解任登記の申請を行います。
解任決議より2週間以内に登記申請を行わなかった場合、過料の制裁など不利益処分を受けるので注意を要します。
■解任された取締役への通知
法律上の通知義務はありません。
ただし、解任された取締役が株主ではない場合、株主であっても株主総会に出席していなかった場合、解任されたか否か対象者が認識できていないこともありますので、念のため通知したほうが無難です。
4.対象となる取締役が取りうる手段
上記までに記載した通り、取締役はいつでも理由なく解任される立場にあります。
しかし、対抗する手段はいくつかあります。
以下では、解任の対象となった取締役が採りうる対抗策につき解説します。
(1)事前防止策を講じる方法
例えば、名義株の問題や新株発行手続きに不備があるため株式の帰属や議決権の数に問題がある場合、株主総会開催禁止の仮処分や議決権行使禁止の仮処分の申立てが検討できます。
また、従前から適法な株主総会が開催されていない場合、解任手続きを進めようとしている取締役は適法に選任されたことにはなっていない以上、手続き自体を進める権限がないことを理由に職務執行停止仮処分の申立てを行うことも考えられます。
これらのポイントは、解任それ自体を問題視するのではなく、そもそも会社はこれまでに会社法上の手続きを適切に履行してきたのかという全体を問題視し、何か綻びがあるのであれば、そこを徹底的に突いていくという点にあります。
中小企業の場合、会社法上の手続きを適法に実践していない方がむしろ通常ですので、手続き上の問題点は必ず見つかると言っても過言ではありません。しかし、株主総会を開催されるまでの僅かな時間で証拠を収集し、裁判所に仮処分の申立てを行うことは現実問題としては難しいところがりあります。
したがって、検討の余地はあるものの、権利行使に至らないというのが実情のようです。
(2)事後的に解任決議の効力を争う方法
繰り返し解説していますが、取締役を解任するに際しては、その解任理由を問いません。
このため、事後的に解任決議の効力を争う方法とは、専ら解任決議に至るまでの「手続き上の不備」を理由とした対処法となります。例えば…
・株主総会決議不存在確認訴訟(例えば、従前より適法な株主総会が開催されていなかった場合など。会社法第830条第1項)
・株主総会決議取消請求訴訟(例えば、招集手続きに法令違反があった場合など。会社法第831条)
などが考えられます。
なお、上記訴訟には一定の時間を要することから、その期間中の取締役としての地位を回復するべく、「取締役の地位を仮に定める仮処分」の申立ても並行して進めることも検討する必要があります。
(3)損害賠償を請求する方法
取締役として解任されたこと自体は争わず、しかし解任されたことによって被った損害を請求するという対処法があります。
【会社法第339条】
| 1 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。 |
解任理由の正当性は解任決議の効力に影響を及ぼしません。しかし、正当性がない場合、会社は損害賠償義務を負うことになります。
では、「正当な理由」とは何かが問題となります。
この点については一律の基準があるわけではなく、ケースバイケースというのが正確な回答と言わざるを得ません。
もっとも、裁判例の積み重ねにより、ある程度の傾向はつかむことができます。
<正当性が認められやすい類型>
・職務執行に関係する法令、定款違反行為があった場合(但し、軽微な違反に留まる場合は別途考慮が必要)
・心身の故障により業務執行が困難な場合
・合理的な理由なく長期にわたって取締役会を欠席した場合
・会社への敵対行為、業務妨害がある場合
・名目的取締役である場合
なお、職務執行と関係しない法令違反行為があった場合、オーナーと対立・見解の相違がある場合、経営判断の失敗に留まる場合(善管注意義務違反と断定できない場合)などの事例では、正当性が認められず、会社が損害賠償義務を負担する可能性は高いと考えられます。
次に、正当性が認められず、会社が損害賠償義務を負担する場合、具体的にどの程度の金銭負担が生じるのかが問題となります。
これについては、原則として、解任が無ければ取締役が残存任期中に得られたであろう役員報酬相当額とされています。
現場実務で問題となるのは、取締役の任期が定款で10年に伸長されている場合の残存任期中に相当する役員報酬相当額の支払い義務が生じるのか、特例有限会社において任期が定められていない場合はどうなるのか、という問題です。
この点、前者については、一定期間(2年程度)に限って損害賠償額を算定した裁判例が存在する一方で、10年の任期を前提にした残存任期に基づく損害賠償額を算定した裁判例も存在しており、判断は統一されていません。ただ、理屈の上では、どうしても10年の任期を前提にした残存任期に基づく損害賠償額算定とならざるを得ないと考えられます。
一方、後者については、任期の定めがないということは、いつ解任されてもおかしくないということになりますので、基本的には損害賠償義務を負わないと考えられています(つまり、残存任期に基づく役員報酬を得られる合理的期待は法律上保護されないということです)。
ところで、役員報酬以外に役員賞与が含まれないのかという点も問題となりえます。
この点については、役員賞与を必ず支給するルール(算定方法、支給時期など)があったと言えるのであれば、会社は役員賞与相当額についても損害賠償義務を負担すると考えられています。逆に、役員賞与は、業績等に応じて株主総会で都度決議をしていたというのであれば、確実に支給されるものとは言い難いため、損害には含まれないことになります。
(4)使用人兼務取締役を主張する方法
上記1.でも触れましたが、取締役と使用人(労働者)は法的地位を異にするものの、両者の地位は同時に併存しえます。例えば、取締役として業務執行しつつも、一方で経理部長や開発責任者等の肩書で現場業務にも従事している場合、両者の地位が併存しているので使用人兼務取締役として取り扱われることになります。
さて、使用人兼務取締役の場合、対象者が取締役として解任されたとしても、使用人(労働者)の地位まで当然に剥奪されたことにはなりません。
労働者の地位まで剥奪するのであれば、解雇手続きを踏む必要があります。そして、解雇手続きを実施する場合、「客観的に合理的な理由があり、かつ当該理由が社会通念上相当」な理由がない限り、解雇することができません(労働契約法第16条)。
以上の地位の相違を捉えて、解任対象となった取締役は、正当性がないとして損害賠償を請求しつつ、使用人としての地位は存続しているとして勤務を希望するという対抗手段を講じることが可能となります。
5.役員解任の訴え
上記までにおいて、取締役は、理由の有無を問わずいつでも解任可能であることを説明してきましたが、これは株主総会で解任の決議ができること、すなわち、支配株主が対象となる取締役の解任を要望している場合を前提にしています。
もし、少数株主が一部の取締役の解任を希望したとしても、支配株主が解任を了承しない場合、解任することは不可能です。
ただ、このような多数決原則を貫いた場合、不正行為のある取締役を放置することとなり、会社に悪影響を及ぼしかねません。
このような事態に備え、会社法第854条では役員解任の訴えという制度を設けています。
【会社法第854条第1項】
| 役員(第329条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第323条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から30以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。
(以下省略) |
かなり要件が厳しく、訴訟必須となるため、そう簡単に利用できる制度ではありませんが、「取締役の解任」という本記事のテーマに関係する制度であることから、ここで取り上げておきました。
6.リーガルブレスD法律事務所のサポート
リーガルブレスD法律事務所は、通算200社以上の顧問弁護士として活動し、またスポットでの法律相談等も多数お受けしています。
そして、取締役による派閥争いや、創業者死亡に起因するお家騒動などの複数の事例に関与することで、取締役の解任にまつわる問題解決やサポート業務の提供を行ってきました。
クライアントの皆様には、現場実務対応で得られた知見とノウハウを活用し、できる限り有利な形での解決を図ることができるよう日々尽力しています。
【リーガルブレスD法律事務所が提供するサポート内容】
リーガルブレスD法律事務所では、ご依頼者様のニーズに合わせて、次のようなサービスをご提供しています。
■取締役解任に向けた事前準備・実行サポートプラン
| ご依頼内容(例) | 取締役を円滑かつ法的に有効な形で解任したい。手続きミスによる無効リスクを避けたい。 |
| サポート内容 | ・定款、会社法に基づく解任手続のフルチェック
・招集通知や議案書、議事録の文案作成 ・株主構成分析による議決権確保のアドバイス ・トラブル回避のための事前交渉支援(退任勧奨含む) |
| 主な利用者 | ・経営陣(代表取締役・支配株主)
・内部対立を抱える中小企業オーナー ・事業承継後の体制再編を検討している経営者など |
| 弁護士費用 | 20万円(税別)〜
(※規模・内容により応相談) |
| 実施方法 | ・オンライン/対面での打合せ
・書類レビュー・作成(Word/PDF対応) ・緊急時の即日対応体制あり(要追加費用) |
■役員人事紛争予防コンサルティングプラン
| ご依頼内容(例) | 将来的な役員間紛争や解任トラブルを未然に防ぎたい。 |
| サポート内容 | ・定款、株主間契約、委任契約の予防的見直し
・「名ばかり取締役」や使用人兼務の地位整理 ・支配権、議決権確保のストック設計や種類株導入検討 |
| 主な利用者 | ・組織再編や事業承継を予定する企業
・経営の安定化を重視する創業者 ・トラブルを未然に防ぎたい中堅企業の管理部門など |
| 弁護士費用 | 月額5万円(税別)~
(※プロジェクト終了までの顧問契約形式) |
| 実施方法 | ・文書ベースでのレビュー、レポート提出
・月1回の定期ミーティング(オンライン対応) ・経営陣とのセッションによる戦略支援 |
■取締役解任への対抗支援(地位・損害賠償請求)プラン
| ご依頼内容(例) | 自分が不当に取締役を解任されようとしている、あるいは解任されたので法的に争いたい。 |
| サポート内容 | ・招集通知や議事録の適法性確認
・仮処分(開催禁止、議決権行使禁止)の申立支援 ・地位確認訴訟/決議取消訴訟/不存在確認訴訟の代理 ・損害賠償請求の検討と実行 ・使用人兼務地位の主張による雇用継続交渉 |
| 主な利用者 | ・経営排除リスクを抱える取締役
・使用人兼務取締役 ・少数株主でありながら役員を務める者など |
| 弁護士費用 | 別途お見積り
(※サポート内容によって異なります) |
| 実施方法 | ・書面の作成、提出、訴訟代理
・継続サポートの契約も可能 |
■スポット(単発)法律相談プラン
| ご依頼内容(例) | ・役員の解任を検討しているが、まずはリスクや進め方を簡単に聞いてみたい
・自分が取締役として排除されそうで不安。対応策を早めに知っておきたい ・会社の内情や株主構成に応じて、動くべきかどうか見極めたい |
| サポート内容 | ・想定される紛争構造の整理とリスク分析
・株主総会や取締役会の手続の概略案内 ・現時点でのベストな初動の方針案提示(攻守いずれでも対応) |
| 主な利用者 | ・役員間の不和、経営権争いが進行中の中小企業関係者
・今すぐ動くかは未定だが、法的リスクを把握しておきたい当事者 ・取締役の立場にあるが、近く解任される兆しを感じている人物など |
| 弁護士費用 | 1回90分当たり15,000円(税別) |
| 実施方法 | ・事前に関係資料の送付(契約書や通知書等)、事前検証
・オンライン面談 or 来所での対面面談 |
<2025年6月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。