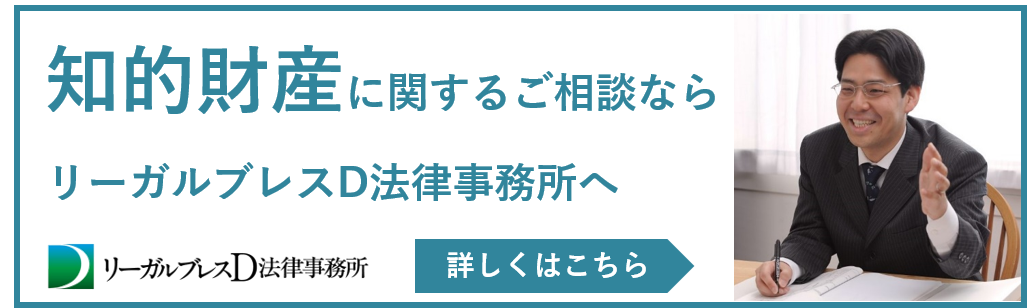システム開発取引に伴い発生する権利は誰に帰属するのか
【ご相談内容】
システム開発に関するコンペを経て、ユーザより前向きな意向が示されたことから、取引条件に関する交渉を行っています。
しかし、著作権等の権利帰属について交渉が難航しています。
そもそも、システム開発により発生する権利について、誰に帰属するのが原則となるのでしょうか。また、権利帰属の交渉を行うに当たり、どのような点に注意をすればよいのでしょうか。
【回答】
システム開発取引に伴い発生する権利としては、所有権、著作権(著作者人格権を含む)、特許権などが代表的なものとなります。また、権利とまでは言えないものの、法的保護に値するノウハウ・アイデア(営業秘密など)も意識する必要があります。
この点、前段にある所有権については有体物を作成した者、著作権(著作者人格権を含む)は著作者、特許権は発明者にそれぞれ帰属するというのが原則論とはなるものの、取引先(ユーザ)が関係する場合と社内人員(従業員等)が関係する場合とでは、法律上のルールが異なってきます。
そこで、本記事では、所有権、著作権(著作者人格権を含む)、特許権につき、権利帰属に関する考え方について解説を行います。
【解説】
1.所有権
システム開発に伴い所有権の対象となるものとしては、サーバ・ハードディスク等の電磁的記録媒体物、設計書・マニュアル等の書類といった有体物が想定されます。
(1)取引先との関係
例えは、ユーザがベンダに対してサーバ・ハードディスク等の電磁的記録媒体物の選定及び購入を依頼していた場合、ベンダが製造者より購入することになりますので、ベンダに所有権が帰属することになります。
そして、ユーザとベンダとのシステム開発取引契約書等で、サーバ・ハードディスク等の電磁的記録媒体物の所有権移転時期につき定めるというのが通常と考えられます(よくあるパターンとしては、サーバ・ハードディスク等の電磁的記録媒体物を引渡した時期、又は代金支払時期の2つです)。なお、契約書を締結していない、締結していても所有権移転時期について定めていない場合、理論上は売買契約の成立をもって所有権が移転すると考えられます。ただ、ベンダは代金を支払うまでサーバやハードディスク等の電磁的記録媒体物につき留置権を主張して引渡しを拒絶することになりますので、現実的には代金を支払うまではユーザが所有者として振舞うことはできないことになります。
一方、設計書・マニュアル等の書類については、ベンダが原始的に作成・生産するものである以上、ベンダに所有権が帰属します。
そして、設計書・マニュアル等の書類の所有権の移転時期についても、やはりユーザとベンダとのシステム開発取引契約書等で定めるのが通常です。
もっとも、設計書・マニュアル等の書類に関する所有権の取扱いについて、何らの定めがない場合、何らかの条件を満たせばベンダからユーザに当然に移転すると考えてよいのかは検討を要します。なぜなら、現実の取引実務では、設計書・マニュアル等の書類は貸与しているだけに過ぎず、システムの使用が終了した場合はベンダに返却することを念頭に置いたパターンも散見されるからです。サーバ・ハードディスク等の電磁的記録媒体物は、見積書や請求書等の内訳で代金額が設定されていますので、所有権の移転対象物であると言いやすいのですが、設計書・マニュアル等の書類については代金額の設定がされていないことも多いと思われます。
以上のことから、設計書・マニュアル等の書類については、所有権の帰属につき明確な合意がないことにはトラブルに発展しやすいことを知っておく必要があります。
(2)社内での取り扱い
まず、本記事内において「社内」とは、あくまでもベンダ(事業者)が雇用する労働者との関係を前提にしています。フリーランスや協力業者など社内に出入りするものの、労働者ではない人員は含まないことにご注意ください。
さて、従業員個人のお金でサーバ・ハードディスク等の電磁的記録媒体物を購入した、従業員個人が用意した紙に設計内容やマニュアルを記載したという場合であれば、それらの有体物に対する所有権は従業員個人に帰属するといえます。
もっとも、通常はベンダ(事業者)のお金でサーバ・ハードディスク等の電磁的記録媒体物を購入し、設計内容やマニュアルを記載する紙を用意するのもベンダ(事業者)です。
したがって、よほどの例外事情がない限り、ベンダに所有権が帰属すると考えて差し支えありません。
2.著作権
システム開発に伴い著作権の対象となるものとしては、システムを構成するプログラム(プログラムの著作物)、ユーザインターフェース(映画の著作物など)、マニュアル等の表現内容(言語の著作物など)といったものが想定されます。
(1)取引先との関係
著作権が誰に帰属するのかについては、著作権法で次のように規定されています。
【著作権法第17条第1項】
| 著作者は、次条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する権利(以下「著作者人格権」という。)並びに第21条から第28条までに規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 |
ちなみに、「著作者」については、著作権法第2条第1項第2号で「著作物を創作する者」と規定されています。
これらの著作権法の規定を前提とする限り、システム開発においてプログラム・ユーザインターフェース・マニュアル等を創作するのはベンダである以上、ベンダに著作権が帰属することになります。なお、著作権法では、著作物を創作するに当たり誰がお金を出したのかによって権利帰属を決するという立場を採用していません。このため、ユーザがシステム制作に要する費用を負担することと、著作権の帰属は全く関係しないことを押さえる必要があります。
上記が著作権の帰属に関する原則論となりますが、ユーザからすれば、お金を出す以上は著作権を譲ってほしいと要望するのが通常と思われます。
そのため、システム開発契約の交渉に際しては、著作権の帰属をめぐって様々なやり取りが行われます。そして、大まかには次の4のパターンで妥結することが多いようです。
①ベンダに著作権を帰属させるパターン
②ユーザに著作権を帰属させるパターン
③ベンダとユーザに帰属する著作権を分離するパターン
④ベンダとユーザが著作権を共有するパターン
①のパターンはベンダにとっては最も都合が良いものとなります。
もっとも、ユーザにとって最悪の内容かと問われるとそうとも言い切れません。なぜなら、ユーザとしては、システムの制作の支障が生じないようライセンスの付与を受ければ、必ずしも著作権の帰属にこだわる必要がないからです。例えば、将来におけるシステムの改修等は他の事業者に依頼することを予定しているのであれば、複製・翻案等の利用に関するライセンスを契約書に定めておく、システムの利用者がユーザ以外の第三者も想定されているのであれば、サブライセンス権を契約書に定めておくことで対処可能です。
権利の帰属よりも、どこまで利用可能かという視点が実は重要だったりします。
②のパターンはユーザにとって最も都合の良いものとなります。
ただ、考え方によってはベンダにおいて、あまり不利益が生じない場合もあります。なぜなら、著作物として保護されるためには創作性が必要となるところ、現場実務の感覚として、プログラムやビジネス向けユーザインターフェースについては、裁判所が創作性を簡単には認めない傾向があること、マニュアル等の表現内容についても、ありふれたものとなりがちであり著作物に該当しない場合も相当多いからです。
つまり、形式的には著作権を譲渡しているものの、その対象となる著作物が存在しないため、実質的にはベンダは何も制約を受けないということがあり得ます。
ここでも権利の帰属に拘る前に、そもそも著作物が存在するのかという視点が実は重要となります。
なお、ベンダの立場からすれば、著作権をユーザに帰属させた場合、ソースコードをユーザに開示することになるのではと心配になるかもしれません。ただ、これについてもソースコードがプログラムの著作物に該当するのかが問われますので、もし該当しないのであればソースコードをユーザに譲渡したことにはなりません。
したがって、開示する必要はないと考えることも十分可能です。
以上の通り、著作権の帰属とソースコードの開示は別問題なのですが、色々と誤解を招きやすいセンシティブなところもありますので、著作権の帰属とは別にソースコード開示の有無についてもシステム開発契約書等に定めておく方が無難といえます。
③のパターンはベンダとユーザが相互に譲歩したものであり、多くの契約書で見かける内容です。例えば、「成果物の著作権(著作権法第27条及び同法第28条の権利を含む)は、受託者又は第三者が従前より保有する著作物の著作権及び汎用的に利用可能なプログラムの著作権を除き、代金支払い完了後に受託者から委託者に移転する。」といった内容が典型的なものです。
ただ、上記のような内容は、実際のところ効果を発揮するのかと問われると微妙と言わざるを得ません。
なぜなら、「受託者又は第三者が従前より保有する著作物」の具体的内容が分かりませんし、上記②のパターンでも解説した通り、そもそも著作物が存在するのかさえ怪しいところがあります。また、「汎用的に利用可能なプログラムの著作権」については、何をもって汎用的と評価するのか客観的な基準がない状況であり、ユーザはもちろんベンダでさえ明確に示すことは困難と考えられるからです。
あえて言ってしまえば、ベンダとユーザ両者の顔を立てるためにお茶を濁した条項と言わざるを得ず、実際には何も定めていないに等しいと言ってよいかもしれません。とはいえ、どちらか一方のみに著作権を帰属させることでは具合が悪いというのであれば、取り得る選択肢といえます。
④のパターンもベンダとユーザが相互に譲歩したものであるという点で、上記③のパターンと同じです。ただ、数ある著作物を分類してどちらかの単独帰属とするのではなく、共有とする点で大きく異なります。
さて、共有、特に持分均等の共有とした場合、何となくフェアな感じがして、一番良い解決ではないかと思われるかもしれません。しかし、弁護士視点としては、一番やってはいけない解決法と言わざるを得ません。なぜなら、著作権法第65条第2項では、「共有著作権者は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。」と定められているからです。すなわち、単独では著作権を利用することができないということを意味しますので、ユーザはシステムを勝手に利用できませんし、ベンダはユーザにいちいちお伺いを立てなければなりません。
もちろん、一方当事者の同意なく、自ら利用することは可能である旨の特約をシステム開発契約書等に定めておけば、上記の問題を解消できます。しかし、著作権法第65条第2項の存在があまり知られていないため、定められてないことが非常に多いというのが執筆者の感覚です。
いずれにせよ、権利を共有状態にすることは色々と制約が大きくなりますので、できる限り単独帰属を目指して交渉を進めたほうが無難と思われます。
なお、後述しますが、著作権の共有と特許権の共有とでは、取扱いが異なることにも注意を要します。
著作権の帰属に関する交渉に基づき、条項化する場合の注意点等については、次の記事をご参照ください。
著作権に関する契約(利用許諾・ライセンス、譲渡、制作)のポイントについて解説
(2)社内での取扱い
ベンダの従業員が、システムを構成するプログラム(プログラムの著作物)、ユーザインターフェース(映画の著作物など)、マニュアル等の表現内容(言語の著作物など)などを創作した場合、著作権は従業員又はベンダ(事業者)のどちらに帰属するのか、という問題があります。
この点、著作権法には次のような規定があります。
【著作権法第15条】
| 1.法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
2.法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 |
いわゆる職務著作と呼ばれる規定となります。
一定の要件を満たす必要がありますが、ベンダ(事業者)の業務の一環として従業員が創作した著作物はベンダ(事業者)に帰属するのが原則となります。なお、著作権法第15条第2項はプログラムの著作物における職務著作の特則であり、“公表”の要件が不要となっています。
なお、特許法には職務発明と呼ばれる規定が存在するのですが、後述する通り、職務著作とは大きく内容が異なる点に注意が必要です。
3.著作者人格権
著作者人格権とは、主として公表権(著作権法第18条)、氏名表示権(著作権法第19条)、同一性保持権(著作権法第20条)を総称して呼ばれる権利のことです。
上記2.で記載したシステムを構成するプログラム(プログラムの著作物)、ユーザインターフェース(映画の著作物など)、マニュアル等の表現内容(言語の著作物など)のそれぞれについて、著作者人格権が発生しています。
取引先との関係
まず、著作者人格権は著作者が保有する権利であるため、ベンダに帰属します。
そうすると、上記2.(1)で解説した通り、ユーザとの間でその帰属をめぐって交渉事項になると思われるかもしれません。しかし、著作者人格権は一身専属権であり、そもそも譲渡することが不可能です。
【著作権法第59条】
| 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 |
ただ、ユーザからすると、著作権の譲渡を受けたにもかかわらず、システムの改修作業を行うと同一性保持権侵害としてベンダより訴えられるリスク、あるいは翻案権のライセンスを付与されたにもかかわらず、やはりシステムの改修作業を行うと同一性保持権侵害としてベンダより訴えられるリスクが生じるため、不都合と言わざるを得ません。
そこで、現場実務では、「受託者は、成果物について、委託者又は委託者から権利の許諾若しくは承継を受けた者その他委託者の指定する者に対し、著作者人格権を行使しない。」といった著作者人格権を行使しない旨の特約条項をシステム開発契約書等に定めることで対処しています。
特にユーザの立場からすれば、著作者人格権の処理については注意したいところです。
(2)社内での取扱い
上記2.(1)で引用した著作権法第17条にある通り、著作者人格権は著作者に帰属します。そして、上記2.(2)で引用した著作権法第15条の要件を充足する限り、職務著作としてベンダ(事業者)が著作者となります。
したがって、著作者人格権はベンダ(事業者)に帰属します。
4.特許権
システム開発契約の目的は、ベンダはシステムを制作しユーザに納品する点にあり、何らかの発明を行うことを目的とはしません。ただ、業務遂行過程で、偶然発明がなされる可能性も有り得るところです。
(1)取引先との関係
特許権は、発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者が出願し、設定登録することで成立します。したがって、ベンダとユーザのどちらが発明者なのかを特定しないことには権利の帰属先を確定させることができません。
このため、上記2.(1)で解説した著作権の場合と異なり、特許権の帰属については、シンプルに「発明を行った者に帰属する」とシステム開発契約書等に定めるのが通常です。もちろん、契約交渉を通じて、特許権及び特許を受ける権利をどちらか一方に単独帰属させる旨定めることも可能です。
なお、特許権につき共有扱いとする場合、著作権とは異なるルールが適用されます。
【特許法第73条】
| 1.特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2.特許権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定をした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその特許発明の実施をすることができる。 3.特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その特許権について専用実施権を設定し、又は他人に通常実施権を許諾することができない。 |
ポイントは特許法第73条第2項です。
特許権の場合、当事者は単独で特許発明を実施することが可能であるのに対し、著作権の場合、当事者単独で著作物を利用することができません(著作権法第65条第2項)。
特許法と著作権法との規律の相違を勘違いすることなく、システム開発契約書等に必要な事項を定めることが重要となります。
(2)社内での取扱い
特許については、職務発明と呼ばれる規定があります。
【特許法第35条第1項】
| 使用者、法人、国又は地方公共団体(以下「使用者等」という。)は、従業者、法人の役員、国家公務員又は地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明(以下「職務発明」という。)について特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する。 |
特許権は従業員に帰属するのが原則であり、事業者に帰属すると定める著作権法とは全く逆であることに注意を要します。
そして、取引先との間で、取引先に特許権を帰属させると定めた場合、従業員に帰属する特許権を、如何にして事業者の権利に移転させるのかが重要な社内課題となります(この課題を解消できない場合、取引先との契約違反に基づく責任追及を受けることになります)。
なお、職務発明にいう「従業員等」には、雇用契約を締結した労働者はもちろんのこと、フリーランスなどの委託関係に基づく者を含むと解釈されています。職務著作における従業員は雇用契約を締結した労働者に限定されている点と大きく異なることにも気を配りたいところです。
5.システム開発によって発生する権利処理につき弁護士に依頼するメリット
システム開発を進める上で、知的財産権を含む権利の管理は企業の成功を左右する重要な要素です。契約書における権利の帰属やライセンスの設定が不明確なままだと、後々高額な訴訟費用や損害賠償を求められる可能性があります。
弁護士に依頼することで、これらのリスクを避け、権利関係をクリアにすることができます。
また、他にも次のようなメリットがあります。
①複雑な法律を正しく理解するための専門知識
システム開発には著作権法、特許法、不正競争防止法などといった権利帰属に関する法律はもちろん、契約の履行ルールを定める民法や商法といった、様々な法律が絡みます。
これらの法律を非法律家が理解するのは難しく、またシステム開発特有の法解釈論を知っておく必要があります。
弁護士に依頼することで、これらの法律を的確に適用し、将来的なリスクを最小限に抑えることが可能です。
②契約書における知的財産権の帰属を明確化
システム開発を外部に委託する際、知的財産権の帰属を契約書に明確に記載することが重要です。たとえば、システム開発契約においてベンダが著作権を持つのか、ユーザが権利を取得するのかを曖昧にしてしまうと、開発完了後にシステムを改修する、他のプロジェクトで再利用する際に大きなトラブルとなる可能性があります。
弁護士は、こうした将来のことを見越して、契約の細部まで注意を払い、適切な条項を作成します。
③契約交渉力の強化
システム開発は、多額のお金が動く取引であり、マネーリスクを回避するためには事前の契約交渉が極めて重要となります。当たり前のことですが、契約書の内容が一方当事者にとって不利なものである場合、その当事者は、契約締結後に大きなリスクを抱えながらプロジェクトを進めていかなければなりません。
しかし、弁護士が交渉に加わることで、有利な条件を引き出し、権利関係を明確に定めることができます。
6.当事務所でサポートできること
当事務所は、複数のベンダの顧問弁護士として活動すると共に、ユーザからの依頼に基づくシステム開発に関する大小のトラブルを多数取り扱うことで、予防法務から紛争解決まで幅広くサポートを行ってきました。
また、迅速かつ丁寧な対応を心掛けており、企業の法務担当者や経営者から高い信頼を得ています。
当事務所の特徴として、以下の点が挙げられます。
①豊富な実績: システム開発に関する相談・トラブルを数多く手がけており、豊富な経験に基づくアドバイスを提供します。
②カスタマイズされたサポート: 企業の規模や業種に応じた法的サポートを提供し、それぞれのニーズに合わせた柔軟な対応が可能です。
③早期解決を目指す交渉力: トラブルが発生した場合、法廷外での早期解決を目指した交渉に尽力します。
システム開発取引を円滑に進めるために、当事務所の弁護士が全力でサポートいたします。契約書の作成、契約内容のチェック、トラブル解決に至るまで、あらゆる法的ニーズに対応し、安心してビジネスを進めていただけます。
<2024年10月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- 契約書があっても防げない! IT企業に蔓延する“契約トラブル”の正体と対処法
- IT企業に必要な契約書とは?弁護士が解説
- 商用利用は大丈夫? ChatGPTと切っても切れない著作権の関係について解説
- システム開発取引に伴い発生する権利は誰に帰属するのか
- IT企業特有の民事訴訟類型と知っておきたい訴訟対応上の知識
- ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説
- メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題
- 画面表示(UI)は著作権その他法律の保護対象になるのか?
- 令和5年改正不正競争防止法のポイントを解説
- オープンソースソフトウェア(OSS)利用時に注意すべき事項について(法務視点)