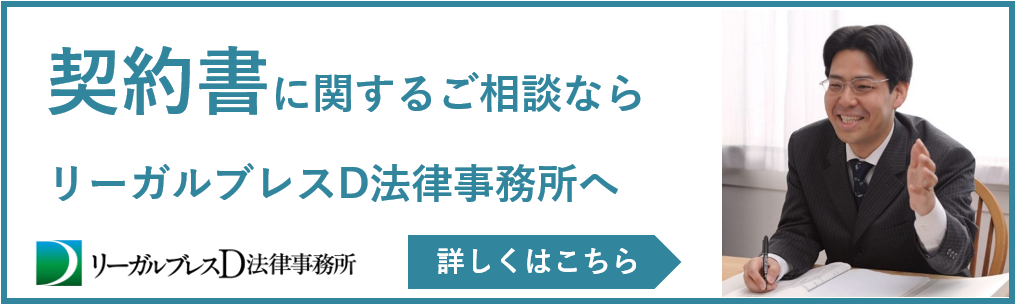契約の有効期間、更新、中途解約のポイントにつき、戦略法務視点で解説
Contents
【ご相談内容】
取引先と契約書を取り交わすことになりました。
ただ内容を確認すると、契約締結日については記載があるものの、契約の有効期間については一切触れられていません。
契約期間を定めない契約は有効なのでしょうか。
【回答】
契約期間を定めない契約であっても法的には有効です。そして、法的には「期間の定めのない契約」として取り扱われることになります。
さて、「期間の定めのない契約」と記述すると、永久に契約が継続するのでは…と思われる方もいるかもしれません。しかし、法律的には全く逆で、いつでも解約可能な契約を意味します。
この観点から、契約に縛られたくないと考える当事者は、いつでも契約関係から離脱できることを狙って、あえて期間の定めのない契約を選択することがあります。一方で、なるべく相手との契約関係を継続したいと考える場合、期間の定めのない契約を選択するべきではなく、一定の契約期間と自動更新条項をセットにした契約にするべきです。
このように、契約期間を定めるか否かは、相手との取引関係をどこまで強化するのかという戦略視点で判断する必要があります。また、契約期間を定めた場合、出口戦略としての中途解約の可否を検討する必要がありますし、契約期間が終了してもなお義務を課したい場合の事後措置についても考慮する必要があります。
本記事では、契約期間を定める意義と、契約期間を定めることで派生する問題とその対処法につき、解説を行います。
【解説】
1.契約期間を定める意義
例えば、1回で完結する売買契約の場合、契約期間を定める意義は乏しいかもしれません(ただし、製品保証(契約不適合責任、製造物責任など)の期限が重要な契約要素となる場合は、有効期限を定めますので、実質的には契約期間を定めることと同様となります)。
しかし、賃貸借契約や雇用契約のように契約期間が重要な要素となる場合はもちろんのこと、継続的な契約関係の場合、契約期間を定める必要があります。
なぜなら、継続的な契約において契約期間の定めがない場合、法的には「期間の定めのない契約」として取り扱われることになります。そして、期間の定めのない契約の場合、いつでも契約を解消することが可能というのが法律の原則だからです(例えば、賃貸借契約における民法第617条、雇用契約における民法第627条、請負契約における民法第641条、委任契約における民法第651条、寄託契約における民法第663条など)。
この結果、契約関係の存続を望んでいる当事者において、予期せぬところで契約終了という事態に陥るということもあり得ます。
このような事態を防止するために、契約期間を定めておく必要があります。
なお、期間の定めのない契約において、契約解消が制限されている裁判例も存在します。ただ、今日明日で契約解消することは認められないものの、一定の予告期間を設けて解消する限りは問題なしという裁判例が多いと言われています。
したがって、裁判例の傾向を踏まえても、完全に契約解消を否定することは難しいと考えたほうが無難であり、この点からも契約期間を定める意義が認められます。
2.どれくらいの契約期間を定めるのが適切か
具体的にどれ位の契約期間を定めるべきかについては、原則として当事者間の自由となります。ただし、次のような場合は法律に従う必要があります(代表的なものを列挙しています)。
・借地権の場合は原則30年以上(借地借家法第3条)
・借家権の場合は原則1年以上(借地借家法第29条)
・有期の雇用(労働)契約の場合は原則3年以内(労働基準法第14条)
・身元保証契約の場合は5年以内(身元保証に関する法律第2条)
・個人根保証(貸金債務)の場合は原則5年(民法第465条の3)
なお、法律上の制限がない場合、現場実務を見る限り、1~2年程度の契約期間を定めることが多いように思われます。
3.契約期間の定め方に関する注意点
法令用語は、国語的な用語例と異なる場合があり、期間の定め方については勘違いが生じやすいことがあります。例えば、
「本契約の有効期間は、×年1月1日から6ヶ月間とする。」
と定められていた場合、
①実際の契約締結日が×年1月1日だった場合、法律上は×年1月2日から×年7月1日までの期間を意味する
②契約締結日が×年1月1日前の場合、法律上は×年1月1日から×年6月30日までの期間を意味する
③契約締結日が×年1月1日後の場合、合理的解釈論としては×年1月1日から×年6月30日までの期間と考えられるが、そもそもバックデイトが有効なのか問題となる
という相違が生じたりします。
上記のような相違を回避したいのであれば、
「本契約の有効期間は、×年1月1日より起算して6ヶ月間とする。」
と定めることが望ましいといえます。
上記以外に、よく間違いが起こる契約期間の定め方として次のようなものがあります。
「本契約の有効期間は、×年7月1日より起算して2ヶ月とする。」
「本契約の有効期間は、×年7月1日より起算して60日とする。」
上段の場合、契約期間の終期は×年8月末日となります。一方、後段の場合、契約期間の終期は×年8月29日となります。
日常的には、2ヶ月と60日とは同じ意味を示す用語例と思われる方も多いかと思いますが、法令用語で用いる場合、月単位でカウントする場合は31日と30日は区別しない、日単位でカウントする場合は具体的日数でカウントするという相違が生じます。
契約期間の終期について意識を持たせる一番確実なものは、
「本契約の有効期間は、×年7月1日より起算して、×年×月×日までとする。」
といった終期についても具体的な日付で特定する方法となります。
4.契約期間の途中で終了させる方法
上記1.で記述した通り、期間の定めのない契約である場合、原則的には一方当事者の都合で中途解約することが可能です(但し、一定の予告期間が必要となる場合があります)。
しかし、契約期間を定めている場合、当然に中途解約が可能という訳ではありません(ちなみに、請負契約の場合は民法第641条により、委任契約の場合は民法第651条により中途解約可能ですが、相手当事者が被った損害を賠償する必要があります)。
そもそも契約期間を定めるということは、契約当事者双方に対して、当該契約期間中は契約関係からの離脱を禁止することを意味します。その裏返しとして、契約期間中であっても契約関係から離脱する方策として、中途解約に関する定めを設ける必要がないのかを検討することが重要となります。
一般的な中途解約条項は次のようなものです。
「甲又は乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して1ヶ月前までに書面で通知することによって、本契約を解約することができる。」
もっとも、上記のような一方当事者の都合だけで中途解約を認めてしまう場合、他方当事者としてはいつ契約の打切りが発生するか分からない以上、安心して取引を行うことができません。そこで、中途解約は仕方がないとしても、中途解約を行うに際しての条件を定めておくことで、中途解約による損失を防止するといった対策を講じることになります。
例えば、次のような条項です。
「甲又は乙は、本契約の有効期間中であっても、相手方に対して1ヶ月前までに書面で通知することによって、本契約を解約することができる。但し、解約を申出た者は、残存期間の×相当額を違約金として支払う。」
例えば、事業用物件の賃貸借契約において、賃借人が中途解約した場合、契約の残存期間の賃料相当額を違約金として支払うといった条項が定められることは珍しくありません。ただ、この違約金についてもあまりに過大な場合、公序良俗に反して無効とし一定額に制限するという裁判例が複数存在します。
したがって、中途解約を思い止まらせる方策として一定の違約金を課すとしても、その金額を青天井とすることは許されず、一定の制限を設けることがポイントとなります。
5.契約期間を延長する方法
(1)自動更新条項
契約期間を定めた場合、期間が満了すれば契約の効力は失われることになります。
しかし、双方当事者が引き続き取引を行いたいと考えている場合、再度新たに契約締結手続きをし直すというのは如何にも煩雑です。
そこで、契約期間を延長する方法として、自動更新条項を定めることがあります。例えば次のような条項です。
「本契約の有効期間は、×年×月×日より起算して2年間とする。但し、期間満了の2ヶ月前までにいずれの当事者からも何らの意思表示がない場合、同一の条件にて更に2年間更新されるものとし、以後も同様とする。」
上記条項例では、双方当事者が何も言わなかった場合、自動的に契約期間が延長されることになります。したがって、新たな契約手続きが不要であり、簡便な方法となります。
もっとも簡便な方法であるが故に、更新するつもりが無かったのに予告期間内に申入れを行うことを失念していたため、不必要な契約が延長されてしまった(なので、何とかして契約終了扱いにできないか)というご相談が後を絶ちません。自動更新条項の場合、契約管理が非常に重要となります。
ところで、上記は何ら申入れがない場合に自動更新するという内容ですが、逆に更新希望の申入れを行うことで自動更新扱いとするといった条項例も存在します。また、予告期間が一定の時期に限定されている(例えば契約期間満了日前の90日から60日まで等)という条項例も存在します。
自動更新条項を検討するにあたっては、
①更新扱いとなるための条件はなにか(積極的に当事者がアクションを起こす必要があるのか)
②予告期間は適切な時期・期間となっているか
を確認することがポイントです。
ところで、自動更新条項と似て非なる条項として次のような条項があります。
「本契約の有効期間は、×年×月×日より起算して2年間とする。但し、期間満了の2ヶ月前までにいずれかの当事者より申入れがあった場合、合意により更新することができる。」
合意更新条項と呼ばれたりするのですが、上記条項例の場合、あくまでも再度契約締結手続きをし直すことが前提となっています。つまり、一方当事者が契約更新したい旨申入れたとしても、他方当事者が契約更新に応じる義務はありません。
契約延長の可否についてコントロールしたいと考える場合は、上記のような合意更新条項を定めておいたほうが良いと考えられますが、できる限り契約関係を存続させたいと考える場合、契約審査段階で、合意更新条項ではなく自動更新条項に契約内容を修正するよう交渉することが肝要となります。
(2)更新拒絶
一方当事者が契約の更新(延長)を求めているにもかかわらず、他方当事者が契約の更新(延長)を拒絶することはできるのか、という点につき、特に継続的な契約関係が成立している場合に問題となり得ます。
ただ、この問題については、どういった状況下で更新が問題となっているのかを分けて検討する必要があります。
①自動更新条項が無く、契約期間満了時に一方当事者が更新を要請した場合
原則論としては、他方当事者が更新を望まない場合、更新を拒絶することは可能です(上記5.(1)の合意更新に関する記述を参照)。
もっとも、例えば、長期の取引を前提にした交渉経緯、契約履行に要する投資額回収の合理的期間を考慮した契約内容、過去において繰り返し更新が行われるなど取引実態による一方当事者の期待度、などの特別の事情がある場合、信義則上当事者に契約更新義務が認められる可能性があります。これ以外にも、一方当事者において取引依存度が高いと想定される場合は、更新拒絶によるトラブルが生じがちですので、契約終了の方法について注意する必要があります。
②自動更新条項があり、一方が更新を求めているにもかかわらず、他方が拒絶する場合
上記(1)で記載した自動更新条項の場合、やはり原則論としては、更新拒絶することが可能となります。
なお、自動更新条項が定められているということは、上記①の場合と比較すると、契約当事者における契約更新への期待が一定程度法的に認められることを意味します。そのため、上記①で記述したような例外パターンがやや広めに認められる傾向があり、裁判例によっては何故更新を拒絶するのかその正当事由を求めるものまで存在します。
程度問題とは言え、更新拒絶が認められない可能性についてやや意識を強く持ったほうが良いと考えられます。
なお、更新拒絶を含む継続的な契約関係が成立している場合において、その契約を解消する場合の方策や注意点については、次の記事をご参照ください。
継続的な契約関係を解消する場合の注意点について、弁護士が解説!
(3)更新と改正民法の関係
2020年4月1に民法が改正されました。
まず押さえておく必要があることは、改正民法が施行される前に締結された契約、すなわち2020年3月31日前に締結された契約であって、まだ契約期間が満了していない場合、旧民法が適用されます。
では、2020年3月31日前に締結されていた契約につき、2020年4月1日後に契約を更新した場合、更新後の契約は旧民法、改正民法のどちらが適用されるのでしょうか。
この点、合意更新された場合、実質的には新たに契約を締結したのと同じである以上、合意更新された時点で適用される法律、すなわち改正民法が適用されるというのはイメージが付くかと思います。
一方、自動更新の場合、特に当事者双方が何らの意思表明を行わない場合に自動的に更新されるという類型の場合、当事者の認識として新たな合意を行ったわけではないこと、むしろ従前どおりの取引を継続する意思であることを考慮すると、旧民法が適用されると考えることも可能です。しかし、立法担当者の解説によれば、「契約期間満了までに契約を終了させないという不作為が存在することをもって更新の合意と同視される」と指摘し、結論として自動更新の場合も、更新後は改正民法が適用されるとしています。
法解釈の権限は裁判所にありますので、裁判所がどのように判断するのか最終的な結論を待つほかないのですが(なお、本記事を執筆した2023年1月時点で自動更新後にどちらの民法が適用されるかにつき判断した裁判例は存在しないと思われます)、現時点では立法担当者の見解に従って処理するのが無難と考えられます。
以上のことから、結論として、更新した場合は一律に改正民法が適用されると捉えておけば事足ります。
6.契約期間終了後の措置
契約期間を定めた場合、当然のことながら契約期間が終了するという場面が生じます。
この点、契約期間が終了することで、双方当事者とも後腐れなく「では、さようなら!」と別れることができるのであれば、特に意識する必要はありません。
しかし、法律の世界では、たとえ契約期間が終了したとしても、一部の権利義務については効力を維持しておきたいという場合があります。代表的なものは次の2つです。
(1)特定の条項につき、引き続き効力を維持したい場合(残存効)
この点、秘密保持や競業禁止に関する条項であれば、契約期間満了後であっても、なお一定期間は引き続き秘密保持義務及び競業避止義務を相手当事者に課したいというニーズが高いと考えられます。
また、取引終了後に発生したトラブルに適用される条項、例えば、損害賠償責任に関する条項、製品・品質保証に関する条項(契約不適合責任、製造物責任に関する条項等)、合意管轄に関する条項などは、むしろ取引が無くなった後にその威力を発揮する条項といえます(取引関係が無くなると、どうしても対応が悪くなり話し合いによる解決が難しくなるため)。
さらに、契約期間終了後も製品やサービスを使用し続ける場合、相手当事者が保有する知的財産権のライセンスが継続されること(知的財産権侵害にならないこと)についても定めておきたい内容と言えます。
上記以外にも様々な残存条項が考えられるところですが、契約終了後も引き続き効力を有することを明らかにするためには、必ず契約書に残存効に関する条項を定めておく必要があります。例えば次のような条項です。
(例)
本契約の終了後であっても、第×条、第×条…の規定は、引き続きその効力を有する。
なお、残存条項を定める場合、契約終了後も永久に存続するとするのか、一定期間に限定して存続するとするのかについても検討が必要です。例えば、秘密保持に関する条項の場合、一般的には6ヶ月から3年の間で残存効を認めるという定めが多いと思われます。
(2)個別契約への影響
継続的な取引を行う場合、基本契約と個別契約の2種類を準備して取引を行うことが多いようです。
この場合、基本契約が契約期間満了により終了した場合、履行未了の個別契約にどのような影響を与えるのか、予め定めておくことが必要です。考え方としては、
①個別契約も失効する
②未履行の個別契約に限り、引き続き基本契約が適用される
のどちらかですが、一般的には②が選択されることが多いようです。その場合、次のような条項を定めておく必要があります。
(例)
本契約が期間満了により失効した場合であっても、現に存する個別契約については本契約の各条項がなおその効力を有する。
7.当事務所でサポートできること
単純に「いつからいつまで」という意味で契約期間を定めるだけであれば、弁護士に相談する必要はないかもしれません。もっとも、
・相手に対しいつまで契約による縛りをかけるべきか
・当方は契約の拘束力をいつまで受けることを許容できるのか
・契約の拘束力より離脱する術を確保するべきか
・相手が簡単に契約より離脱できない手段を講じるべきか
・契約が終了した場合であっても、なお契約の拘束力を維持する場面が想定できないか
などを戦略的に考え、これらを適切に契約書に反映させる必要があります。
また、当然のことながら、相手のある話ですので、当方が思い描いているシナリオ通りに進まない場面も想定され、その場合、代替案の提示など柔軟かつ迅速な戦略変更も必要となります。
相応の専門的知識と経験が必要となりますので、契約書の有効期間及びこれに派生する問題(中途解約や残存条項など)への対応について、是非当事務所までご相談ください。
<2023年1月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説
- ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説
- 競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点
- 電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説
- IT業界で注意したい偽装請負問題について
- メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題
- 検収完了後にシステム不具合が発覚した場合のベンダの責任、ユーザの対処法について
- 利用規約・約款に免責規定・免責条項を定める場合の注意点
- データ提供契約(ライセンス型)作成に際してのポイントを解説
- 画面表示(UI)は著作権その他法律の保護対象になるのか?