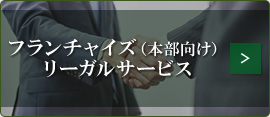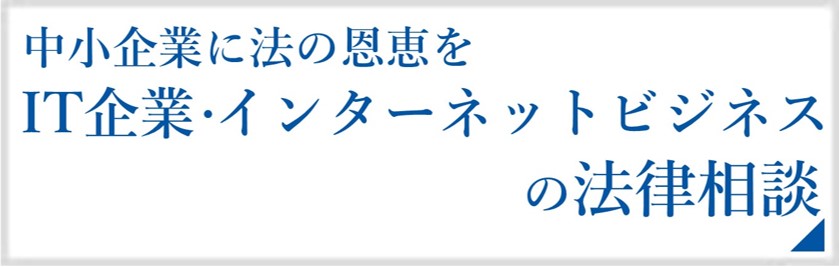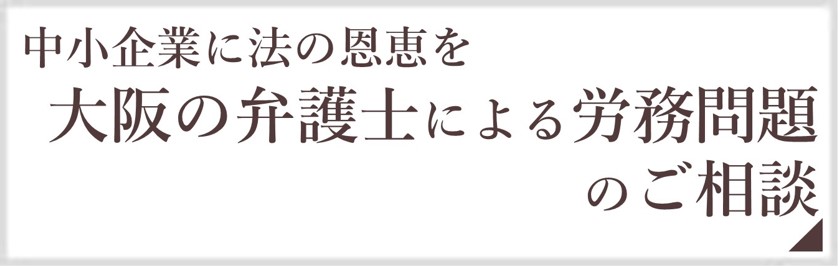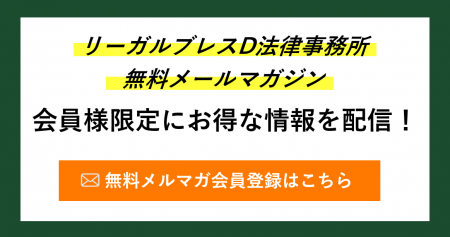人事トラブルを回避する法律実務の基礎~回答と解説~
1.労働時間・賃金に関するトラブルと解決の視点
(1)タイムカードがないことのリスク!?
Q:タイムカードを導入しないことによって…
正解⇒③
正確な出退勤時間を把握できないことになり、後々の裁判等で労働者の言い分に沿った出退勤時間がまかり通ってしまうリスクがある。
A:タイムカードを導入しないことによって、正確な出退勤時間を把握できないことになり、
後々の裁判等で労働者の言い分に沿った出退勤時間がまかり通ってしまうリスクがある。
⇒ 残業代を請求するには、正確な残業時間を算出する必要があります。
そこで、よく逆転の発想(?)で、タイムカードがなければ残業時間を算出することが不可能になる、
ということでタイムカードを導入しない、あるいは廃止したとおっしゃる事業者を見かけるのですが、
リスキーな判断と言わざるを得ません。
これは、そもそも論として使用者は労働者の労働時間を把握する法律上の義務があるとされているところ、
この義務を守らないのであれば、労働者が主張する労働時間に基づいて未払い残業代を算出するという裁判例が多数存在するからです。
つまり、事業者としては、証拠を残さない(労働時間の算定をごまかす)うまい手段であると考えるのもかもしれませんが、
法的には全く以て無意味な愚策というほかないところがあります。
主に使用者側で弁護士している私個人の立場からすれば、労働者側の残業時間の主張もおかしなところが多数あるのが普通なので、
反論する意味でもタイムカード等の残業時間が分かる資料が欲しいというのが本音です。
タイムカードを導入することは、むしろ会社を守るために必要であると考えていただければと思います。
(2)労働時間とは?労務管理の必要性
Q:賃金支払いの対象となる労働時間とは…
正解⇒③
使用者(会社・事業主)の指揮命令下に置かれている時間のことをいう。
A:賃金支払いの対象となる労働時間とは、使用者(会社・事業主)の指揮命令下に置かれている時間のことをいう。
⇒ 就業規則や労働契約書に定められている時間は、一般的には所定労働時間といい、
当初から勤務が予定されている労働時間というべきものとなります。
したがって、この所定労働時間に労働者が勤務しなかった場合は、
賃金を支払う必要がありませんし(ノーワーク・ノーペイ)、場合によっては懲戒処分の対象となります。
ただ、この所定労働時間を超えて勤務した場合(典型的には残業ですが、いわゆる始業前の朝活の場合もあります)、
労務を提供している以上は労働時間=賃金支払い対象時間とする必要があります。
そして、たとえタイムカードや勤怠管理表に記載されていなかったとしても、
実際に労務の提供を行っていたのであればそれは労働時間と考えなければなりません。
ただし、例えば、使用者(会社)が勤務するなと禁止している場合や使用者(会社)が命じていないにもかかわらず、
自主的に残業等した場合にまで労働時間=賃金支払い対象期間とすることは、使用者(会社)にとって不合理です。
したがって、賃金支払いの対象となる労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいう、というのが正解となります。
(3)休憩時間、始業前・終業後、在宅(持ち帰り残業)での業務遂行
Q:労働者全員に一斉に休憩時間を付与しなかった場合…
正解⇒③
使用者の指揮命令下にない限り、休憩時間を付与したことになる。
A:
労働者全員に一斉に休憩時間を付与しなかった場合、使用者の指揮命令下にない限り、休憩時間を付与したことになる。
⇒ 意外と知られていないのですが、労働基準法上は一斉に休憩時間を付与しなければならないと明記されています。
つまり、昼休みの交代制は原則違法ということになります。
(事業内容によっては、休憩時間を一斉に付与しなくてよいという例外規定が存在しますが、ここでは省略します)
ちなみに、昼休みの交代制を採用したいのであれば、労使協定を結んでおければ労働基準法違反とはなりません。
以上の通り、労働基準法上は休憩時間を一斉に付与しなければならないとされているのですが、一斉に付与しなかったから休憩できなかったのかというと、そういう訳ではありません。
実際に休憩時間を取っているのであれば、その時間は労務の提供を行っていない以上、
賃金支払いの対象となる労働時間としてカウントされません。
労働基準法に定められている休憩時間の一斉付与の問題と労働時間の算出の問題は別問題であることにご注意ください。
正解⇒③
使用者の指揮命令下にない限り、休憩時間を付与したことになる。
A:
労働者全員に一斉に休憩時間を付与しなかった場合、使用者の指揮命令下にない限り、休憩時間を付与したことになる。
⇒ 意外と知られていないのですが、労働基準法上は一斉に休憩時間を付与しなければならないと明記されています。
つまり、昼休みの交代制は原則違法ということになります(事業内容によっては、休憩時間を一斉に付与しなくてよいという例外規定が存在しますが、ここでは省略します)。
ちなみに、昼休みの交代制を採用したいのであれば、労使協定を結んでおければ労働基準法違反とはなりません。
以上の通り、労働基準法上は休憩時間を一斉に付与しなければならないとされているのですが、一斉に付与しなかったから休憩できなかったのかというと、そういう訳ではありません。
実際に休憩時間を取っているのであれば、その時間は労務の提供を行っていない以上、賃金支払いの対象となる労働時間としてカウントされません。
労働基準法に定められている休憩時間の一斉付与の問題と労働時間の算出の問題は別問題であることにご注意ください。
Q:予め定められた始業時刻前に、労働者が朝一番の会議のための資料作成のために早出した場合…
正解⇒③
原則として始業時刻から労働時間の開始時刻となるが、始業開始前に資料作成をすることが使用者より義務付けられていた場合は、早出した時間から労働時間の開始時刻となる。
予め定められた始業時刻前に、労働者が朝一番の会議のための資料作成のために早出した場合、
原則として始業時刻から労働時間の開始時刻となるが、
始業開始前に資料作成をすることが使用者より義務付けられていた場合は、早出した時間から労働時間の開始時刻となる。
⇒ 先ほどのQAで、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間」ということを解説しました。
例えば、従業員にもいろいろなタイプがあり、業務開始前に準備を完了させないことには
気持ちよく仕事をスタートさせることができないといって、早出をする人もいるかもしれません。
しかし、早出することを使用者(会社)が命じていないのであれば、
それは使用者の指揮命令下にあったとは言えない以上、労働時間とは言えません。
なお、明示的な指示があった場合は当然労働時間としてカウントされますが、
黙示的な指示(早出して資料作成を行うことが社内の暗黙のルールになっており、会社も特に禁止していなかった場合など)
があった場合も労働時間としてカウントされることになります。
実務上「黙示の指示」の有無は非常に判断しづらいところがあるのですが、
労働法上好ましくない社内風潮があるのであれば、少しずつでも是正していった方が後々のトラブルを防止するために有効です。
Q:所定労働時間終了後、会社内で行われている英会話研修に参加した場合…
正解⇒③
英会話研修への参加が義務付けられている場合に限り、英会話研修終了時間をもって労働時間の終了時刻として取り扱う。
所定労働時間終了後、会社内で行われている英会話研修に参加した場合、英会話研修への参加が義務付けられている場合に限り、
英会話研修終了時間をもって労働時間の終了時刻として取り扱う。
⇒ QC活動など勤務終了後に行われる社内活動について、どこまで労働時間として取り扱われるかについても、
やはり「使用者の指揮命令下」にあったか否かで判断されることになります。
この点、英会話の研修受講が完全任意とされているのであれば労働時間として取り扱われることは有りません。
しかしながら、研修受講を義務付けられている場合はもちろんのこと、任意と言いながら研修受講をしない場合は
人事評価に悪影響を及ぼすと言った場合は事実上強制されていることと同視できますので、
この場合は労働時間としてカウントすることになります。
Q:社内ルールでは残業許可制になっているにもかかわらず、上司の許可を得ずに残業した場合…
正解⇒③
残業に際して上司の許可が絶対条件となっており、かつ上司の許可が必要である運用が形骸化していないのであれば、所定労働時間の終了時間をもって労働時間の終了時刻と取り扱ってよい。
社内ルールでは残業許可制になっているにもかかわらず、上司の許可を得ずに残業した場合、
残業に際して上司の許可が絶対条件となっており、かつ上司の許可が必要である運用が形骸化していないのであれば、
所定労働時間の終了時間をもって労働時間の終了時刻と取り扱ってよい。
⇒ サービス残業問題や多額の未払い賃金請求などが表面化するにつれ、
残業を許可制にすることで残業時間の抑止を図るということが行われるようになりました。
最近の就業規則では、所定労働時間終了後に業務をする場合は上司の許可を得る、といったことが定められていることもよく見かけるのですが、このような許可制にすること自体は適法です。
問題なのは、許可制といいつつ全く社内で運用されていない、仕事量からして残業せざるを得ない状況であり
会社も上司もその点を認識していた、といった場合です。
形式的には上司の許可を得ていませんが、こういった事例の場合、
ほとんどの場合で黙示の許可があったと裁判では認定されることになります。
就業規則を制定しても、その内容どおりに運用されていなければ、
せっかくの規定が無意味になってしまうという典型例ですので、ご注意ください。
Q:終日、社外での業務遂行を行った場合…
正解⇒③
使用者において労働時間を算定しがたい事由が存在する限り、「事業場外のみなし制度」の適用はある。
終日、社外での業務遂行を行った場合、使用者において労働時間を算定しがたい事由が存在する限り、
「事業場外のみなし制度」の適用はある。
⇒ いわゆる事業場外のみなし労働時間の問題となります。
一昔前であれば、社外に出て行ってしまった場合、使用者(会社)は社外に出ていった従業員と連絡を取り合うことは物
理的に難しかったので、外出した=事業場外のみなし労働時間の対象と考えても問題はありませんでした。
しかしながら、最近では携帯電話やスマートフォンなどの端末の発達により
、いつでもどこでも社外にいる従業員と連絡を取り合えるようになり、
単純に外出したから事業場外のみなし労働時間制の適用があるとは言いづらい状態になっています。
実はこの事業場外のみなし労働時間制については、適用範囲についてかなり紛糾しています。
単純に携帯電話やスマートフォンでいつでも連絡が取れるから、
労働時間を算定しがたいとは言えない…とまで言い切れるかは疑問がありますが、
例えば、外出している従業員に対し、外出先での出来事をその都度携帯電話等で上司に報告させていたというのであれば、
労働時間の管理ができていますので、事業場外のみなし労働時間制度の適用は無いと考えるべきではないかと思われます。
話題になった阪急トラベルサポート事件の最高裁判例が出されて以降、
事業場外のみなし労働時間制度については、適用範囲を絞りこもうとする動きが強くなっていることにご注意ください。
Q:自宅に持ち帰って仕事を行った(いわゆる風呂敷残業)場合…
正解⇒③
原則として労働時間にカウントされることは無い。
自宅に持ち帰って仕事を行った(いわゆる風呂敷残業)場合、原則として労働時間にカウントされることは無い。
⇒ 自宅での活動時間は、労働者の自由である以上、
使用者の指揮命令下にありませんので労働時間としてカウントされないのが大原則です。
もっとも、会社で居残っての残業はダメなので、家で業務をやってこいと上司より命令があった場合、
自宅での業務遂行時間は労働時間としてカウントされることになります。
(ただし、自宅での業務遂行であるため、どのくらいの時間を費やしたのか客観的に算定することが難しいという問題があります)
また、業務のボリュームが多いため、社内で居残り残業しても到底終えることができない状況下で、
その点を会社も認識していたというのであれば、黙示的に自宅での残業命令を行っていたと認定されるリスクがあります。
従業員が抱えている業務の質・量を把握することが、未払い賃金問題を解消する最初の第一歩と言えるのかもしれません。
(4)年俸制or高給取りと残業代
Q:年俸制を採用していることを理由に、何時間働いても残業代を支払わないと主張することは…
正解⇒③
明らかな間違いであり、法律が定める労働時間を超えた場合は残業代を支払う必要がある
A:
年俸制を採用していることを理由に、何時間働いても残業代を支払わないと主張することは、
明らかな間違いであり、法律が定める労働時間を超えた場合は残業代を支払う必要がある。
⇒ 成果主義賃金体系の議論と混同されたのか、年俸制を採用した場合は残業代を支払わなくてもよいという誤解が
かなり広まっていましたが、これは残念ながら間違いというほかありません。
ただ、この誤解に基づき、数年前までは年俸制を採用している事業者は相当数ありましたが、
いざ残業代を請求されてしまうと全く対抗できないことが明らかとなり、
最近では残業代対策として年俸制を採用する事業者はほぼ存在しないのではないかと思われます。
ところで、欧米では一定額以上の年俸を支払っている場合は
残業代を支払わなくてもよいとする法制度を設けている国も存在するようです。
そこで、外資系企業に多いのですが、この欧米の制度をそのまま日本国内で導入し、
「高額の年俸を支払っている以上、この年俸の中には残業代を含んでいる」という理論構成をとってくる場合があります。
たしかに、実はこのような主張が認められた裁判例も過去には存在しましたが、非常にレアケースであり、
この裁判例に続く裁判例が皆無の状態です。
したがって、一定額以上の年俸を支払っているから残業代は支払う必要がないと認識することは、
現時点では誤りと考えたほうが良いかと思います。
正解⇒③
明らかに間違いであり、法律が定める労働時間を超えた場合は残業代を支払う必要がある。
他の従業員と比較して1.5倍以上の給料を支払っていることを理由に、
時間無制限で残業代が含まれていると主張することは明らかに間違いであり、
法律が定める労働時間を超えた場合は残業代を支払う必要がある。
⇒ 人情論として(?)、あれだけ高額の給料もらっているんだから、
当然それに見合った仕事をこなすためには長時間労働も当たり前である、ということは考えがちだと思います。
また、日本以外の国では一定の賃金を超える場合は残業代を支払わなくてもよいとする法律を定めているところもあるようです。
しかしながら、日本の労働法の場合、賃金がいくら高くても残業代を支払わなくてもよいとする制度はとっていません。
単純に労働時間が長ければ、それに応じた賃金を支払うよう定めています。
また、よくある主張として「入社時に従業員に対して、残業代込みであることを説明し、了解を得ている」という
事業者の言い分があるのですが、いわゆる定額(固定)残業代としての要件を充足しているのであればともかく、
そのような合意を行っても法律上は無効です。
したがって、給料が高いから残業代を支払わなくてもよいと考えるのは間違いという結論になります。
(※ホワイトカラーエクゼプションの議論はされていますが、法制度化されるかは未定です)。
(5)固定(定額)残業代の有効性
Q:いわゆる定額残業代(固定残業代、みなし残業代)は…
正解⇒③
基本給に残業代込みとする形の定額残業代はほぼ認められない可能性が高く、基本給とは別の手当として支給する形の方がよい。
A:いわゆる定額残業代(固定残業代、みなし残業代)は、基本給に残業代込みとする形の定額残業代はほぼ認められない可能性が高く、基本給とは別の手当として支給する形の方がよい。
⇒ 定額残業代(固定残業代、みなし残業代)はもともと法律上に明記されている制度ではなく、
裁判例の積み重ねによって法的有効性が確認されてきたというものになります。
そして、近時、定額残業代(固定残業代、みなし残業代)に関する重要な裁判例が立て続けに出現し、
その有効要件についてまだ流動的なところはあるものの、ある程度固まってきたと考えてよい状況です。
その有効要件ですが、私個人の見解にはなりますが、
①固定残業代の定義や内容を就業規則等に明記すること(基本給や他の手当てと明確に区分すること)、
②個別の労働契約書において、固定残業代として支払う具体的金額とそれに対応する残業時間を明記し、労働者の了解を得ること、③労働契約書に記載した残業時間を超えた場合は別途残業代を支払うことを明記すること
(可能であれば、残業代の計算方法を明記することが望ましい)
④給料明細書において、就業規則及び労働契約書に従った手当の名称を用いること
(可能であれば、当月の残業時間を明記することが望ましい)が必要ではないかと考えています。
定額残業代が無効となってしまった場合、当然のことながら既払いの残業代として控除することができませんし、
基礎賃金の算定に際しての「1カ月の賃金」に組み込まれてしまいます。
二重の意味で痛手になりますので、早急に見直すべき内容だと思います。
Q:社内階級として部長職や課長職に就任している者に対し、何時間働いても残業代を支払わないと主張することは…
正解⇒③
労働基準法上の管理監督者に該当すれば残業代の支払い義務はないが、該当することは稀であり、
基本的には残業代支払い義務が生じると考えたほうが良い
社内階級として部長職や課長職に就任している者に対し、何時間働いても残業代を支払わないと主張することは、
労働基準法上の管理監督者に該当すれば残業代の支払い義務はないが、
該当することは稀であり、基本的には残業代支払い義務が生じると考えたほうが良い。
⇒10年近く前にかなり話題になった、「管理者」と「管理監督者」に関する設問となります。
設問にもある通り、社内・組織体制上の職位として部長職や課長職などの上長を置くこと、これ自体は全く問題ありません。
ただ、残業代を支払わなくてもよいとされる労働基準法上の「管理監督者」に、
このような部長や課長が該当するかは全く別問題です。
部長や課長職に就いていれば問題ないと考えている方もいるかもしれませんが、
残念ながら肩書や名義付与だけでは該当するとはいえません。
どういった労働者が労働基準法上の管理監督者に該当するのかについては、いろいろと考え方があるのですが、
ただ、正直なところ、現在の裁判実務を踏まえると「管理監督者」に該当する労働者はほぼ皆無ではないかと思われます。
したがって、長時間労働に伴う残業代対策として、役職を付与することで対応するという方針はとらないほうが無難です。
なお、いわゆるマクドナルドの店長が管理監督者に該当しないという裁判例が出されて以降、対策として講じられたのは、
部長職や課長職の労働者を管理監督者と捉えるのではなく、
管理職手当を固定(定額)残業代と位置づけて残業代をあらかじめ支払うという方策になります。
ただ、固定(定額)残業代である以上、基本給や他の手当てと明確に分離され、何時間分の残業に該当するのか、
超えた場合は清算する(超過分を支払う)といった運用を適切に行う必要があります。
したがって、単に管理職手当を支払っていたから残業代を支払っていた、とはならないことに注意が必要です。
2.退職・解雇に関するトラブルと解決の視点
(1)会社より労働契約終了を申し出ることはリスクしかない!?
Q:内心では解雇するつもりがなくても、社長が「明日から来なくていい!」と労働者に対して言ってしまった場合…
正解⇒③
外部的に表示した言葉から判断する以上、解雇したといわれる可能性が高い。
A:内心では解雇するつもりがなくても、社長が「明日から来なくていい!」と労働者に対して言ってしまった場合、
外部的に表示した言葉から判断する以上、解雇したといわれる可能性が高い。
⇒ 教育的指導という言葉が通じなくなってきている世の中ですが、一昔前であれば「明日から来るな!」と社長が言っても、
社長は本気で言っているわけではないことは社長も労働者も共通認識として持っており、この共通認識に基づいて
労働者は歯を食いしばって出社し、社長に認めてもらう(見返す)べくがむしゃらに働くというのが、
ある種定番のようなところがありました。
ところが、近時は、社長が「明日から来るな」と言ってしまうと、労働者は文字通りに受け止めて、
本当に出社しなくなってしまうという場合が増加してきています。
そして、こういった労働者は労働基準監督署や労働組合、弁護士に駆け込み相談し、
「不当解雇である!」と主張して、徹底的に争ってくるというのが、むしろパターン化しているといっても過言ではありません。
そして、不当解雇であるとして争われてしまうと、会社側は法的にほぼ勝てないというのが実情であり、
この紛争のために多額の無駄金を使い、気持ちも収まらない…という負の連鎖に陥ってしまいます。
残念ながら、社長が人情家であり、内心ではクビにするつもりはないといったところで、内心は社長以外誰にもわかりません。
現実にあるのは社長の言葉であり、この発した言葉を基に物事が進んでしまいます。
不当解雇であるとして争われた場合、経験則上3桁の数字(単位「万」)の費用負担が生じることが多いです。
不必要な発言は厳に慎むというのが最良の対策であることを肝に銘じていただければと存じます。
Q:就業規則が存在しない、または就業規則や労働契約書等に解雇に関する規定が無い場合…
正解⇒③
懲戒解雇はできないが、普通解雇は可能な場合がある。
A:
就業規則が存在しない、または就業規則や労働契約書等に解雇に関する規定が無い場合、
懲戒解雇はできないが、普通解雇は可能な場合がある。
⇒ やや理論的な話になるのですが、労働契約を締結することで使用者(会社・事業主)は
当然に懲戒権を持つわけではありません。懲戒解雇を含めた懲戒権を使用者が有するためには、
懲戒事項を定めた就業規則の制定が必須となります。
したがって、就業規則が存在しない場合は懲戒解雇を行なうことは不可です。
一方、普通解雇とは、労働者が労働契約に従った労務の提供を行わないこと、
法的に構成するのであれば労働契約違反・債務不履行に基づく労働契約の解除となります。
したがって、労務の提供を行っていない・不十分であるというのであれば、労働契約の解除=普通解雇は可能となります。
ただ例えば、よく解雇事由として定めてある「社内秩序を乱し、他の従業員に悪影響を与えた」という事例の場合、
果たして労務の提供を行っていないといえるのか、やや微妙なところがあります。
(業務自体は適切に遂行している場合もあるので)
その意味で、解雇事由を明記した就業規則が存在しない場合、普通解雇ができる範囲は狭まるものと言わざるを得ません。
(2)退職勧奨に際しての注意点
Q:事業主・会社が労働者に対し、退職をお願いすることは…
正解⇒③
法律上の制限はなく、全く自由である。
A:
事業主・会社が労働者に対し、退職をお願いすることは、法律上の制限はなく、全く自由である。
⇒ 退職勧奨とは、あくまでも「辞めてもらえませんか?」というお願い・要請であって、
労働契約の終了という法的効果を伴うものではありません。
したがって、法律上は何らの定めが無く、退職勧奨を行なうこと自体は事業主・会社の自由です。
ただ、別問題とはなってしまうのですが、退職させることに熱心になり過ぎると
“退職強要”や“パワハラ”となってしまい、違法行為となってしまいます。
この線引きは難しいのですが、退職勧奨に際しての留意事項として
レジュメにチェックリストを添付しましたので、ご参照ください。
正解⇒③
原則問題は無いが、例えば、労働組合嫌悪による組合差別として退職勧奨するといった事例の場合は法律上問題になる。
A:退職勧奨を行う際、特定の労働者に対してのみ行うことは、原則問題は無いが、
例えば、労働組合嫌悪による組合差別として退職勧奨するといった事例の場合は法律上問題になる。
⇒ 前述の通り、退職勧奨については何も法律上の定めは無く、事業主・会社の自由です。
したがって、辞めて欲しいと考える従業員に対し、個別に退職勧奨を行なうこと、それ自体は何ら違法ではありません。
ただ、選択肢にも記載した通り、労働組合が絡む案件の場合は注意が必要です。
事業主・会社としては、業務命令に従わない反抗的態度や業務怠慢などの能力不足を根拠に
退職勧奨を行なうことが多いのですが、必ずと言っていいほど「組合差別だ」「組合嫌悪だ」として、
労働組合法上の違法行為である不当労働行為であるという反論が行われてきます。
当然のことながら、本当に能力不足があるのであれば退職勧奨を行なうことも適法ですし、
場合によっては普通解雇することも適法です。
しかし、組合に加入した従業員は労働組合法という強力な反論材料を持ち合わせていますし、
また、事業主・会社側も多かれ少なかれ労働組合に対する悪感情を持ち合わせているのも事実だと正直思います。
その意味で、組合員に対する退職勧奨を行うのであれば、事前に綿密な作戦を立てた上で実施する必要があります。
あと、最近では、最近では妊娠や子育てを理由とした退職勧奨は、マタハラとして問題になりえますので、注意が必要です。
Q:退職勧奨に応じない労働者に対し、繰り返し説得することは…
正解⇒③
必要に応じて再度説得することは問題ないが、行き過ぎると退職強要として違法行為となり得る
A:退職勧奨に応じない労働者に対し、繰り返し説得することは、
必要に応じて再度説得することは問題ないが、行き過ぎると退職強要として違法行為となり得る。
⇒ 繰り返しますが、退職勧奨それ自体は法律上の定めは無く、事業主・会社の自由裁量で行うことが可能です。
したがって、繰り返し説得することも原則問題ありません。
ただ、退職勧奨を行う側の担当者も仕事熱心のあまり(?)、退職に応じない従業員に対し、
あの手この手でだまし討ち的に(?)、あるいは脅迫して(?)、強引に退職を迫ることも事実として存在します。
このような禁じ手を使った場合は、詐欺による退職の意思表示の取消という問題や、
退職強要・パワハラとして違法であると後で言われかねません。
2つ前の設問解説にも記載した通り、その線引きは非常に難しいのですが、
レジュメ添付のチェックリストに記載した注意事項を念頭に置きつつ、
どうしても退職勧奨に応じないのであれば、
普通解雇にできないか証拠固めや証拠づくりを行うという方針に切り替えた方が良いかもしれません。
(3)会社から労働契約終了を正当に申し出ることができる場合とは?
Q:一定期間の無断欠勤や、私傷病休職の期間満了時点において復職しない場合において、自動的に退職扱いとすることは…
正解⇒③
就業規則等に退職扱いとして取扱う旨明記されているのであれば原則問題ないが、
特に定めが無い場合は解雇手続きを行う必要がある。
A:
一定期間の無断欠勤や、私傷病休職の期間満了時点において復職しない場合において、
自動的に退職扱いとすることは、就業規則等に退職扱いとして取扱う旨明記されているのであれば原則問題ないが、
特に定めが無い場合は解雇手続きを行う必要がある。
⇒ 雇用・労働契約を終了させるにはどうすればよいのかという問題なのですが、
いわゆる無期雇用の正社員である場合、期間の定めがありませんので(厳密には定年までですが)、
たとえ出勤しようがしまいが雇用・労働契約は継続しています。
そして、出勤しないことを理由に雇用・労働契約を終了させたいのであれば、
雇用・労働契約の解除=解雇手続きを行うというのが原則論となります。
つまり、出勤しないから退職扱いとして良いとする法律上のルールはどこにも存在しないのです。
しかし、退職扱いとすることを禁止する法律上のルールも一方では存在しませんので、
存在しないのであれば就業規則等で定めておけば原則ルールは有効となります。
したがって、就業規則等で退職扱いとすると定めておけば、この定めに従って対処可能となります。
なお、出勤しない以上、解雇すればいいじゃないか!と思われる方もおられるかと思います。
たしかに、法律上は問題が無いのですが、厄介なのが30日前に解雇予告を行うか(つまり30日後にしか解雇できない)、
30日分の解雇予告手当を支給するか(つまり金銭出費を伴う)、という二者択一の判断が迫られます。
出勤しないのにどうしてこんなことまで…と思われるかもしれませんが、残念ながら現行法上のルールであり致し方ありません。
このような現行法上のルールを回避したいのであれば、就業規則等を整備するというのが解決策となります。
正解⇒③
会社が期待する能力について労働者と認識共有し、期待値を下回っても何度も指導を繰り返し、
それでも改善が見込まれない段階に至って初めて解雇が可能となる。
A:勤務成績不良による解雇を行うことは、会社が期待する能力について労働者と認識共有し、
期待値を下回っても何度も指導を繰り返し、それでも改善が見込まれない段階に至って初めて解雇が可能となる。
⇒ 会社から見れば、全く役に立たないしミスばかりしている、指導しても耳を貸さない又は指導しても全く治らない、
その結果、他の従業員があおりを受けて士気低下にもつながっている、といった問題従業員について、
辞めさせたいと思うのが本音だと思います。
たしかに、一般論として勤務成績不良・能力不足による解雇、それ自体は認められています。
ただ、実際に解雇が法的に有効と判断されるためには、残念ながら非常に高いハードルがあるため、
ほとんどの会社ではこのハードルを乗り越えることができず、結果として解雇無効という判断に流れてしまうというのが実情です。
このハードルが、解雇する理由として「客観的に合理的な理由」があること、
及び解雇という選択肢を取ることが「社会通念上相当であること」という労働契約法16条の規定です。
この具体的内容として、某裁判例では「単なる成績不良ではなく、
企業経営や運営に現に支障・損害が生じ又は重大な損害を生じる恐れがあり、
企業から排除しなければならない程度に至っていることを要し、
かつ、その他、是正のため注意し反省を促したにもかかわらず、改善されないなど今後の改善の見込みもないこと、
使用者の不当な人事により労働者の反発を招いたなどの労働者に宥恕すべき事情が無いこと、
配転や降格ができない企業事情があることなども考慮」すると示されています。
つまるところ、やるべきことを尽くしたが如何ともしがたいという最終状況にまで陥らなければ、
解雇は困難という話になってしまいます。
正解⇒③
法律上は普通解雇手続きとなるので、解雇予告手続き又は解雇予告手当の支払い、
解雇の正当性(客観的かつ合理的な理由の存在と社会通念上の相当性)等を検討する必要がある。
A:いわゆる試用期間中の労働者に辞めてもらう場合、法律上は普通解雇手続きとなるので、
解雇予告手続き又は解雇予告手当の支払い、
解雇の正当性(客観的かつ合理的な理由の存在と社会通念上の相当性)等を検討する必要がある。
⇒ この「試用期間」については非常に誤解のある言葉だと感じています。
巷では、試用期間中の労働契約と正社員登用後の労働契約が2つ別々に存在していると思われているところがあります。
しかし、残念ながらこれは間違いです。法的には、入社させた時点で1つの労働契約しか成立しておらず、
労働契約期間中のある特定時期を試用期間と勝手に名づけているだけにすぎないと考える必要があります。
したがって、試用期間が終了した=労働契約が期間満了により終了したという話にはなりません。
そして、試用期間中であっても試用期間満了時であっても、労働契約の途中でやめさせる以上は「解雇」に該当します。
そして、解雇である以上、これまでに解説した、解雇予告手続き又は解雇予告手当の支払い、
解雇の正当性(客観的かつ合理的な理由の存在と社会通念上の相当性)等を充足するのか検討を行う必要があります。
なお、試用期間中であれば解雇予告手当不要と労働基準法に定められていないかと質問を受けることがあります。
たしかに、労働基準法第21条に規定があるのですが、あくまでも「14日以内」に解雇する場合です。
一般的に試用期間は3~6ヶ月程度を定めることが多いかと思うのですが、14日は優に超えています。
したがって、試用期間中の労働者を14日以内で早々に見切りをつけて解雇するという例外の場合以外は、
解雇予告手当の支給は必要になるのが実情です。
Q:労働者への賃金支払いに苦労するほど会社経営が苦しい場合…
正解⇒③
会社経営が苦しいことだけでは解雇は実施できないが、他の事情を考慮することによって、
有効な解雇手続きを実施できる場合がある。
A:労働者への賃金支払いに苦労するほど会社経営が苦しい場合、会社経営が苦しいことだけでは解雇は実施できないが、
他の事情を考慮することによって、有効な解雇手続きを実施できる場合がある。
⇒ 使用者(会社・事業主)としても、賃金を支払う余裕さえない以上は辞めてもらわないと困る!という必要性があります。
ただ一方で、経営苦境は労働者の責任とはいえず、労働者からすれば自分に非が無いのに解雇されては困る!
という反論もあるのであって、その反論は真っ当なものと言わざるを得ません。
そこで、実は労働法には整理解雇(いわゆるリストラ)については何も定めていないのですが、
裁判例の積み重ねによって、今では次の①~④を検討して解雇の有効性を判断するという実務が固まっています。
すなわち、①人員削減の必要性があること(経営が困難であること)、
②解雇回避努力を行ったこと(解雇以外の代替手段を尽くしたこと)、
③人選の合理性(リストラ対象者について社長の好き嫌いではなく、客観的かつ合理的な基準に基づいて実施すること)、
④手続きの妥当性(労働組合や労働者に対して十分な説明を行い、納得が得られるよう努力をすること)が考慮要素となります。
なお、よく世間で耳にする「希望退職の募集」は、上記でいえば②に関連して実施されるものです。
希望退職を募集して申込みがあった場合、合意退職してもらうことになります。
つまり、一方的に解雇するのではなく人員削減を図ったと評価されるのです。
裏を返せば、それなりの条件をつけて希望退職を募集したものの、
予定人数まで行かなかった場合にいよいよ整理解雇を実施しなければならない場面が訪れると考えればよいかと思います。
(4)社員を解雇せざるを得ないときにすべきこと
Q:法律上有効な解雇とするためには
正解⇒③
解雇の予告通知または解雇予告手当の支払いのみならず、
内容・原因を踏まえた解雇の正当性(客観的かつ合理的な理由の存在と社会通念上の相当性)が最低限必要となる
A:法律上有効な解雇とするためには、解雇の予告通知または解雇予告手当の支払いのみならず、
内容・原因を踏まえた解雇の正当性(客観的かつ合理的な理由の存在と社会通念上の相当性)が最低限必要となる。
⇒ 解雇を行う場合、形式的な手続きとして、
①30日前に予告を行う→労働契約は解雇言い渡し日から30日の経過をもって終了→30日間は就労させかつ賃金支払い義務ありとなる「予告解雇」を行うか、
②その日に解雇を行う→労働契約はその日に終了→30日分の解雇予告手当という金銭を支払う必要がある「即時解雇」のどちらかを選択する必要があります
(なお、例えば、10日前に解雇予告し、20日間分の解雇予告手当を支払うといった併用を行なうことも可能です)。
ただ、これらの手続きは必要条件であっても十分条件とは言えません。
解雇が有効となるためには、さらに実質論、すなわち解雇に値するだけの問題行動が存在することという要件を
充足させる必要があります。
ほとんどの事案の場合、上記形式面はクリアーできてはいるものの、
解雇に値するだけの問題行動が存在したことを証明できないため、
使用者(会社・事業主)にとって厳しい裁判所の判断が下されているのが実情です。
(いわゆる不当解雇トラブルと呼ばれる問題です)
なお、解雇が認められるためには、他にも解雇制限期間に引っかからないこと
(例:業務上の負傷・疾病による休業期間中及び復職後30日以内、産前産後休業期間中及び復職後30日以内などは解雇制限期間に該当)
解雇禁止事由に該当しないか
(例:労働組合員であることを理由とした解雇、婚姻・妊娠・出産等を理由とした解雇などは解雇禁止事由に該当)といった法律上定められている解雇禁止事項の該否についても検討する必要があります。
正解⇒③
形式的に懲戒解雇事由に該当しても、やむにやむを得ない(重大かつ悪質)ものといえる場合のみに限定して、
慎重に懲戒解雇手続きを実施したほうが良い。
A:懲戒解雇手続きを選択する場合、形式的に懲戒解雇事由に該当しても、
やむにやむを得ない(重大かつ悪質)ものといえる場合のみに限定して、慎重に懲戒解雇手続きを実施したほうが良い。
⇒ 解雇手続き、特に懲戒解雇処分は、刑事裁判でいえば死刑判決を下すようなものです。
死刑判決を行うのはやむにやまれぬ場合に限定されていることからもイメージができるかと思うのですが、
懲戒解雇についても、単純に懲戒解雇事由に該当したから懲戒解雇有効というロジックを裁判所は用いません。
特に、実際の裁判例では、懲戒解雇は厳しすぎるが、普通解雇であれば有効性を認めるというものまで存在しますので、
安易に懲戒解雇を選択することはリスクがあると考えたほうがよいかもしれません。
なお、いわゆる不当解雇リスクを回避するのであれば、できる限り自主退職に持って行く方が賢明という点では、
普通解雇、懲戒解雇ともに同じです。
ちなみに、不当解雇で裁判となり、使用者側が敗訴となってしまった場合、
労働契約はいまだに成立していたこと、そして労務の提供を拒絶したのは使用者の一方的都合に過ぎないこととなってしまい、
たとえ就労していなくても解雇を言い渡した日まで遡って賃金全額を支払う必要があります。
そして、職場復帰を認める必要もあります。このような状況下になってしまうと、
社内の雰囲気は最悪になってしまうこと間違いないのですが、残念ながら間違えた解雇手続きを行ってしまうと、
このような事態が発生してしまいます。
なお、懲戒解雇を実施するに際しては、労働者本人に弁明の機会を与えたか、就業規則上懲罰委員会にて結論を出すことになっていないか、労働組合との労働協約上、団体交渉を事前に行う必要があるのではないか、懲戒解雇処分を行う前に、同じ問題行動を原因とした懲戒処分(懲戒処分としての降格や賃金カット等)を実施していないか、問題となっている行動について従前発生した類似事例の懲戒処分とバランス・均衡がとれているかといったことも検討する必要があります。
また、非常に細かい話ではあるのですが、裁判の場合にポイントになるのが、
懲戒解雇の場合、懲戒解雇を言い渡した時点で会社が問題視した懲戒解雇の原因事由のみ対象として、
解雇の有効性が判断されることになります。
つまり、あとで他にも問題行動があったと追加主張しても聞き入れてもらえません。
この点からも懲戒解雇処分は非常に限定されていることがお分かり頂けるかと思います。
正解⇒③
懲戒解雇事由と除外認定事由とは異なることを意識しつつ、
懲戒解雇手続きを実施する前に、除外認定手続きを行うことが望ましい。
A:解雇予告手当の除外認定手続きを選択する場合、懲戒解雇事由と除外認定事由とは異なることを意識しつつ、
懲戒解雇手続きを実施する前に、除外認定手続きを行うことが望ましい。
⇒ 懲戒解雇、普通解雇を問わず、即時解雇を選択する場合、平均賃金30日分以上の解雇予告手当の支払いが必要になります。
ただ、解雇するくらい悪いことをしている労働者に対してお金を支払うのは、
まさに“盗人に追い銭”と思ってしまう使用者(会社・事業主)がいても不思議ではありません。
そこで、労働基準法上、解雇予告手当を支払いたくないのであれば、
労働基準監督署に対してその旨を申告し、審査してもらう手続きが設けられています。
このような手続きが存在するのであれば、是非とも利用したい!と考えられる使用者は多いと思うのですが、
実はこの手続きが非常に使えないものになっています。
選択肢にもある通り、解雇予告手当の除外事由に該当するものは
懲戒解雇事由より相当狭い内容となっています(典型的には横領をおこなった等の刑法犯罪に該当する場合)。
また、法律上は明記されていないのですが、事実上、解雇手続きを実施する前に労働基準監督署に申告し
審査を受ける必要があります。
(解雇手続き実施後に申告を行っても受付けてもらえないか、受付けてもらってもなぜか労働基準監督署より指導を受けたりします)
そして何より、労働基準監督署があれこれ難癖(?)を付けて、なかなか除外認定を認めようとしません。
したがって、解雇予告手当の除外認定手続きという制度があるのですが、
残念ながら、非常に使い勝手が悪い=実効性に乏しいと考えてもらった方がよいというのが実情です。