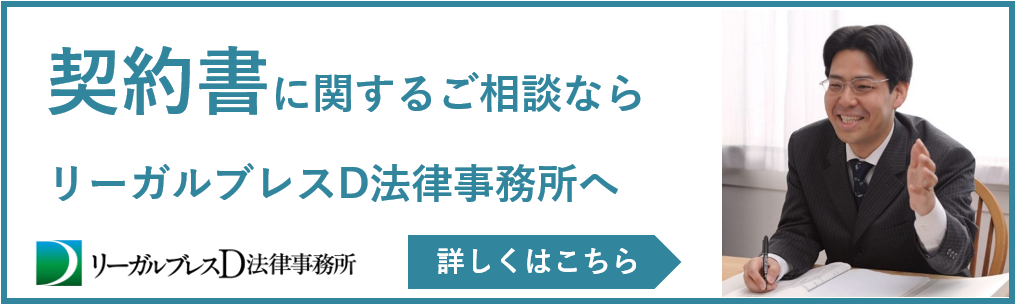契約書に定める「損害賠償条項」の考え方・チェックポイントを解説
【ご相談内容】
契約書のチェック業務を行っている際、損害賠償に関する条項が定められていなかったことから、条項を加筆修正しました。そうしたところ、取引先との交渉窓口になっている担当者より、「損害賠償は法律上定められている制度なのだから、あえて契約書に定める必要が無いのでは?」という指摘を受けました。
言われてみればその通りのような気がします。
損害賠償条項についてはどのように考えればよいのでしょうか。
【回答】
たしかに、損害賠償は法律上の制度として複数存在することから、契約書に定めていないから損害賠償請求ができなくなるという訳ではありません。
その意味では、絶対に定めなければならない条項とまでは言えません。
しかし、当事者間で合意すれば、法律上の損害賠償制度の内容を変更することができます。すなわち、自社にとって都合のよい損害賠償制度を契約により生み出すことが可能となります。もちろん相手のあることなので、自社のみに都合のよい契約内容となることは稀ですが、少しでも有利になる又はリスクヘッジができる損害賠償条項を契約内容として落とし込むことは極めて重要なことです。
本記事では、前半で損害賠償の法制度について簡単に解説した後、後半では現場実務で用いられる損害賠償条項を見ながら、何がポイントなのかにつき解説を行います。
【解説】
1.損害賠償条項を定める意義
上記の回答でも記載した通り、契約書に損害賠償に関する条項を定めるか否かは任意です。なぜなら、損害賠償責任については様々な形で法定化されているからです。
法定化されている損害賠償責任と同一内容を契約書に記載しても、あまり有意義とは言えません。そこで、まずは法律上定められている主な損害賠償責任について解説します。
(1)法律に明文化されている損害賠償責任
・債務不履行責任
債務不履行=契約違反を根拠にする損害賠償責任です。
これは民法第415条第1項に定められています。
| 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 |
条文を分解すると、
・契約違反があること(債務の本旨に従った履行をしない、履行が不能である)
・債務者(損害賠償責任を負う者)に帰責事由があること
・損害が発生していること
・契約違反と損害との間に因果関係があること
という4要件を充足すれば、債務不履行責任が認められると定められています(なお、厳密には帰責事由については、債権者が主張立証するのではなく、債務者に帰責事由が無いことを主張立証する旨規定されています。しかし、実際の交渉や裁判の場面では、まずは債権者が債務者の帰責事由を積極的に主張立証することが通常です)。
ところで、この帰責事由についてですが、2020年3月以前の民法では、「債務者の故意過失又は信義則上これと同視すべき事由」が必要とされ、債務者の帰責=過失責任という解釈がとられていました。
しかし、2020年4月1日に施行された改正民法では、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」損害賠償責任の有無を判断すると修正されています。このため、従来のような債務者の帰責=過失責任に限定されないこと、すなわち、債務者の帰責事由に含まれる内容が拡大したことを意味することに注意を要します。
以上のように、債務不履行責任が法定化されているにもかかわらず、あえて契約書に定める場合、
①契約違反となる具体例を明確化し疑義をなくすため
②帰責事由の主張立証責任の転換を図るため
③損害賠償の範囲を変更するため
といった目的で定めていないか確認することになります。
・不法行為責任
不法行為責任とは、基本的には契約関係の無い当事者間で発生する損害賠償責任のことを意味します。
ところで、不法行為責任の問題は契約関係がない損害賠償責任を前提とする以上、契約書を検討する上で知る必要のない知識ではと疑問に思われるかもしれません。
しかし、契約関係がある当事者間であっても、
①債務不履行責任ではなく、あえて不法行為責任を追及することも可能であること
②契約関係からは一義的に導かれない義務違反に基づく損害賠償請求を行う場合に不法行為責任を用いる場合があること
③契約書に契約当事者以外の第三者からの損害賠償を念頭に置いたルールを定める場合があること
といった実情を踏まえると、契約書を作成・検討する上では、不法行為責任を押さえておくことは必須といっても過言ではありません。
さて、民法に定められている不法行為責任にはいくつかの類型があるのですが、基本類型は民法第709条となります。
| 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
条文を分解すると
・権利(法律上の利益)の侵害
・故意又は過失
・損害の発生
・権利(法律上の利益)の侵害と損害との因果関係
という4要件が充足した場合、損害賠償責任が認められると定められています。
債務不履行責任でいう「契約違反があること」は、不法行為責任でいう「権利(法律上の利益)の侵害」に該当しますので、相違点は「債務者の帰責事由」と「故意又は過失」となります。ただ、執筆者個人の現場感覚となりますが、「債務者の帰責事由」と「故意又は過失」は明確な差異があるわけではないように思います。
したがって、法理論的には細かな相違があるものの、ひとまずは債務不履行責任と不法行為責任の発生要件はほぼ同一とイメージしても強ち間違いとは言えません。そのため、不法行為責任が法定化されているにもかかわらず、あえて契約書に定める場合、上記債務不履行責任の場合と同様の視点で確認することになります。
・製造物責任(PL責任)
請負、製造委託、制作物供給などの有体物の作成に関する契約や、製造物を対象とする売買契約の場合、契約書に製造物責任(PL責任)に関する条項が定められることが多いと思われます。
この製造物責任(PL責任)は、契約関係の無い当事者間で発生する損害賠償責任という点では不法行為責任なのですが、故意又は過失を要件としない(無過失責任)という点で、不法行為責任の特則と位置付けられるものとなります。この点については、製造物責任法第3条が次のように定めています。
| 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第3項第2号若しくは第3号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。 |
条文を分解すると
・生命、身体又は財産(但し当該製造物以外の財産)の侵害
・欠陥
・損害の発生
・権利(法律上の利益)の侵害と損害との因果関係
という4要件を充足した場合、製造物責任が生じることとなります。
製造物責任(PL責任)が法定化されているにもかかわらず、あえて契約書に定める場合、
①欠陥の定義を変更するため
②製造物自体を無過失責任の対象範囲に含めるため
③損害の範囲を変更するため
といった目的で定められていないか確認することになります。
(2)法律が予定している損害内容
契約書を読んでいると、通常損害・特別損害、積極損害・消極損害、直接損害・間接損害という色々な「損害」という言葉が飛び交うのですが、実は法律に出てくる用語例は、通常損害と特別損害のみです。これは民法第416条に定められています。
| 1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 |
民法第416条から分かるのは、特別損害が認められるためには債務者(損害賠償義務者)において「その事情を予見すべきであったとき」という要件が加重されるという点です。このため、通常損害・特別損害には何が含まれるのか(どのように分類されるのか)が重要となってくるのですが、実は一律に判断できるものではないとされています。
ただ、現場実務を見ていると、契約書の作成・検討において、損害賠償の範囲を狭めたい当事者は損害の範囲から特別損害を除外しようとし、損害賠償の範囲を拡大したい当事者は予見の有無を問わず特別損害を損害の範囲に包含しようとして、相互に牽制し契約交渉が難航するという事態に陥ったりします。
ところで、損害の範囲に含めるか否かで鬩ぎ合いが起こる用語例として、他にも積極損害・消極損害、直接損害・間接損害といったものがあります。
上記でも記載した通り、「積極損害・消極損害」、「直接損害・間接損害」は法律で定められている概念ではないため、実のところ定義自体が曖昧です。
一般的には、積極損害とは現実に発生した利益の滅失または減少のこと(例:物が損傷することで生じた修理費など)、消極損害とは将来の利益獲得を妨げられたことによる損失(例:逸失利益)のことをいいます。
一方、直接損害と間接損害ですが、
①被害者以外の者が損害賠償請求できるのかという区分(直接の被害者が被った損害は直接損害、被害者以外の第三者が被った損害は間接損害という考え方)
②契約違反行為又は不法行為と損害との因果関係の程度による区分(直接的な因果関係のある損害は直接損害、派生的・付随的な因果関係にすぎない場合は間接損害)
など多義的であり、法的観点からすれば意味の無い損害名称となります。
なお、これらの用語を契約書に用いることで、損害賠償の範囲を画そうとする交渉が現場実務で行われていますが、重要なのは用語例の有無ではなく、具体的にどのような損害が想定され、それをどこまで具体的に明記するのかが重要となります。
(3)法律が損害賠償責任を制限する場合
上記(1)で、法律が定めている主な損害賠償責任として債務不履行責任、不法行為責任、製造物責任の3つを取り上げました。また、上記(2)では損害の内容として、法律上は通常損害・特別損害という概念があること、また現場実務では積極損害・消極損害、直接損害・間接損害という用語例があることを取り上げました。
さて、これらの法律が認めている制度とは異なる損害賠償制度を設定したい場合、契約書にその内容を書き込むことになるのですが、これとは別に法律は一定の限界を設けています。
ここでは損害賠償制度について、法律が定めている限界につき主だったものを解説します。
-消費者契約法-
事業者と消費者が契約当事者となる場合に適用される法律となります。
損害賠償の制限については大きく3つのことが定められています。
【事業者の損害賠償責任(消費者契約法第8条)】
・事業者の免責を認める条項は無効
・事業者の一部免責を認める条項は原則無効。但し、軽過失に限る場合は有効。
【消費者の損害賠償責任(消費者契約法第9条)】
・事業者に生ずるべき平均的な損害を超える違約金条項は、その超過部分については無効
・年利14.6%を超える遅延損害金条項は無効
【その他(消費者契約法第10条)】
消費者の利益を一方的に害する条項は無効
-特定商取引法-
特定商取引法は消費者トラブルの多い取引類型、具体的には訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入につき規制している法律です。
損害賠償の制限については次の2つがポイントとなります。
・クーリングオフに伴い事業者が被った損害・損失を消費者が賠償する旨の条項は無効
・消費者が中途解約した場合の損害賠償金(違約金)につき、特定商取引法が定める上限額を超える条項は無効
-労働基準法-
労働基準法第16条は、「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定めています。
なお、労働契約の不履行によって実際に被った損害を労働者に請求すること自体は可能です。あくまでも労働基準法第16条が禁止しているのは、事前に違約金等の定めを置くことを禁止しているに留まります。
-独占禁止法、下請法-
やや抽象的な話となるのですが、損害賠償責任を著しく制限する条項、又は損害賠償の予定額・違約金を不当に高額に定めた条項については、優越的地位の濫用に該当するものとして無効と判断される場合があります。
また、下請法が対象とする契約(製造委託契約など)において、契約違反がないにも関わらず委託料を減額する条項(例えば協力金等の名目で一定額を減額することを内容とする条項)、又は契約違反の場合に違反の程度を超えた減額を認める条項(例えば違反の内容・程度を問わず委託料全額を減額する旨定める条項)については、下請法第4条第1項第3号(下請代金の減額)に違反するため、当該条項は無効と判断されることになります。
-民法(公序良俗違反)-
これも抽象的な話となるのですが、民法第90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。」と定めています。
例えば、一商品当たりの取引額が数千円程度であるにもかかわらず、当該商品に欠陥が見つかった場合は違約金として1000万円支払うことを定めた条項は、無効となる可能性が高いと考えられます。
なお、契約が定型約款に該当し、その条項に民法第548条の2第2項に定める不当条項に該当するものが含まれていた場合、当該条項については合意が成立しなかったものとみなすと規定されている点も注意が必要です。
-利息制限法-
損害賠償の中でも遅延損害金と呼ばれるものになりますが、金銭消費貸借契約の場合、利息制限法第4条及び第7条で遅延損害金の上限が定められており、これを超える遅延損害金を定めた条項は無効となります。
2.損害賠償条項を定める・チェックする際のポイント
上記1.で記述した通り、損害賠償に関する法制度はある程度充実しており、契約書に必ず定めなければならないものではありません。
もっとも、上記1.(3)に違反しない限り、損害賠償に関する法制度を当事者間の合意により変更することは可能です。この変更に関しては、次の4パターンが考えられます。
(1)発生要件
法律が定めている債務不履行責任、不法行為責任等の発生要件については上記1.(1)で記述した通りですが、要件を加重する、立証責任を転換する等につき当事者間で合意することで、次のように変更することも可能です。
(例1)
本契約に違反して乙に損害を与えた場合、甲は、甲に故意又は重過失がある場合に限り、その損害を賠償する。
(例2)
甲が本契約の目的に反する行為により乙に損害を与えた場合、甲はその損害を賠償する。
(例3)
本契約に違反しかつその違反が甲の責めに帰すべき事由であることを乙が証明した場合、乙は甲に対し、損害賠償を請求することができる。
(例4)
本契約に違反して乙に損害を与えた場合、甲はその損害を賠償する。但し、甲に故意又は過失がない場合はこの限りではない。
(例1)と(例2)は債務者(損害賠償義務者)の帰責事由を意識した条項となります。
すなわち、(例1)は債務者(損害賠償義務者)の帰責事由を法律より狭めている点で、債務者(損害賠償義務者)に有利な条項となります。
一方(例2)は、契約上の義務違反に留まらず本契約の目的からしてあるべき対応を取らなかった場合、債務者(損害賠償義務者)の認識及び認識可能性を問わず、損害賠償責任が発生すると定める点で、債権者(損害賠償請求権者)に有利な条項となります。
次に(例3)と(例4)は立証責任を意識した規定となります。
(例3)は、帰責事由があることを債権者(損害賠償請求権者)が証明しなければならず、法律とは真逆のことを定めている点で、債務者(損害賠償義務者)に有利な条項に修正されています。
一方(例4)は、債務者が帰責事由の無いことを証明しなければならないという点では法律と同じなのですが、免責される条件が故意または過失に限定されている点で債権者(損害賠償請求権者)に有利な条項となります。
(2)損害の範囲
損害の範囲については上記1.(2)で記述した通りですが、損害範囲につき広狭つけることを当事者間で合意することで、次のように変更することも可能です。
(例1)
甲又は乙は、本契約意に反することで相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する。
(例2)
甲又は乙は、本契約意に反することで相手方に損害を与えた場合、相手方に生じた一切の損害を賠償する。
(例1)は、損害の範囲を「直接損害」かつ「現実損害」かつ「通常損害」の3つに絞っています。当然のことながら、債務者(損害賠償義務者)にとって有利な条項となります。
ところで、このような条項を設ける趣旨は、おそらく逸失利益や弁護士費用、その他特別損害を認めないということだと考えられるのですが、直接損害や現実損害という用語は法律上用いられていません。したがって、この条項内容はよく見かけるのですが、実際のところ損害の範囲をどこまで絞り切れているのかは疑義が残ります。法律用語を意識して修正するのであれば、「…相手方に対し、その生じた損害(但し、逸失利益や弁護士費用、その他特別損害は除く)を賠償する。」と書いたほうが無難かもしれません。
次に(例2)は、「一切」とすることで、損害の範囲を際限なく拡大するという目的で定められる条項であり、債権者(損害賠償請求権者)に有利な条項となります。
ただ、このように定めたとしても“風が吹けば桶屋が儲かる”ではないですが、ありとあらゆる損害賠償が認められるわけではありません。損害の範囲として含めておきたいのであれば、あらかじめ具体的な損害内容を契約条項として明記したほうが良いと考えられます。なお、損害の内容として明記するのは交渉上やりづらいというのであれば、契約の目的条項を詳細に明記する(例えば売買契約であれば、買主は転売を想定していることを明記するなど)、あるいは債務者の義務内容を詳細に明記する(例えば売買契約であれば、中古品であっても品質保証や稼働保証を義務付けるなど)といった、他の契約条項の修正を図ることで、契約の趣旨目的からして「通常損害」に含まれると解釈できるよう対処するといったことが考えられます。
(3)損害額の制限or違約金
損害額(違約金)を高額化することについては一定の制限があることにつき、上記1.(3)で記述した通りです。一方で、損害額を一定の範囲内に抑え込むということも実務ではよく見かける内容となります。
(例1)
本契約に違反した場合、甲は事由の如何を問わず、違約金として金×円の支払い義務を負う。
(例2)
本契約に違反した場合、甲は、乙が被った損害を賠償する。但し、甲が負担する損害賠償額は金×円を上限とする。
(例1)は、例えば秘密保持契約において、秘密情報の漏洩があったのは事実だが、漏洩したことによる損害額を算定することが難しい場合に、具体的な違約金を明記することで損害賠償請求を容易にするといった目的で定められることがあります。その観点からすると、債権者(損害賠償請求権者)にとって有利な条項となります。ただ、違約金の額が著しく過大である場合は公序良俗違反等で無効となる可能性があります(民法第90条)。
次に(例2)は、損害の範囲については絞り込みを掛けず、しかし現実に債務者(損害賠償義務者)が支払う金額に上限を設けることで、債務者の責任を軽減するという目的で定められる条項となります。したがって、債務者(損害賠償義務者)に有利な条項となります。なお、現場実務でよく見かけるのは、「個別契約に基づく報酬相当額を上限とする」といった、要は受け取った金額をすべて返すことでチャラにする…という内容となります。
(4)請求期間
損害賠償請求期間を一定期間に制限する条項を設けることは、現場実務ではよく見かけることです。
(例)
甲は、商品の種類・品質・数量に関して契約内容に適合しないことを発見したときは、商品納品後6ヶ月以内にその旨を乙に通知しない限り、当該適合しないことを理由とする追完請求、代金減額請求、損害賠償請求及び契約の解除をすることはできない。
(例)は契約不適合責任(旧瑕疵担保責任)に関して定めた条項となりますが、民法第566条によると、「不適合を知ったとき」から「1年以内に」売主に通知する必要があると定めています。上記の条項(例)は、この2点から債務者(損害賠償義務者、売主)にとって有利なものとなります。
なお、いわゆる時効の利益を放棄することは不可能です(民法第146条)。このため、損害賠償請求権に関する時効期間を延長する又は短縮するような条項を定めても無効となることに注意が必要です。
3.当事務所でサポートできること
これから前向きにビジネスを始めようとする段階で、ビジネスが上手くいかなかった場合を想定した損害賠償条項に力を入れて検討するということは、心理的に難しいかもしれません。
しかし、契約書の役割は、何か事が生じた場合の解決ルールを提供するものです。そうであれば、損害賠償条項こそ慎重かつ厳格に検討し、必要に応じて修正等を含めた契約交渉を行う条項となります。
ただ、様々な法律解釈論が絡み合うため、なかなか現場実務の担当者だけでは何がポイントなのか、どこか落しどころなのか見極めることは難しいと思います。こういった場合、是非弁護士に相談の上、納得のいく契約内容を掴み取ってください。
<2022年10月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- その「免責条項」は本当に意味があるのか?契約リスクを左右する責任条項の考え方
- そのSLA、本当に機能していますか? 弁護士が教えるSLAの法的リスクと設計の勘所
- 契約書は誰が作成すべきか? 作成側・受領側が押さえたいポイントを弁護士が徹底解説!
- 偽装請負に該当するとどうなる? 契約形態・運用・制裁・是正策を弁護士が徹底解説
- IT取引の契約解消トラブル-無効・取消し・解除の実務対応
- 「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法
- 利用規約とは?作成・リーガルチェックのポイントについて弁護士が解説
- なぜテンプレートの利用規約はダメなのか?弁護士が教えるテンプレートの落とし穴
- 契約書のAIレビュー・チェックだけで万全!? 弁護士のリーガルチェックとの異同を解説
- アプリ事業者必見!スマホソフトウェア競争促進法で変わるスマホ市場の競争環境