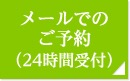契約書は誰が作成すべきか? 作成側・受領側が押さえたいポイントを弁護士が徹底解説!
契約書をどちらの当事者が作成するか。
一見シンプルなこの問いには、実は明確なルールが存在しません。
「雛形をもらったから」、「相手が先に送ってきたから」といった受け身の対応を続けていると、自社にとって重大なリスクを見落としてしまう可能性があります。
本記事では、契約書作成に関する実務慣行、法的な整理、そして一方当事者が契約書を作成・提示する際に押さえるべき視点を、わかりやすく解説します。
さらに、契約書を受け取った側が見落としがちなチェックポイントや、弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットについても触れています。
「契約書のやりとりは何となく進めている」
そんな方こそ、ぜひご一読ください。ビジネスを守る視点が、きっと見つかります。
Contents
1.契約書はどちらの当事者が作成するのか?
結論から申し上げると、どちらの当事者が契約書を作成しなければならないという法律上のルールはありません。
しかし、執筆者が知る限りの現場実務では、おおむね次のような状況となっています。
(1)業界慣習により作成者が決まっているパターン
・不動産賃貸借契約の場合、貸主が契約書を作成することが通常
・不動産売買契約の場合、宅建業者の支援を受けている側が契約書を作成することが通常
・地方自治体など公共団体との取引の場合、公共団体が契約書を作成することが通常
(2)相手より強い立場にあることを理由に作成者が決まっているパターン
・ライセンス契約の場合、ライセンサーが契約書を作成することが通常
・高額のお金が動く取引の場合、支払いを行う側が契約書を作成することが通常
・当事者間で情報格差のある取引の場合、情報を有する側が契約書を作成することが通常
(3)交渉の成り行きで作成者が決まるパターン
・交渉中により細かな条件を提示した側が契約書を作成することが多い
・契約書の締結を求めた側が契約書を作成することが多い
・企業規模の格差のある当事者の場合、大きい側が契約書を作成することが多い
なお、繰り返しますが、契約書はどちらの当事者が作成するべきなのかについて、法律上のルールはありません。一方当事者が自ら契約書を作成したいと申し出れば、相手方当事者も受け入れることが多いと思われます。
2.契約書を事実上作成しなければならない当事者とは?
上記1.では、どちらの当事者が契約書を作成しなければならないという法律上のルールはないと解説しました。
もっとも、様々な政策的な理由により、事実上一方当事者が契約書を作成しなければならない(作成しないことで不利益を受ける)というパターンも存在します。
例えば、次のようなものです。
(1)下請法に基づく書面交付義務との関係
下請法(正式名称は下請代金支払遅延等防止法)に定める取引類型でありかつ親事業者に該当する場合、親事業者は下請事業者に対し、次に定める事項を記載した書面を交付する義務があります。
| ①親事業者及び下請事業者の名称(番号、記号等による記載も可)
②製造委託、修理委託、情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日 ③下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう、明確に記載する。) ④下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、役務が提供される期日又は期間) ⑤下請事業者の給付を受領する場所 ⑥下請事業者の給付の内容について検査をする場合は、検査を完了する期日 ⑦下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが、算定方法による記載も可) ⑧下請代金の支払期日 ⑨手形を交付する場合は、手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期 ⑩一括決済方式で支払う場合は、金融機関名、貸付け又は支払可能額、親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日 ⑪電子記録債権で支払う場合は、電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日 ⑫原材料等を有償支給する場合は、品名、数量、対価、引渡しの期日、決済期日、決済方法 |
上記事項を見ればわかるかと思いますが、主要な取引条件を網羅しており、契約書に記載するべき事項と重複します。したがって、親事業者は、事実上契約書(又は契約書類似の書面)を作成する義務を負担することになります。
なお、下請法は、2026年より「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」と名称が変更されますが、上記の書面交付義務は引き続き適用があります。
(2)フリーランス法に基づく書面交付義務との関係
フリーランス法(正式名称は特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)に定める取引類型でありかつ業務委託事業者に該当する場合、業務委託事業者は特定受託事業者に対し、次に定める事項を記載した書面を交付する義務があります。
| ①業務委託事業者と特定受託事業者の名称等
②業務委託をした日 ③特定受託事業者が提供する給付又は役務の内容 ④納期又は提供期間 ⑤納入場所又は提供場所 ⑥検収完了日 ⑦報酬額と支払日 ⑧手形、ファクタリング、電子記録債権等を用いて報酬を支払う場合は規則に定める事項、特定受託事業者との取引がいわゆる孫請(再委託)等に該当する場合において、元請からの支払いがあった日より30日以内に特定受託事業者に対して報酬を支払う場合は、規則に定める事項 |
下請法と重複する事項とフリーランス法独自の事項がありますが、やはり主要な取引条件を網羅しており、契約書に記載するべき事項と重複します。したがって、業務委託事業者は、事実上契約書(又は契約書類似の書面)を作成する義務を負担することになります。
(3)特定商取引法に基づく書面交付義務との関係
特定商取引法(正式名称は特定商取引に関する法律)に定める取引類型のうち、書面交付義務が定められている取引類型があります(訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)。
書面交付義務に違反した場合、いろいろな制裁を受けることになりますが、その中でもクーリングオフを受けるリスクがいつまで経っても残る点が挙げられます(必要事項を記入した書面を交付しないことにはクーリングオフ消滅のカウントダウンが始まらないため)。
したがって、リスクを回避したい事業者は、事実上契約書を作成する義務を負担することになります。
ところで、近時はZoomなどオンラインで取引を勧誘することが多くなっていますが、音声通話システムを用いているという点で電話勧誘販売に該当します。この点を失念して、必要な書面を交付していない事例をよく見かけますので、注意をしてほしいところです。
(4)労働基準法に基づく書面交付義務との関係
労働基準法では、労働契約を締結するに際し、使用者が労働者に対して一定の事項を記載した書面(労働条件通知書と呼ばれています)を交付する義務を定めており、これに違反した場合、使用者は刑事罰を受ける可能性があります。
この一定事項は、労働契約の主要条件を構成する事項であり労働契約書に記載するべき事項と重複します。したがって、使用者は、事実上契約書を作成する義務を負担することになります(現場実務では、「労働条件通知書兼労働契約書」といったタイトルを付けて、一定の記載事項を記した書面と契約書を一体化させていることが多いようです)。
なお、IT取引とは縁遠いのですが、建設業法に基づき注文者が発行する書面、宅建業法に基づき宅建業者が発行する書面なども、事実上一方当事者が契約書を作成する義務を負担していると言ってよいかもしれません。
3.一方当事者が契約書を作成するメリット・デメリットとは?
事実上一方当事者が契約書を作成する場面はありますが、上記1.で解説した通り、どちらの当事者が契約書を作成しなければならないという法律上のルールはありません。
しかし、契約書を作成するのは、正直面倒ですし時間もかかりますので、できれば相手方当事者に作ってほしい…という気持ちがあるのではないでしょうか。
そこで、契約書を作成した当事者が得られるメリット、デメリットを挙げておきます。
(1)契約書を作成した当事者が得られるメリット
主に次の4点が挙げられます。
| メリット | 概要 |
| 自社に有利な条件で初期案を提示できる | 取引条件(報酬額の算定、支払条件、責任範囲、免責事項、中途解約など)を、自社にとって望ましい形で構成できる。相手が「たたき台」として受け入れることで、そのまま大枠が確定する可能性がある。 |
| 契約交渉を主導しやすい | 自社案を基準に修正交渉が行われるため、交渉の出発点となる。相手が契約交渉に慣れていない場合、そのまま受け入れられることもある。 |
| 手続がスムーズに進む(時間・コストの管理がしやすい) | 契約書作成を相手任せにするよりも、自社ペースでコントロールすることができる。また、自社フォーマットや過去の契約テンプレートを活用することで、効率的に作成できる。 |
| 法務・コンプライアンス対応を自社基準で設定できる | 自社のリスク管理方針に基づいて、必要な条項(権利帰属、機密保持、個人情報保護、環境保護、暴力団排除、人権尊重など)を漏れなく反映できる。 |
(2)契約書を作成した当事者が被るデメリット
主に次の4点が該当します。
| デメリット | 概要 |
| 契約交渉が長引くおそれ | 条項内容が自社寄りであるほど、相手方当事者より「一方的」として反発される可能性がある。結果的に修正交渉に時間を要し、かえって非効率になる可能性も否定できない。 |
| 不十分・不正確な条項により、自社が損失を被るおそれ | 作成ミスや検討不足により、自社に不利な義務や曖昧な表現が残ったまま契約が成立してしまうリスクがある。 |
| 草案作成者側が不利益を負うおそれ | 後で誤り等に気が付いて修正を求めても、相手方当事者より「作成した以上、後で修正するのはおかしい」と指摘され、修正が難しくなる場合がある。また、契約締結後に解釈論争が生じた場合、「条項使用者不利の原則」を適用されるリスクが生じる。 |
| 業界慣習や特殊な法規制を見落とす可能性がある | 相手業界固有の取引慣習を十分に理解していない場合、不適切な条項を含んでしまう可能性がある。 |
(3)まとめ
上記の通り、メリット・デメリット双方が考えられるところですが、デメリットの大部分は弁護士などの専門家に依頼すれば解消可能です(もちろん、依頼費用が生じるという新たなデメリットが生まれますが)。
自社有利で進めていきたいのであれば、自ら買って出ても契約書の作成は行った方がよいといえます。
4.契約書を自ら作成する場合の注意事項
一方当事者が契約書草案を作成し、相手方当事者に提示する場合に確認したほうが良い事項をチェックリストにしました。
(1)全体方針・戦略面の確認
□自社が契約書を提示することを妨げる理由はないか
(上記1.で解説した業界慣習や当事者間のパワーバランスなどを考慮)
□相手方の業界や立場を理解しているか
(相手方当事者が属する業界の商習慣に配慮する)
□「たたき台として提示する」旨を共有したか
(一方的に押し付けるのではなく、変更の余地があることを予め表明する)
□過去の類似契約や雛形の活用可否を確認したか
(自社内にあるノウハウを活かすなど。但し、一切修正せず過去の契約書を用いることは厳禁)
(2)基本条件の確認
□契約の目的や背景が明確に記載されているか
(「前文」や「目的条項」での明示が望ましい)
□契約当事者の名称、住所、代表者名に誤りがないか
(相手方当事者に失礼がないようにする。なお、交渉窓口担当者が所属している会社と実際に契約を締結する会社が異なる場合は要注意)
□契約期間、更新条件は明確か
(適切な契約期間の設定、自動更新の有無を考慮する)
(3)主要条項の妥当性確認
□業務内容、成果物の範囲が明確か
(なるべく具体的に記載。別紙引用するのであれば別紙漏れがないよう留意する。具体的に記載しづらい場合、対象外業務、別途協議が必要となる業務を明記するなどの工夫を行う)
□報酬、支払条件が明記されているか
(報酬発生条件、報酬額算定方法、支払時期・方法の確認はもちろん、契約が途中終了した場合の清算方法などを明記することが望ましい)
□納入遅延、不具合への対応が明記されているか
(遅延に対する責任内容、不具合があった場合の対応範囲につき明記する)
□損害賠償の制限が設定されているか
(通常損害への限定、上限額の設定、故意・重過失は除外するなどのバランスを考慮する)
□知的財産権の帰属・利用が明確か
(成果物の権利帰属、利用ライセンスの有無・条件、第三者からの権利侵害警告対応などを明記する)
□秘密保持義務の範囲が妥当か
(対象となる情報、秘密保持期間、目的外使用の禁止、違反の場合の措置などを明記する)
□期間途中での契約解消が明記されているか
(約定解除事由の設定と行使条件、中途解約権の有無、契約解消した場合の清算ルール、契約解消後の残存条項などを明記する)
(4)相手方当事者との関係性確認
□一方的すぎる条項が含まれていないか
(全部免責、過度な違約金など相手方当事者からの反発リスクが高い内容がないか確認する)
□相手方からの合理的な修正要望を受け入れる余地を確保しているか
(草案提示の際に、修正の余地がある旨触れておくなど)
□反社排除条項その他コンプライアンス条項が含まれているか
(反社条項以外に、環境配慮、公務員への賄賂禁止、SDGs、人権配慮などを明記する必要性がないか確認する)
(5)形式・手続き面での確認
□契約書の体裁(ページ番号・条番号・見出し)が整っているか
(読みやすく、修正時に参照しやすい体裁になっているか確認する)
□弁護士や法務部によるリーガルチェックを行ったか
(特に初めて契約書を作成する契約類型や、高額取引の場合は必須と考えるべき)
□電子契約を予定しているか
(相手方当事者が電子契約に対応しているか確認する)
□テキストデータの契約書草案を提示しているか
(PDFデータの場合、修正がしづらく、場合によっては修正に応じないと相手方当事者に受け止められてしまうリスクがある)
5.契約書草案を受領した場合の注意事項
相手方当事者が作成した契約書草案を検証するうえで確認したほうが良い事項をチェックリストにしました。
(1) 全体方針・戦略面の確認
□「誰が、どのような立場で作成したか」を把握しているか
(雛形か、過去取引を流用したのか、本件のためだけに作成したのかによって検証レベルが異なると考えるべき)
□交渉のスタンスを事前に共有しているか
(相手方当事者に意見を述べることが可能な環境を整えてきたのか社内で確認する)
(2)基本条件の確認
□契約当事者の名称、住所、代表者名に誤りがないか
(当方、相手方当事者とも確認する。なお、交渉窓口担当者が所属している会社と実際に契約を締結する会社が異なる場合は要注意)
□業務内容が曖昧、不正確でないか
(業務範囲や内容が個別具体的か確認する。事前交渉段階で要望や確認していた業務はどの条項で含まれていると考えればよいのか詰めて確認する)
□契約期間、更新条件、解約条件は明確か
(契約期間の設定、自動更新の有無、解除や中途解約条件が適切かを確認する)
(3)権利・義務の確認
□責任・義務が自社に偏っていないか
(損害賠償、契約不適合、納期遅延などの責任が重くないかを確認する)
□一方的な免責条項が入っていないか
(相手方当事者のみ免責がある場合、草案全体としては不公平な内容となっている可能性が高いと認識するべき)
□違約金・損害賠償が適切か
(各当事者が負担する違約金が妥当といえるか、損害賠償請求に際して条件が付されていないか確認する)
□相手方の義務が不明確または一切ない形になっていないか
(相手方当事者に何をしてもらいたいのか今一度確認し、条項に反映されているか確認する。都合よく解釈せず、文言から形式的に読み取れるかを重視する)
(4)知的財産・秘密保持などの確認
□成果物や知的財産の帰属が明確かつ公平か
(一方当事者が制作したもの全てが相手方当事者に帰属すると定めることは、果たして公平な処理と言い得るのか確認する)
□秘密保持条項の範囲・期間が妥当か
(守るべき情報に対し、過度な拘束が生じていないか確認する)
□競業避止義務や再委託制限が過度でないか
(本件業務の遂行に支障が生じないか、相手方当事者以外の者との業務処理に支障が生じないか確認する)
(5)紛争解決方法の確認
□管轄裁判所の指定が一方的でないか
(相手方当事者の本店所在地に限定されている場合は修正を求める)
□準拠法が海外法になっていないか
(日本国以外の法令につき十分な情報がない以上、原則受入れ拒否で対応する)
(6) 形式・手続き面での確認
□誤字脱字、未記載、空欄がないか
(意味内容が変わるor勝手に加筆されるリスクもあることから、必要な修正を行う)
□対応すべき添付資料(仕様書・見積書等)が明記されているか
(仕様書等との矛盾抵触がないか確認する)
□電子契約に対応できるか
(自社の契約管理システムとの整合性を確認する)
□社内決裁・稟議が必要か事前確認したか
(相手方当事者の交渉窓口担当者の権限の有無・内容を把握すると共に、対案に対する回答までのスケジュール感を確認する)
6.契約書作成を弁護士に相談・依頼するメリット
契約書を一から作成すること、あるいは相手方当事者より提示を受けた契約書を1つずつ検証することは、思った以上に労力と時間がかかります。
また、大変遺憾ながら、必ずしも法律に明るくない方が作成または検証を行っても、押さえるべきポイントやリスク分担などへの配慮ができないのが実情です。
このような煩雑な作業から解放されたい、正確な情報を掴んで不安を取り除きたいと考えるのであれば、弁護士に相談・依頼するべきです。
上記以外にも、弁護士に相談・依頼するメリットは多くあります。
(1)法的リスクの見落としを防げる
契約書は、ビジネスを法的に裏付ける重要な文書です。
弁護士は「条文の背景にあるリスク」を読み取り、将来的な紛争の種を事前に摘むことができます。
例えば、外部協力会社を活用しながら成果物の制作を行うことが前提になっているにもかかわらず、再委託禁止条項が定められているといった場合、実務上業務遂行が不可能となるので修正を提言することになります。あるいは、成果物の著作権はすべて相手に帰属となっている場合、自社のノウハウを失うことを意味しますので、やはり修正を提言することになります。
(2)契約交渉を有利に進められる
契約交渉は法的知識だけでなく、「交渉の構造」、「どこで譲歩し、どこを守るか」という戦略が重要です。
弁護士の助言により、相手方の提案の背後にある意図や交渉余地を見抜き、主導権を握ることができます。
(3)自社に有利な条項設計ができる
弁護士は多数の契約事例を知っているため、自社にとって有利かつ法的に正当な範囲で相手方に受け入れられやすい形で条項を設計できます。
(4)紛争時に「勝てる契約書」を作ることができる
トラブル発生時、裁判や交渉の根拠となるのは契約書の文言そのものです。
弁護士が関与することで、「万一の際にも自社を守れる契約書」となる確率が格段に高まります。
(5)業界ごとの特殊な事情や規制に対応できる
例えば、IT業界に精通する弁護士であれば、業界慣習や行政動向(例えば、フリーランス保護政策など)を踏まえた契約整備が可能です。
(6)社内外への安心材料になる
「弁護士チェック済み」というだけで、社内の稟議や経営判断がスムーズになることもあります。
また、相手方に対しても「法的リスクを管理している会社」として信頼感を与えることができます。
(7)事後トラブルの対応コストを劇的に下げられる
契約書を整備せずにトラブルが起こると、弁護士に依頼するタイミングは「事後的紛争対応」になり、費用も数十万円〜数百万円になることが多いのが実情です。
一方、契約締結前の相談・依頼は「事前予防相談」になるため、数万円〜数十万円で対応できることが多く、結果的に大きなコスト削減につながります。
弁護士は「トラブルが起きたら相談する」存在ではなく、「トラブルを起こさないために活用する」存在です。
契約書の整備は、いわば事業運営の地盤づくりといえます。小さな綻びが、将来の大きな損害や信用失墜に直結することもありますので、未然に防止するためにもぜひ弁護士にご相談ください。
7.リーガルブレスD法律事務所のサポート
リーガルブレスD法律事務所は、通算200社以上の顧問弁護士として活動し、またスポットでの法律相談等も多数お受けしています。
そして、クライアントのニーズに応じた契約書の新規作成やリーガルチェックはもちろんのこと、契約締結交渉の支援、対案の提示、契約解釈の相違に基づく紛争解決など、契約関係にまつわる問題解決やサポート業務の提供を行ってきました。
クライアントの皆様には、現場実務対応で得られた知見とノウハウを活用し、できる限り有利な形での解決を図ることができるよう日々尽力しています。
【リーガルブレスD法律事務所が提供するサポート内容】
リーガルブレスD法律事務所では、ご依頼者様のニーズに合わせて、次のようなサービスをご提供しています。
■オーダーメイド契約書作成プラン
| ご依頼内容(例) | ・新しい取引のため、自社の立場で契約書を一から作成してほしい
・自社に有利な内容で契約条件を整理したい |
| サポート内容 | ・ヒアリングによる契約目的、取引実態の把握
・契約内容の設計(報酬、権利帰属、責任分担等) ・完全オリジナルの契約書案(Word形式)の作成 ・業界慣習、法規制(例:下請法、フリーランス法等)への適合確認 |
| 主な利用者 | ・新規取引の契約書を自ら提示したいスタートアップ企業、中小企業
・自社で契約書のひな形を持たない事業者 ・下請法、フリーランス法等の義務を遵守したい発注者 |
| 弁護士費用 | 8万円(税別)~
(※取引内容の複雑さ難易度、作成ボリューム等によって変動) |
| 実施方法 | ・初回ヒアリング(Zoom / 対面 / 電話)
・予め合意した時期までに初稿提示 ・要望に応じた修正 |
■契約書セカンドオピニオン・レビュープラン
| ご依頼内容(例) | ・相手方から提示された契約書案をチェックしてほしい
・自社に不利な条項やリスクがないか判断してほしい |
| サポート内容 | ・契約書案の全文精査
・リスクの洗い出し(コメント機能または別紙指摘表で対応) ・条項ごとの修正提案、理由の説明 ・必要に応じて対案条項の作成 |
| 主な利用者 | ・相手方から契約書が提示された、法務部がない中小企業
・自社に不利な条件を見抜けるか不安な個人事業主、フリーランス |
| 弁護士費用 | 6万円(税別)~
(※ページ数、内容の専門性等により変動 |
| 実施方法 | ・契約書データ(WordまたはPDF)をメールで受領
・予め合意した時期までにレビューシート返却 ・照会事項への回答 |
■スポット(単発)法律相談プラン
| ご依頼内容(例) | ・相手方から契約書案が提示されたが、内容が理解できず不安
・自社で作成した契約書に問題がないか、弁護士の意見を聞きたい ・契約交渉を進めるにあたって、戦略や優先交渉ポイントを整理したい ・下請法やフリーランス法など個別の法的制度の適用可否を確認したい ・緊急で弁護士の見解を求めたい(社内決裁や契約締結期限が迫っている) |
| サポート内容 | ・Zoom/対面による相談対応
・契約書案1件(6ページ程度まで)の事前確認含む ・相談後に必要に応じて簡易アドバイスメモ(メール形式)を送付 ・契約類型、リスク論点、法令チェック等に関する専門的な助言提供 |
| 主な利用者 | ・法務部がなく、判断に迷っているスタートアップや中小企業
・契約書を初めて扱う担当者、経営者 ・顧問弁護士がいない、または契約していない個人事業主、フリーランス ・契約交渉の直前にポイントだけ確認したい方 |
| 弁護士費用 | 1回90分当たり15,000円(税別) |
| 実施方法 | ・事前に関係資料の送付、事前検証
・オンライン面談 or 来所での対面面談 |
<2025年7月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- その「免責条項」は本当に意味があるのか?契約リスクを左右する責任条項の考え方
- そのSLA、本当に機能していますか? 弁護士が教えるSLAの法的リスクと設計の勘所
- 契約書は誰が作成すべきか? 作成側・受領側が押さえたいポイントを弁護士が徹底解説!
- 偽装請負に該当するとどうなる? 契約形態・運用・制裁・是正策を弁護士が徹底解説
- IT取引の契約解消トラブル-無効・取消し・解除の実務対応
- 「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法
- 利用規約とは?作成・リーガルチェックのポイントについて弁護士が解説
- なぜテンプレートの利用規約はダメなのか?弁護士が教えるテンプレートの落とし穴
- 契約書のAIレビュー・チェックだけで万全!? 弁護士のリーガルチェックとの異同を解説
- アプリ事業者必見!スマホソフトウェア競争促進法で変わるスマホ市場の競争環境