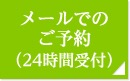そのSLA、本当に機能していますか? 弁護士が教えるSLAの法的リスクと設計の勘所
クラウド、SaaS、AIサービスがビジネスの中核にある今、
「障害が起きたとき、サービス提供者はどこまで責任を負うのか」
「SLAがあるけど、いざというとき役に立つのか」
…そんな不安を抱えたことはありませんか?
SLA(サービスレベルアグリーメント)は、単なるサービス説明書ではありません。
契約書に添付される文書である以上、サービス提供者の損害賠償責任や信頼を左右する法的拘束力のある文書になります。
特に近年、AIを活用したソフトウェアや生成系サービスにおいては、「SLAが現実と噛み合っていない」といったトラブルも増加しています。
本記事では、弁護士の視点から
・SLAが問題となる典型的な契約トラブル
・契約書に盛り込むべき条項とドラフト例
・AIサービスにおける特有のリスクとその整理法
などを分かりやすく解説します。
「万一の時、SLAが助けてくれる契約になっているか」を確認するためにも、ぜひお読みください。
Contents
1.SLAとは何か
SLA(Service Level Agreement、サービス レベル アグリーメント)という言葉は、法令上の裏付けのある用語ではなく、また一律の定義が確立しているとは言い難いようです。
もっとも、一般的には、サービス提供者と利用者の間で、ITサービスの契約を締結する際に、提供するサービスの範囲・内容及び前提となる諸事情を踏まえた上で、サービスの品質に対する要求水準を規定するとともに、規定した内容が適正に実現されるための運営ルールを両者の合意として明文化したものという意味で用いられています(なお、この定義は独立行政法人情報処理推進機構が用いている定義です)。
(1)SLAの基本的な内容
SLAには、次のような項目が定められることが多いようです。
| 項目 | 具体例 |
| サービスの内容 | 提供される具体的なサービスの説明(例:クラウドサービス、ヘルプデスクなど) |
| 可用性(稼働率) | 「月間稼働率99.9%保証」など、サービスが正常に稼働する割合 |
| 応答時間 | 障害や問い合わせへの対応を開始するまでの時間(例:2時間以内に初動対応) |
| 解決時間 | 問題の完全解決にかかる目標時間(例:重大障害は24時間以内に解決) |
| 報告義務 | 定期的なレポート提出、障害発生時の通知方法など |
| ペナルティや補償 | SLA未達成時のサービス料割引や返金などの補償内容 |
(2)SLAの目的
SLAを制定する目的は、次の3点が挙げられます。
①サービスの品質保証…サービス提供者と利用者の双方が期待するサービスの基準を明確にすることで、トラブルを未然に防ぎます。
②責任範囲の明確化…障害発生時の対応範囲や、どちらがどこまで対応すべきかを明確にします。
③信頼性の向上…サービス提供者にとっては、品質を数値で約束することで信頼性を高め、差別化要素にもなります。
(3)SLAの活用例
代表的なものとして次のようなものが挙げられます。
・クラウドサービス(SaaS、IaaSなど)…AWSやMicrosoft Azureなどは「99.99%の稼働率保証」といったSLAを設けています。
・アウトソーシング業務…コールセンター業務やITサポート業務でも、応答率や解決時間に関するSLAが設定されています。
・システム開発、保守契約…運用フェーズにおける障害対応時間や対応フローなどをSLAで合意しておくことで、継続的な品質維持が可能になります。
なお、近時ではAIを用いたサービスでもSLAが制定されることが増えているようです。
(4)SLAと契約書との関係
SLAは、業務委託契約やサービス契約などの主契約に付随する文書として作成されることが一般的です。そして、主契約の中で「SLAに基づいて対応する」旨を定め、別紙で詳細なSLAを添付する形式が採用されることが通常です。
2.SLAに起因して生じるトラブル
SLAは、ITサービスの安定的な運用や品質の確保を目的とした契約上の重要条項ですが、その性質上、技術的な用語や定量的な指標が多く、実務上の運用と法的な解釈にギャップが生じやすい点が特徴です。
SLAが実際の契約実務においてどのような場面で問題となりやすいのか、典型的なトラブル例をもとに法的視点から解説します。
(1)サービスレベルの「認識のズレ」による紛争
SLAの中でもっとも多いトラブルは、契約当事者間で「サービス水準」についての認識が一致していなかったというものです。たとえば、サービス提供者側は「稼働率99.9%」を「努力目標」として認識していたのに対し、利用者側は「契約上の義務」と理解していた、といったケースが典型例です。
このような場合、仮に実際の稼働率が99%を下回ったとしても、サービス提供者側が「法的な義務ではない」と主張し、利用者は「契約違反(債務不履行)に該当する」と反論し、法的責任の有無が争点となります。
(2)定義が曖昧なことによるトラブル
SLAにおける「障害」「応答時間」「回復時間」などの用語が曖昧であることも、紛争の火種となります。たとえば、「重大な障害」の定義が明確でないまま、復旧目標時間だけが記載されているような場合、何が「重大」なのかを巡って解釈が分かれることになります。
また、稼働率の算定方法が明示されていない場合にも、メンテナンス時間や計画停止が「ダウンタイムに含まれるか否か」といった点で争いが生じやすくなります。
(3)SLA違反時の補償範囲を巡る対立
SLAでは、一定のサービスレベルが未達成だった場合に補償(サービスクレジットや料金の割引など)を行う旨定められることが多くありますが、その補償がどこまでの損害をカバーするのかが明確でないと、重大なトラブルに発展します。
たとえば、SaaS型の業務システムが長時間停止した結果、ユーザー企業が商機を逸して数百万円規模の売上損失を被ったというケースで、サービス提供者側は「SLAで補償すると定めた内容が全てであり、これ以上の補償義務はない」と主張する一方、利用者側は「サービスを利用できなかったことに対する補償に過ぎず、逸失利益など他の損害に充当されるわけではない」と主張して争いになります。
このように、補償がカバーする損害の種類(通常損害、特別損害、直接損害、間接損害など)や補償上限をどう定めておくかは、契約設計上きわめて重要です。
(4)SLA対象外事項に関する誤解・誤認
「このケースはSLA対象外である」という主張を巡って争いになることも少なくありません。たとえば、「第三者のクラウドインフラの障害はSLAの範囲外」と記載されていたとしても、利用者側はそれに気づかず、「事実上使えないサービスを提供したのだから補償すべき」と訴えることがあります。
このようなトラブルを防ぐには、何がSLAの対象で、何が対象外かを明確にし、それが利用者にも認識されている状態を作ることが不可欠です。
(5)AIサービス等における成果保証・性能保証の問題
近年では、生成AIや機械学習モデルなどを活用したサービスが急増していますが、こうしたAIサービスでは、アウトプットの「正しさ」や「精度」が保証しきれないという特性があります。
たとえば、「画像認識の正答率90%以上を目標とする」という文言がSLAに記載されていた場合に、それが「義務」なのか「努力目標」なのかが曖昧だと、期待と現実のギャップが法的トラブルに発展します。
AI技術の性質上、出力結果に対して一義的な「正解」がない場面も多いことを踏まえると、SLAにおいて成果の保証ではなく、学習・検証・改善のプロセスをどこまで担保するのかを契約上明確にしておく必要があります。
(6)トラブル後の対応体制・連絡義務の欠如
障害発生時の連絡先や報告体制がSLA上定められていない、あるいは機能していないことで、事態の悪化を招く例も多くあります。たとえば、夜間や休日の障害について、SLA上対応時間が「平日9〜18時」と定められていたにもかかわらず、利用者側は「24時間体制を期待していた」と誤認していたような場合です。
こうした認識の齟齬を避けるためにも、対応時間・緊急連絡体制・エスカレーションルールなどをSLAに明記し、かつ契約当事者で共有しておくことが求められます。
上記は一例にすぎませんが、SLAの文言の曖昧さや認識のズレがあった場合、それが直ちに法的責任の有無につながります。
トラブルを未然に防ぐためには、サービス提供者と利用者の双方が、SLAに記載されている内容を文面通り読むだけではなく、その意味・運用・限界を正しく理解し、合意形成を行うことが何より重要といえます。
3.SLAに関係する主要な法律と法的論点
SLAは、技術的・運用的な要素を多分に含む一方で、契約書に付随する文書として作成される以上、原則として法的効力を有するものと考えられます。
このため、SLAの内容次第では、契約違反(債務不履行)、損害賠償、責任制限、さらには個人情報保護や競争法との関係でも、重大な法的リスクが発生し得ます。
ここでは、SLAを作成するうえで認識しておきたい主要な法律と、その代表的な論点を解説します。
(1)民法(契約法)
契約書に付随する形式でSLAが定められる場合、サービス提供者と利用者との合意内容を形成し、契約として取り扱われることになります。この結果、SLAに定められたサービス水準が守られなかった場合、原則としてサービス提供者は契約違反(債務不履行、民法第415条)として法的責任を問われることになります。
たとえば、SLAに「月間稼働率99.9%以上を維持する」と記載されていたにもかかわらず、サービス停止により90%しか達成されなかった場合、利用者は損害賠償を請求することが可能です。
ところで、SLAにつき努力目標として規定したにすぎない場合でも、サービス事業者は、サービスレベルの達成・維持に向けて継続的に取り組むべき義務は負っていると考えられています。このため、直ちに法的責任が追及されるわけではないものの、SLAで明記した内容を達成する努力を怠っていた場合は法的責任を負う可能性が出てきます。努力義務に留まるから法的責任は絶対に負わないと安易に判断するべきではありません。
ちなみに、実務上はSLAに定めるサービス水準に満たなかった場合を想定して、サービス提供者の責任範囲を限定する条項(たとえば、故意・重過失に限定する、損害の範囲を限定する、損害賠償額に上限を設定するなど)をSLAに組み込むことが一般的です。
もっとも、利用者が消費者である場合、消費者契約法により責任限定条項が無効とされる可能性があります。また、SLAを含む契約条項が利用規約に該当する場合、民法第548条の2第2項によって合意対象から除外されるといったリスクを内包します。
したがって、責任限定条項さえ定めておけば問題がないと考えるのは間違いです。
(2)消費者契約法
利用者が消費者である場合、消費者契約法の適用が問題となります。
この消費者契約法で特に留意したいのが、事業者の損害賠償の責任を免除する条項等が無効となることを定める消費者契約法第8条と、消費者の利益を一方的に害する条項が及び無効となることを定める消費者契約法第10条の存在です。
このため、SLAに「すべての損害は一切補償しない」などとする条項を設けても法的効力を有しないことに注意を要します。
なお、近時流通しつつあるAI系サービスでは、予測誤りや誤判定により消費者被害が発生したとして訴訟に発展するケースも想定されるところです。消費者を利用者として取り込むサービスの場合、免責条項や責任制限条項の設計に際しては特に慎重な対応が求められます。
(3)個人情報保護法
SLAの対象となるサービスにおいて、個人情報の取扱いが含まれる場合には、個人情報保護法及びそのガイドラインに従った設計が必要です。
特に、クラウドベースのAIサービスやSaaSなどでは、利用者が収集した個人情報をサービス提供者(委託先)が処理するという構造にならざるを得ません。この場合、利用者はサービス提供者(委託先)に対して監督義務を負う以上(個人情報保護法第23条)、サービス提供者(委託先)は利用者の義務履行を容易にするべく、率先して必要な対策を講じることが求められます(なお、いわゆるクラウド例外に該当する場合、委託先への監督義務は発生しません。もっとも、利用者は安全管理措置義務が発生しますので、この義務履行を容易にするべくサービス提供者側で支援できることはないか…という別問題が生じます)。
このサービス提供者(委託先)に求められる対策のうち、アクセス制限、ログ管理、暗号化、バックアップ等は、SLAや別紙の管理体制文書に記載されることが望ましく、法的義務と実務運用の整合性が重要となります。
なお、金融・医療・情報通信業界の場合、各業界向けの個別ガイドラインが存在しますので、このガイドラインも意識しながらSLAを作成する必要があります。
(4)独占禁止法
SLAが法人間契約に限定される場合、上記(2)で解説した消費者契約法は適用されません。もっとも、提供者が大手クラウドベンダーやプラットフォーマーであり、利用者が中小事業者である場合には、「独占禁止法」(特に優越的地位の濫用)との関係を意識する必要があります。
たとえば、「一切の補償なし」「利用者が損害を被っても提供者は責任を負わない」といった一方的かつ過度な免責条項は、契約自由の原則の範囲を超えて不公正な取引方法に該当するおそれがあり、公正取引委員会からの指導等の対象となる可能性も否定できません。
そのため、法人間取引であっても、一方的すぎる免責条項や補償拒絶条項はリスクが高く、合理的なバランスの取れたSLA設計が求められます。
4.SLAに盛り込むべき契約条項
SLAは、契約書における品質保証の中核として機能する文書です。そして、前述の通り、SLAは民法その他の法制度の下で契約責任や補償義務の根拠となるため、明確かつ実効性ある条項設計が欠かせません。
ここでは、SaaSやクラウド型ITサービスなどの「従来型のSLA条項」と、近時注目されているAIソフトウェアにおける「新たなSLA設計のアプローチ」の双方につき、整理を試みます。
(1)SaaS・クラウドサービスにおけるSLA条項の構成例
SaaSやクラウドサービスにおいては、SLAの運用実績が豊富であり、条項設計にもある程度の「定型性」が確立されています。
典型的な構成要素は次の通りです。
①サービスの定義、範囲に関する条項
・サービス内容の特定…提供されるサービスの内容(例:クラウドホスティング、保守サポート、アプリの監視など)、提供されないサービスの除外事項(例:サードパーティ製品の障害は対象外など)
・対象システム・範囲…サービス対象となるシステム、インフラ・ネットワーク等の範囲の明示
②サービスレベル指標(KPI)の定義
・稼働率(可用性)…稼働保証(例:本サービスは、1ヶ月のうち99.9%以上の時間、正常に稼働するなど)、計算方法や稼働時間の定義(例:定期メンテナンスは除外など)
・応答時間…問い合わせや障害連絡に対して、初動対応を開始するまでの時間(例:重大障害は2時間以内に対応を開始することなど)
・回復時間…障害などの完全な復旧までに要する時間、障害レベル(重大・中度・軽微)に応じた区分け
③サポート体制・対応時間
・対応時間帯…深夜、休日の取扱い
・問い合わせ方法…電話、メール、Webフォームなどの受付手段
・エスカレーションルール…初動対応後、一定時間で未解決の場合の対応ルートの開示
④障害時の報告・連絡体制
・障害発生時の連絡フロー・連絡先
・障害報告書(インシデントレポート)の提出義務
・復旧見通し、対応状況の定期報告
⑤SLA未達成時の補償条項
・サービスクレジット…返金や割引(例:月間稼働率が99.0%未満だった場合、翌月利用料の10%を減額するなど)
・損害賠償の範囲と上限…通常損害のみに限定(特別損害・間接損害・逸失利益は免責)、上限金額の明記(例:月額料金の2ヶ月分を上限とするなど)
⑥SLAの測定方法と監査・証明
・監視ツールによる自動測定(例:モニタリングシステムのログなど)
・利用者による測定結果の確認方法
・定期的な報告(例:月次レポート、四半期ごとのレビュー会議など)
⑦SLAの除外事由(免責条項)
・天災、戦争、暴動、法令改正等の不可抗力免責
・利用者の操作ミス、機器故障、ネットワーク障害による免責
・提供者が計画的に行うメンテナンス(事前通知あり)による免責
⑧改定・見直しのルール
・SLAの見直し時期(例:年1回の合意見直し)
・双方の協議による改定手続の定め
なお、作成に際しては、次のような事項にも注意をしてください。
| ポイント | 解説 |
| 定量的な表現にする | 例えば、「適切に対応する」ではなく「2時間以内に対応を開始する」など明確に表現するなど |
| 定義を厳密にする | 例えば、「重大障害」の具体例を明記し、認識のズレを回避するなど |
| ビジネスリスクを反映する | 業務停止による損害や社会的影響の大きいサービスには、手厚い補償と対応体制を設定するなど |
(2)AIソフトウェアにおけるSLA設計上の特有論点
上記(1)で示した構成要素と対比する形で解説すると、次の通りとなります。
①サービスの定義、範囲に関する条項
・提供対象は「モデルそのもの」ではなく、「AIを用いた推論サービス」または「出力支援機能」と定義する(例:「自然言語生成による回答支援」、「画像分類に基づく識別支援」など)
・出力内容や判断結果については「補助的な支援」に留まることを強調し、完全な代替にはなり得ないことを前提にする(例:最終判断の代行を行うものではないなど)
②サービスレベルの指標(KPI)の定義
・基本的には上記(1)と同様。ただし、AIの「出力品質のばらつき」「誤出力」は性能の問題であり、KPIではなく目標値的に扱うのが実務的(例:稼働率については、AI APIの正常応答率を対象に設定するなど)
③サポート体制・対応時間
・基本的には上記(1)と同様。ただし、誤出力・不適切出力などAI特有の「品質に関する問い合わせ」にも対応するか明確にする(例:「サービスの稼働や応答不具合」に限定し、出力内容の疑義までは含めないなど)
④障害時の報告・連絡体制
・基本的には上記(1)と同様。加えて、「著しい誤出力」や「生成エラー多発」などAI特有の障害定義や発生条件も設けるのが無難(例:「学習済モデルが特定入力で無限ループを起こす」等のAI固有事象に対応できるよう、異常出力の定義を明文化するなど)
⑤SLA未達成時の補償条項
・(現状のAIの状況を踏まえれば)精度未達や誤出力に対する金銭的補償は原則行わないとした方が無難。補償内容としてはサービスクレジットまたは再学習対応、モデル調整の努力義務で対応(例:「精度が当初の目標を著しく下回った場合、サービス提供者は再学習を実施する努力をする」など)
⑥SLAの測定方法と監査・証明
・出力精度の測定には、事前に定義された「テストデータセット」や「評価指標」を用いることを明記する(例:「四半期ごとに評価用データにて精度確認を行う」など)
⑦SLAの除外事由(免責条項)
上記(1)に追加して、入力データの偏り・不完全性・不適切利用による出力異常を明確に除外事由として記載することが重要(例:「利用者が提示した入力データが不正確または著しく偏っていた場合は、精度低下についてサービス提供者は責任を負わない」、「出力をそのまま意思決定に使用した結果生じた損害については、サービス提供者は一切責任を負わない」など)
⑧改定・見直しのルール
・モデル精度、機能の進化に伴い、見直し頻度を高める必要あり(例:「四半期ごとのレビューをもとに、SLA内容について協議の上改定する」、「アップデートの影響範囲が大きい場合は、事前に変更内容を通知し、利用者が異議を述べた場合は旧SLAを一定期間継続する」など)
⑨その他
上記8項目のいずれにも該当しないものとして、次のような事項をSLAに明記することも検討に値します。
| 項目 | 内容 |
| 精度指標と評価プロセス | 正答率・F値などを「目標値」として設定し、「合理的努力により維持する」といった表現にとどめる。 |
| 出力責任の限定 | AIの出力内容は助言にすぎず、最終判断は利用者の責任であることを明文化する。 |
| モデル更新・再学習 | 更新によって出力が変動するリスクを説明し、事前通知・影響報告のルールを設ける。 |
| 不適切出力・バイアスへの対応 | 利用者による通報受付、社内監査、修正手順などを整備し、SLAに反映する。 |
| 説明可能性 | 可能な範囲で出力根拠を提示する努力義務を定める。 |
5.SLA作成・レビューにおける実務上の留意点
SLAは、サービス提供者と利用者の間で交わされる「サービス品質の約束」であり、契約書上の明文として残る以上、その一つひとつの条項には法的責任が伴います。
しかし実際の現場では、SLAが「定型的なひな形に従って機械的に添付されるだけ」、「契約締結時には目を通されるが、運用では顧みられない」ことも少なくありません。
実効性を持たせるためには、契約実務(法務)・技術運用・組織体制の3つの側面から検討する必要があります。
(1)定型文頼みのSLAが抱えるリスク
SLAのひな形を使い回し、サービスの実態と乖離した項目を漫然と残してしまうことは、契約実務においてしばしば見受けられます。たとえば、特定のSaaSサービスには存在しないサポート窓口がSLAに記載されたままになっていたり、SLAに定めた稼働率が現実的に不可能な水準であったりすることがあります。
このような状況では、サービス提供者は無自覚のうちに過剰な義務を負ってしまい、一方の利用者は誤った期待を持ったまま契約を締結することになります。
契約書が紛争の際の証拠文書として用いられる以上、SLAもまた「現実のサービス仕様・体制と齟齬がないか」を丁寧に検証し、定期的にレビューすることが不可欠です。
(2)「技術部門まかせ」「法務部門まかせ」の分断リスク
SLAの策定は、しばしば「技術に詳しいエンジニア部門」、「契約を統括する法務部門」、「契約交渉を担う営業部門」のいずれかに偏ってしまいがちです。
その結果、次のような弊害が生じるおそれがあります。
・技術部門主導型:実装に基づく制約が反映されている一方で、文言が曖昧・抽象的になり、法的責任の観点からは不十分
・法務部門主導型:責任限定や免責に偏重し、サービスの実態や利用者の期待との間に乖離が生まれる
・営業主導型:契約獲得を優先して過大な品質保証を盛り込み、運用で破綻する
このような事態を避けるには、SLAを「部門横断的な合意文書」として捉える必要があります。最低限、法務(品質、責任、補償に関する法的リスク)、技術(提供するサービスの機能と制約)・営業(顧客の期待とビジネスへの影響)の三者が関与し、明文化するプロセスが推奨されます。
(3)定量化できるもの・できないものを分けて記載する
SLAの文言には、「定量的に測定可能な項目」と、「定性的・努力義務的にしか表現できない項目」とがあります。
この区別を明確にせず、「目標」と「義務」を混在させたまま文書化すると、後の紛争で不利な解釈を受ける危険があります。
【例:避けたい曖昧な表現】
本サービスは高い可用性を維持するよう努める。
→ 何をもって「高い」とするのか不明。目標か義務かも不明。
【例:明確な記述】
・月間稼働率99.9%以上を目標とする(義務ではなく努力目標とする)。
・実績値が98.0%未満となった場合には、甲乙協議の上改善措置を講ずる。
このように、数値化できるもの(稼働率・応答時間など)は具体値と測定方法を明示し、数値化できないもの(正確性・ユーザー満足度など)は努力義務として記述する工夫が必要です。
(4)AIサービスの場合は「結果」ではなく「プロセス」を記述する
AIソフトウェアにおけるSLAは、従来型のサービスのように「成果」や「可用性」を保証するだけでは不十分です。AIの出力は本質的に不確実であり、「精度90%以上を保証する」といった定量的義務を負わせることには、サービス提供事業者にとって極めて高いリスクが伴います。
そのため、AI系サービスのSLAでは、「出力精度」や「誤判定率」等を参考値としつつ、次のような「継続的管理プロセス」をSLAに明文化することが重要です。
・精度測定の方法と頻度
・モデル更新時の通知、検証フロー
・ユーザーからの誤出力報告と再学習対応
・バイアス検出や倫理的問題への対応義務
AIは「止まっているサービス」ではなく「進化し続けるサービス」であるという認識をSLAに反映させることが、利用者との適切な関係構築に資するものとなります。
(5)レビューの頻度と見直しプロセスを明記する
SLAは一度定めたら終わりではなく、サービスの変更・技術の進化・事業の成長に応じて定期的に見直されるべき文書です。特にAIサービスやAPIベースのSaaSでは、半年〜年単位でのアップデートが一般的です。
そのため、SLA本文または基本契約書に以下のような条項を設けることが推奨されます。
(例)
「甲および乙は、少なくとも年1回、本SLAに定めるサービスレベルおよび運用状況についてレビューを実施し、必要に応じて協議のうえ見直しを行う。」
また、見直しの際の合意手続(文書通知/電子同意/発効日)や、改定による旧版との関係についても明示しておくと、後日の混乱防止につながります。
6.SLAの作成・レビューを弁護士に相談・依頼するメリット
SLA(サービスレベルアグリーメント)は、技術と業務の接点にあると同時に、契約法や損害賠償責任といった法的ルールの影響を強く受ける領域です。
サービス内容の定義、稼働率・精度等の数値目標、障害時の対応義務、補償や責任の限定、AIによる出力の取扱いといった各項目は、いずれも契約上の義務や法的責任の有無を左右するものであり、些細な文言の違いが、とんでもない数字の損害賠償請求や訴訟リスクに発展することもあります。
その一方で、SLAの設計やレビューが、営業部門・技術部門・管理部門それぞれに任されたまま、「現場で作成したひな形が、そのまま契約書の一部になっている」というケースも少なくありません。
こうした状況を打破するには、三部門それぞれに割って入ることができる弁護士の関与が価値を発揮します。
■弁護士に依頼するメリット
| ・SLA条項を「契約として機能する文言」に整備し、曖昧さを排除できる
・法的責任や補償リスクを見越した構成(免責・限定条項、努力義務化など)が可能 ・AIやクラウドなど、新技術に対応した契約構造の見直しを支援 ・SLAと契約書本体や仕様書との整合性を確認し、全体としての契約リスクを最小化できる ・顧客やベンダーとの契約交渉時に、不利な条件を回避する交渉戦略を構築できる |
■弁護士への相談を強く推奨される場面
| ・提供しているSaaSやクラウドサービスのSLAひな形が現実に合っているか不安
・AIソフトの提供を始めたが、どこまで精度や出力結果に責任を負うべきか分からない ・取引先とのSLAで補償範囲や免責条項に関して意見が対立している ・SLAの内容が契約書と食い違っていて、どちらが優先されるのか分からない |
弁護士は、契約書を単にレビューするのではなく、事業モデルや提供体制、リスク耐性に応じて、最適なSLA構造を一から設計することも可能です。
貴社のサービスが継続的に信頼され、トラブルに強い事業基盤となるよう、法務の観点からしっかりと支援いたします。
SLAの策定・見直し・交渉でお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。
7.リーガルブレスD法律事務所のサポート
リーガルブレスD法律事務所は、通算200社以上の顧問弁護士として活動し、またスポットでの法律相談等も多数お受けしています。
そして、クライアントのニーズに応じたSLAの新規作成やリーガルチェックはもちろんのこと、契約締結交渉の支援、対案の提示、契約解釈の相違に基づく紛争解決など、契約関係にまつわる問題解決やサポート業務の提供を行ってきました。
クライアントの皆様には、現場実務対応で得られた知見とノウハウを活用し、できる限り有利な形での解決を図ることができるよう日々尽力しています。
【リーガルブレスD法律事務所が提供するサポート内容】
リーガルブレスD法律事務所では、ご依頼者様のニーズに合わせて、次のようなサービスをご提供しています。
■SLA条項のリーガルレビュープラン
| ご依頼内容(例) | ・利用者側よりSLAの提示があったが、過剰な義務を負っていないか心配
・稼働率、補償、責任制限の条項が妥当かを第三者に確認したい ・ベンダーから提示されたSLAを、法務部でどうチェックすべきか分からない |
| サポート内容 | ・SLAの条項構成と文言の妥当性を契約法、損害賠償リスクの観点から精査
・目標義務と法的義務の混在を指摘し、修正案を提示 ・必要に応じて契約全体(基本契約・仕様書)との整合性チェックを実施 |
| 主な利用者 | ・中小、中堅IT事業者(SaaS、クラウド、AIベンダーなど)
・自社のSLAひな形をチェックしたい情報システム部門、法務部門 ・システム発注者(利用企業)としてSLAの意味を正しく理解したい購買担当者など |
| 弁護士費用 | 10万円(税別)~
※分量、難易度、精査対象の範囲に応じて変動 |
| 実施方法 | ・Word/PDFでSLA条項または契約書一式をご提出いただき、合意した日までにレビュー結果を記載したデータを納品
・必要に応じてZoomでご説明 |
■SLA条項のドラフト作成・ひな形整備プラン
| ご依頼内容(例) | ・新規のSaaSサービスを立ち上げるので、自社サービスに合ったSLAを設計したい
・AIチャットボットを提供しているが、精度や出力責任の扱いが契約上あいまいで不安 |
| サポート内容 | ・サービス内容、技術仕様、運用体制のヒアリングに基づき、リスクに応じたSLA条項を一から設計
・AIやAPI連携など新しい技術に対応した条項を提案、ドラフト化 |
| 主な利用者 | ・スタートアップ、SaaS系ベンチャー企業
・新サービスのリリースを控えるIT、Web系企業 ・利用規約、契約ひな形を整備したい経営者、法務責任者など |
| 弁護士費用 | 10万円(税別)~
※分量、難易度等に応じて変動 |
| 実施方法 | ・初回ヒアリング(オンライン/対面)
・ドラフト案の提示(Word形式) ・ご要望に応じた修正対応 ・納品(Word形式) |
■スポット(単発)法律相談プラン
| ご依頼内容(例) | ・自社が提供するSaaS、AIサービスにSLAをつけるべきかどうか判断に迷っている
・顧客から提示されたSLAを読んでも、内容の意味やリスクが分からない ・SLAに書かれている「補償」や「免責」がどこまで法的に効力があるか確認したい ・契約書とSLAの整合性をどこまでチェックすればよいのか知りたい |
| サポート内容 | ・SLAの基本的な構造と法的意味についての解説
・契約書中のSLA条項に関するリスクポイントの助言と一般的な対応方針の提示 ・依頼者の業種、業態、サービス内容に応じたSLA設計の方向性に関するアドバイス |
| 主な利用者 | ・初めてSLAに向き合うスタートアップ、中小IT事業者
・社内に法務部門がない企業の経営者、担当者 ・システム導入を検討中の企業で、発注者としてSLAの読み方を理解したい方 ・AIサービス導入前に法的な確認を行いたい情報システム部門など |
| 弁護士費用 | 1回90分当たり15,000円(税別) |
| 実施方法 | ・事前に関係資料の送付、事前検証
・オンライン面談 or 来所での対面面談 |
<2025年7月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- その「免責条項」は本当に意味があるのか?契約リスクを左右する責任条項の考え方
- そのSLA、本当に機能していますか? 弁護士が教えるSLAの法的リスクと設計の勘所
- 契約書は誰が作成すべきか? 作成側・受領側が押さえたいポイントを弁護士が徹底解説!
- 偽装請負に該当するとどうなる? 契約形態・運用・制裁・是正策を弁護士が徹底解説
- IT取引の契約解消トラブル-無効・取消し・解除の実務対応
- 「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法
- 利用規約とは?作成・リーガルチェックのポイントについて弁護士が解説
- なぜテンプレートの利用規約はダメなのか?弁護士が教えるテンプレートの落とし穴
- 契約書のAIレビュー・チェックだけで万全!? 弁護士のリーガルチェックとの異同を解説
- アプリ事業者必見!スマホソフトウェア競争促進法で変わるスマホ市場の競争環境