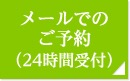その「免責条項」は本当に意味があるのか?契約リスクを左右する責任条項の考え方
現代のビジネス契約において、「免責条項」はごく当たり前のように使われています。
取引先が作った契約書にも、自社のサービス利用規約にも、こんな文言があるはずです。
「当社は一切の責任を負いません」
「損害賠償は●●円を上限とします」
「バグやトラブルが起きても補償はできません」
しかし、実は、法律の観点から見ると無効になる免責条項や、実質的に意味をなさない条項も少なくありません。
免責条項は、リスクヘッジ策として非常に強力なツールですが、書き方や使い方を誤ると、かえってトラブルの火種になることもあります。
本記事では、次のような実務上の観点から、免責条項の基礎と応用を分かりやすく解説していきます。
・免責条項とは何か、なぜ必要なのか
・どんな種類の免責条項があるのか
・どこまで免責できて、どこからが無効なのか
・消費者契約法や独禁法などの落とし穴は
・システム開発、SaaS、EC、プラットフォームなど、業種別の実務ポイントは
ぜひ本記事を通じて、自社の契約書、利用規約が守りを固められているかどうかを見直してみてください。
Contents
1.免責条項とは
(1)意義
免責条項とは、契約書や利用規約などにおいて、「一定の条件下では当事者の法的責任を免除する」ことを定めた条項です。つまり、通常であれば生じうる損害賠償などの責任について、あらかじめその責任を負わないことを定めた合意内容となります。
(2)目的
免責条項を定める理由・目的として、主に次の4点が挙げられます。
①予期しないトラブルへの備え(リスクヘッジ)
例えば、天災、システム障害、第三者による妨害など、自らのコントロールが及ばない事態に起因する損害にまで責任を負わないようにすることが挙げられます。
②責任の範囲を明確にして、紛争を防ぐ
例えば、「軽微なバグについては修補対応をすることで、その他の責任を免れる。」と契約書に定めておくことで、万一トラブルが発生した場合であっても、どこまで責任を負うのかが明確になり、紛争を予防できることが挙げられます。
③費用・価格の適正化
例えば、あらゆる責任を負担することを想定した場合、その責任を果たすための費用を価格に上乗せせざるを得ません。しかし、免責条項により過大な責任を排除した場合、合理的な価格設定が可能となることが挙げられます。
④サービス提供者側の保護
例えば、AIを組み込んだサービス提供の場合、技術的に100%の品質保証が難しいことを踏まえ、サービス提供者に対する過度な責任負担を解放することが挙げられます。
(3)免責条項の主な3類型
免責条項には様々なパターンが考えられますが、契約実務で押さえておきたいのは次の3類型と考えられます。
①第1類型:損害賠償責任を一切負わない(全部免責)
これはタイトル通りで、契約違反や不法行為が発生しても、損害賠償責任を全面的に免除する条項を指します。
例えば…
・「天災地変その他不可抗力により履行不能となった場合、責任を負わない」といった、自然災害や戦争などの不可抗力に起因して発生した損害は全面的に免責されることを定めた条項
・「ユーザの操作ミスによるデータ損失について当社は責任を負わない」といった、相手方の行為に起因して発生した損害は全面的に免責されることを定めた条項
・「通信回線の障害等、当社の支配領域外の事由に起因する損害は免責される」といった、外部要因に起因して発生した損害は全面的に免責されることを定めた条項
・「乙が当該不具合を通知しなかった場合、甲は責任を負わない」といった、相手方当事者が負担する一定の義務を履行しなかったことに起因して発生した損害は全面的に免責されることを定めた条項
などが代表的なものです。
なお、後述しますが、全部免責条項は定めておけば常に有効という訳ではありません。例えば、相手方当事者が消費者である場合、消費者契約法により無効となる場合があります。
このため、全部免責条項を定めても大丈夫なのかを見極めることが重要となります。
②第2類型:一部の損害賠償責任を免れる(一部免責)
これもタイトル通りで、一定の範囲に限って免責する(一部の損害賠償責任は負担する)条項を指します。
例えば…
・「甲の軽過失により生じた損害については責任を負わない」といった、故意、重過失の場合は通常通りの責任を負うものの、軽過失に起因して発生した損害は免責されるという場合分けを定めた条項
・「当社は逸失利益その他特別損害について責任を負わない」といった、通常損害は責任を負うものの、特別損害は免責されるといった場合分けを定めた条項
・「損害賠償額は契約金額を上限とする」といった、契約金額内で賠償責任を負うものの、契約金額を超過した部分は免責されるといった場合分けを定めた条項
・「契約終了後に発生した損害については責任を負わない」といった、契約期間内に発生した損害については責任を負うものの、契約終了後は免責されるといった場合分けを定めた条項
などが代表的なものです。
なお、これについても後述しますが、一部免責条項についても常に有効という訳ではありません。例えば、相手方当事者が消費者の場合、軽過失の場合に一切責任を負わない(軽過失全部免責)という条項は無効となる場合があります。
やはり、一部免責条項についても、どういった場面で定めることができるのかを見極めることが重要となります。
③第3類型:一定事項について保証しない(保証責任の否定)
上記①②は損害賠償責任を負うか負わないかという場面に限った免責条項でしたが、ここでいう保証責任とは、一方当事者の行為により相手方当事者が期待する結果が生じなかった場合であっても、何ら問題視されない(相手方当事者は異議を述べることができない)という意味です。いわば、損害賠償責任の前提となる義務違反を否定する条項とイメージすれば分かりやすいかもしれません。
この類型の条項ですが、例えば…
・「本サービスが特定の目的に適合することを保証しません」といった、相手方当事者の期待を裏切ったとしても責任を負わないことを定めた条項
・「提供される情報の正確性、完全性、最新性について保証しない」といった、相手方当事者の認識とミスマッチが生じたとしても責任を負わないことを定めた条項
・「本製品の利用が利用者の属する業界内自主ルール・倫理基準に適合するか否かは保証されません」といった、一方当事者の調査能力を超える場面で問題が発生したとしても責任を負わないことを定めた条項
・「コンサルティングの結果として売上が増加することを保証しない」といった、相手方当事者にとって望ましい成果が発生しなかったとしても責任を負わないことを定めた条項
などが代表的なものです。
なお、保証責任を否定する条項を多用しすぎると、ユーザより「何のためにサービスの提供を受けるのか分からない」と言われかねませんので、何をどこまで条項化するのかについては慎重な判断を要することになります。
(4)免責条項の制定に際して注意したい法律
相手方当事者が事業者か消費者かによって、注意すべき法律が大きく異なります。
①事業者間取引(BtoB)の場合
事業者間取引の場合、「契約自由の原則」が重視されることから、基本的には当事者間で合意した全部免責条項、一部免責条項、保証責任否定条項は有効と判断されます。
もっとも…
・あまりに一方的な内容、例えば、故意重過失があるにもかかわらず全責任が免除されると定めた場合、公序良俗違反(民法第90条)で無効と判断されることがあること
・当事者間の優劣により不利な条件を押し付けられた場合、例えば、大企業に売上げの大部分を依存している中小企業が、大企業に言われるがままに免責条項を受け入れた場合、独占禁止法や下請法違反として効力を有しないことがあること
・利用規約に定めた免責条項の内容が、「相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第1条第2項に規定する基本原則(※民法に定める「信義誠実の原則」のこと)に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる」場合、そもそも合意不成立と取り扱われることがあること(民法第548条の2第2項)
といった例外もあります。
ただ、例外が発動する場面は、相当限定されると考えられますので、免責条項がある場合はそのまま受け入れてよいのか、受け入れざるを得ない場合はリスクを低下できないか、あるいはリスクを第三者に転嫁できないか等の経営判断が求められることになります。
②消費者取引(BtoC)の場合
取引先が消費者である場合、上記①で記載した事項(公序良俗違反、定型約款規制)も検討対象となりますが、それよりも先ず意識しなければならないのは消費者契約法です。
特に免責条項の制定で意識しなければならないのは次の条項です。
【消費者契約法第8条第1項】
| 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
①事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 ②事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 ③消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項 ④消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項 |
簡単にまとめると
・債務不履行(契約違反)、不法行為に基づく損害賠償責任を全部免責する条項は無効
・債務不履行(契約違反)、不法行為に基づく損害賠償責任のうち、故意重過失がある場合に一部免責する条項は無効
・債務不履行(契約違反)、不法行為に基づく損害賠償責任のうち、軽過失に限って一部免責する条項は有効
となります。
【消費者契約法第8条第3項】
| 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)又は消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものを除く。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する消費者契約の条項であって、当該条項において事業者、その代表者又はその使用する者の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていないものは、無効とする。 |
これはサルベージ条項に対する規制と呼ばれる規定です。
例えば、「当社は、法令に違反しない限り、1万円を上限として賠償する」といった、具体的にどういった場合に一部免責条項が有効となるのか明記していない条項は無効になることが定められています。上記条項例の有効性を担保するためには、「法令に違反しない限り」を「故意重過失がない限り」と言い換える必要があります。
【消費者契約法第10条】
| 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 |
前述の消費者契約法第8条の解説に際し、軽過失による一部免責条項は有効であると記載しましたが、8条の問題をクリアーしても、次に10条違反にならないかという問題を別に検討する必要があります。
例えば、軽過失の場合に負担する損害賠償責任が著しく低額である(免責される損害賠償額が不当に高額すぎる)といった場合は、この消費者契約法第10条に違反し無効と判断される可能性があります。
2.システム開発・プログラム制作における免責条項のポイント
システム開発・プログラム制作取引における免責条項について、責任の所在に応じて3類型に分類し、それぞれの条項例と法的留意点を解説します。
(1)当事者双方に責任がない場合(不可抗力・第三者要因等)
(条項例)
| 甲又は乙は、天災地変、戦争、暴動、火災、法令の制定・改廃、公権力の行使、通信回線の不通、第三者による攻撃(サイバー攻撃等)その他、自己の責に帰することができない事由により本契約に基づく義務を履行できなかった場合、その責任を負わない。ただし、当該不可抗力事由が発生した場合、直ちに相手方に通知し、誠実に協議を行う。 |
いわゆる不可抗力免責と呼ばれる条項例です。
よく見かける条項例だと思われますが、実は「不可抗力」とは何か明確な定義はありません。このため、上記条項例では、例えば新型コロナのような感染症の流行の場合、不可抗力として取り扱ってよいのか判別がつかないという問題があります。したがって、不可抗力の具体的内容を列挙することがポイントとなります。
ただし、列挙したから不可抗力として免責されるわけではありません。
例えば、暴風雨は不可抗力の典型例として挙げられますが、翌日大型の台風が近づくことが分かっていたにもかかわらず、翌日ユーザ事業所内でコンサルティングを実施するという契約を前日に締結したところ、案の定大型台風の影響で交通機関がストップし実施できなかったという事例についてまで、形式的に不可抗力で免責されると結論付けるのは疑義があります。
したがって、実際に不可抗力として免責されるか否かは、ケースバイケースの判断に委ねられることになります。
また、システム開発・プログラム制作特有のものとして、第三者が提供するサービスを前提にするという点が挙げられます。
例えば、第三者が提供する通信サービスに異常が発生した場合は作業を進めることができない、第三者が提供するクラウドサーバがウイルスに汚染された場合はシステムを停止せざるを得ないといった事例です。
開発者・制作者側であれば、第三者が提供するサービスに障害が生じた場合も不可抗力として明示することが重要となります。
(2)相手方当事者に責任がある場合(遅延、誤情報提供、協力義務違反等)
(条項例)
| 乙が本業務の遂行に必要な情報の提供、打合せへの参加、承認等を遅滞した場合、当該遅滞に起因して甲が履行できなかった義務については、甲は一切の責任を負わない。 |
システム開発やプログラム制作取引の場合、委託者(発注者)は受託者に対する協力義務があるとされています。
この協力義務に違反した場合、免責扱いとなることを定めたのが上記条項例となります。
なお、実際のところ、協力義務が問題となる場面では、必ず受託者のプロジェクトマネジメント義務も問題となりますので、上記のような条項例が発動する場面は狭いものと考えられます。
この観点からすると、協力義務違反による免責は定めつつ、協力義務違反があった場合の挽回策(例えばスケジュール変更を可能にするなど)も合わせて定めておき、原則挽回策を発動させながら関係性を保持していく方が、上手な対処法なのかもしれません。
(3)当方に責任がある場合(契約不適合、納期遅延等)
(条項例)
| 甲の責に帰すべき事由により本契約上の義務の履行に支障が生じた場合、乙に現実に発生した直接かつ通常の損害について、甲は乙が本契約に基づき支払った対価の総額を上限として賠償責任を負い、逸失利益、間接損害、特別損害等については一切責任を負わない。 |
当方に帰責性がある場合、損害賠償責任を避けて通ることはできません。
ただ、その範囲を狭めることは可能です。
この観点から、上記条項例は損害賠償責任のうち、損害の項目と損害額を一定範囲に限定する一部免責条項を定めています。
システム開発やプログラム制作の場合、一度不具合が発生すると、あっちもこっちも支障を来し、損害が莫大になりやすいという特徴を有します。このため、開発者・制作者側からすれば、一部免責条項は必須と言っても過言ではありません。
なお、システム開発やプログラム制作後、成果物に対する運用保守業務も受託している場合、不具合については運用保守業務として対応するというパターンも存在します。この場合、運用保守業務で修補を行うことを前提に、あえて全部免責条項を設定するといった調整も考えられるところです。
ところで、近時は生成AIを組み込んだシステム開発等が盛んになっています。ただ、今のところ、生成AIが出す回答内容は正確性を欠くため、開発者・制作者側としては結果保証を求められると困るというのが実情です。
この観点からすると、生成AIが出す回答内容その他成果については保証しないといった免責条項を定めることも、今後は重要になるものと考えられます。
3.ソフトウェアライセンス取引における免責条項のポイント
ソフトウェアライセンス取引(SaaSを含む)における免責条項について、責任の所在に応じて3類型に分類し、それぞれの条項例と法的留意点を解説します。
(1)当事者双方に責任がない場合(不可抗力、第三者責任等)
(条項例)
| 甲または乙は、天災地変、火災、停電、戦争、暴動、公権力の行使、通信回線の不通、クラウド基盤の障害その他、自己の責に帰すことができない事由により本契約に基づく義務を履行できなかった場合、その責任を負わない。ただし、当該事由が発生したときは速やかに相手方に通知し、対応策について誠実に協議する。 |
いわゆる不可抗力免責を定めた条項です。
具体的な不可抗力事由を列挙すること、もっとも不可抗力に該当するか否かはケースバイケースの判断にならざるを得ないことについては、上記2.(1)で解説した通りです。
また、ソフトウェアライセンス取引は、電気・通信回線の中断、AWS等のインフラサービスの障害など、第三者が提供するサービスに依存している点も上記2.(1)で解説したシステム開発・プログラム制作取引と同様です。
したがって、ライセンサー側としては、不可抗力事由として、第三者に起因する事由を具体的に明示することが重要となります。
(2)相手方当事者に責任がある場合(ユーザの誤操作、規約違反等)
(条項例)
| 利用者が本サービスの利用に際し、登録情報の誤記、不正使用、第三者へのアカウント開示、その他利用規約違反を行ったことに起因して生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。 |
相手方当事者に帰責性がある場合、当方が責任を負わないという当たり前のことを定めた条項例となります。
ただ、例えば、ライセンサー側が、ソフトウェアが不正使用されていることを認識していたにもかかわらず、適時に適切な対策を講じなかったといった落ち度がある場合、条項例が形式的に適用されて、ライセンサー側が免責されることにはならないと考えられます。
したがって、現場実務ではケースバイケースの判断が求められます。
なお、上記条項例の適用範囲を拡大したい場合、ユーザに帰責性ありと指摘できる環境を整えることがポイントです。そこで、例えば禁止条項を充実化させる、使用に際しての注意喚起を徹底するといった対策を講じることも有用です。
(3)当方に責任がある場合(システム障害、バグ、機能不備等)
(条項例)
| 本サービスに関して当社の責に帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合、当社は、利用者が過去3ヶ月間に本サービスに対して支払った利用料金の合計額を上限として、現実に生じた直接かつ通常の損害についてのみ責任を負い、逸失利益、間接損害、特別損害等については一切責任を負いません。 |
当方に帰責性がある場合、損害賠償責任を回避することは不可能ではあるものの、損害項目と損害額を絞ることで、その責任範囲に制限をかけることが可能です。
ただし、ユーザに消費者が含まれる場合、上記条項例は故意重過失の場合にも一部免責されることを定めている点で無効と判断される可能性が高いと言わざるを得ません。
また、軽過失の場合に限定して適用される条項であったとしても、免責額が過大すぎることを理由に消費者契約法第10条違反となる可能性も否定できないことも注意を要します。
ちなみに、システム障害やバグ、機能不備については、修繕義務を負うことを全面的に押し出すことで、損害賠償責任を免れるといった対策を講じることも検討に値します(なお、消費者契約法第8条第2項参照)。
なお、何らかの理由でサービス提供を休止・停止する場合も免責条項を定めることが一般的ですが、この場合、事前告知関係を設ける、代替サービスを案内する、返金対応を行うといったトラブル回避のための施策を講じることが通常です。
このため、上記条項例とは別にサービス休止・停止に関する条項例を設定したほうが無難です。
4.ネット通販・ECにおける免責条項のポイント
ネット通販・EC取引における免責条項について、責任の所在に応じて3類型に分類し、それぞれの条項例と法的留意点を解説します。
(1)当事者双方に責任がない場合(不可抗力、第三者の責任を含む)
(条項例)
| 当社は、天災地変、火災、停電、戦争、テロ、疫病、法令の制定・改廃、交通機関の遅延・停止、運送会社の事故・不備、その他当社の責に帰すことができない事由により商品の配送・提供が遅延又は不能となった場合、その責任を負いません。 |
いわゆる不可抗力免責を定めた条項です。
具体的な不可抗力事由を列挙すること、もっとも不可抗力に該当するか否かはケースバイケースの判断にならざるを得ないことについては、上記2.(1)で解説した通りです。
また、ネット通販・ECは、取引自体は電子化されているとはいえ、商品の引渡しは運送会社に依存していること、デジタルサービスは通信会社やプラットフォーム等に依存して
いる点も上記2.(1)で解説したシステム開発・プログラム制作取引と同様です。
したがって、通販事業者側としては、不可抗力事由として、第三者に起因する事由を具体的に明示することが重要となります。
ただ、商品引渡しについては、ヤマトが駄目なら佐川に委託すればよい…といった履行手段が複数認められることから、列挙しても不可抗力として認められるかはやや微妙なところがあります。
(2)相手方当事者に責任がある場合(購入者の誤入力、不在、規約違反等)
(条項例)
| 購入者の入力ミス、不在による再配達未受領、商品の誤使用等に起因して損害が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。 |
相手方当事者に帰責性がある場合、当方が責任を負わないという当たり前のことを定めた条項例となります。
なお、現場実務視点では、免責条項の適用に支障を来す事由が生じないか、例えば
・誤入力の場合は電子消費者契約法に基づく錯誤取消しを主張されないような画面構成になっているか
・未受領が続く場合は自動キャンセル扱いとすることを謳っているか
・誤使用による返品対策として、特定商取引法に基づく返品特約につき明記しているか
・契約を取消されないよう、特定商取引法が求める最終確認画面に記載するべき事項が抜け漏れなく表示されているか
といったことも検討しておくことが重要です。
(3)当方に責任がある場合(欠陥商品、誤配送、記載ミス等)
(条項例)
| 当社の責に帰すべき事由により損害が発生した場合、当社は購入者が当該商品について支払った金額を上限として、現実に生じた直接かつ通常の損害に限り賠償責任を負うものとします。逸失利益その他の間接損害については責任を負いません。 |
当方に帰責性がある場合、損害賠償責任を回避することは不可能ではあるものの、損害項目と損害額を絞ることで、その責任範囲に制限をかけることが可能です。
ただし、ユーザに消費者が含まれる場合、上記条項例は故意重過失の場合にも一部免責されることを定めている点で無効と判断される可能性が高いと言わざるを得ません。
また、軽過失の場合に限定して適用される条項であったとしても、免責額が過大すぎることを理由に消費者契約法第10条違反となる可能性も否定できないことも注意を要します。
ちなみに、欠陥商品対応については、商品交換を全面的に押し出すことで、損害賠償責任を免れるといった対策を講じることも検討に値します(なお、消費者契約法第8条第2項参照)。
5.プラットフォームサービスにおける免責条項のポイント
プラットフォームサービス(シェアリングエコノミーやマッチング型サービス)における免責条項について、責任の所在に応じて3類型に分類し、それぞれの条項例と法的留意点を解説します。
(1)当事者双方に責任がない場合(不可抗力・第三者の責任を含む)
(条項例)
| 当社は、天災地変、火災、停電、戦争、暴動、公権力の行使、通信回線障害、プラットフォーム外部のシステム障害、第三者による不正アクセス、その他当社の責に帰すことができない事由により本サービスの全部または一部を提供できない場合、責任を負いません。 |
いわゆる不可抗力免責を定めた条項です。
具体的な不可抗力事由を列挙すること、もっとも不可抗力に該当するか否かはケースバイケースの判断にならざるを得ないことについては、上記2.(1)で解説した通りです。
また、プラットフォームサービスは、電気・通信回線の中断、レンタルサーバ等のインフラサービスの障害など、第三者が提供するサービスに依存している点も上記2.(1)で解説したシステム開発・プログラム制作取引と同様です。
したがって、サービス提供者側としては、不可抗力事由として、第三者に起因する事由を具体的に明示することが重要となります。
(2)相手方当事者に責任がある場合(ユーザ側の違反・過失による免責)
(条項例)
| ユーザが利用規約違反、虚偽情報の登録、法令違反行為、第三者との間の紛争、または当社の指示に従わないことに起因して生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。ユーザは自己の責任と費用でこれを解決します。 |
相手方当事者に帰責性がある場合、当方が責任を負わないという当たり前のことを定めた条項例となります。
また、ユーザ同士のトラブルについても、プラットフォームサービス提供事業者はあくまでも「場」の提供を行うに過ぎない媒介者である以上、責任を負わない旨定めることが重要となります。
ただ、近時プラットフォームサービス提供事業者は媒介者とはいえ、ユーザに対する一定の配慮義務があるのではないかという議論が盛んになっています。また、取引デジタルプラットフォーム消費者保護法に基づく情報開示義務など法整備が進められている状況です。
したがって、法改正時はもちろんのこと、社会情勢の変化を見極めながら随時免責条項を見直すことが肝要です。
(3)当方に責任がある場合(システム障害、データ漏えい、表示ミス等)
(条項例)
| 当社の責に帰すべき事由により利用者に損害が生じた場合、当社は、当該利用者が過去3か月間に当社に支払った利用料金の合計額を上限として、現実に発生した直接かつ通常の損害に限り責任を負います。逸失利益、間接損害、特別損害については責任を負いません。 |
当方に帰責性がある場合、損害賠償責任を回避することは不可能ではあるものの、損害項目と損害額を絞ることで、その責任範囲に制限をかけることが可能です。
ただし、ユーザに消費者が含まれる場合、上記条項例は故意重過失の場合にも一部免責されることを定めている点で無効と判断される可能性が高いと言わざるを得ません。
また、軽過失の場合に限定して適用される条項であったとしても、免責額が過大すぎることを理由に消費者契約法第10条違反となる可能性も否定できないことも注意を要します。
なお、プラットフォームサービス提供事業者は媒介者だから帰責性は無いというスタンスを貫くことは検討を要すること、前述(2)で解説した通りです。
6.免責条項の考案・設定を弁護士に相談・依頼するメリット
免責条項は、契約上の責任リスクを限定、排除するために非常に重要な条項です。
しかし、その設計や交渉には、次のような難しさが伴います。
・一見有効に見える条項でも、消費者契約法や民法の規制により無効となる可能性がある
・業種やサービス内容によって、どこまで免責できるかの「相場」が異なる
・相手方との交渉で不利な立場に立たされると、過剰な責任を抱え込んでしまう
このような場面では、契約法務の専門知識と実務経験を有する弁護士にご相談いただくことで、次のようなメリットが得られます。
■弁護士に相談・依頼するメリットとは
| ①自社サービスに最適な免責条項を設計できる(定型文の流用ではなく、オーダーメイド)
②消費者契約法、独禁法、下請法等のリスクを回避した合法性のある条項にできる ③相手方との交渉で不利にならないよう、法的根拠に基づいた交渉材料を準備できる ④契約全体の構成(検収、契約不適合責任、保証など)との整合性を踏まえた調整が可能になる |
免責条項は「書いておけば安心」ではなく、「適切に書かれていてこそ意味がある」条項です。
万一の紛争やクレーム対応を想定して、法的に有効かつ実務的なリスク回避が図れる契約書を整備するためにも、どうぞお気軽にご相談ください。
7.リーガルブレスD法律事務所のサポート
リーガルブレスD法律事務所は、システム開発事業者、プログラム制作事業者、ソフトウェア事業者、EC運営者、プラットフォームサービス提供事業者などの顧問弁護士として活動すると共に、スポットでの法律相談等も多数お受けしています。
そして、サービスローンチ前の適法性検証、取引交渉支援、契約書の作成・リーガルチェック、トラブル対応などで多くの知見とノウハウを身に着けています。
クライアントの皆様には、現場実務対応で得られた知見とノウハウを活用し、できる限り有利な形での解決を図ることができるよう日々尽力しています。
【リーガルブレスD法律事務所が提供するサポート内容】
当事務所では、免責条項の作成や修正を含む契約書や利用規約に関する支援を多数取り扱っています。
免責条項の検証、交渉サポート、スポットでの法律相談まで、貴社の業務実態に応じた対応が可能です。
ご関心のあるサービスがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
■契約書・利用規約チェックプラン
| ご依頼内容(例) | ・取引先から提示された契約書の免責条項に不安がある
・自社で作った利用規約の責任条項に法的問題がないか確認したい |
| サポート内容 | ・契約書/利用規約中の免責条項のリーガルチェック
・条項修正案と簡易コメントの提供(Word形式) |
| 主な利用者 | ・自社で契約雛形を運用している中小企業
・SaaSやECサービスを運営する事業者など |
| 弁護士費用 | 5万円(税別)~
※ボリューム、全体への影響度、複雑性などにより変動 |
| 実施方法 | ・メール等で契約書データ送付
・協議し定めた納期までに検討結果を報告 ・必要に応じてオンライン面談(30分程度) |
■契約交渉・免責条項修正支援プラン
| ご依頼内容(例) | ・取引先からの契約に過剰な免責条項が含まれており、どう修正交渉すべきか困っている
・自社に不利な条件を受け入れる前に、専門家の意見を得たい |
| サポート内容 | ・契約書をレビューし問題点の指摘
・免責条項の修正文案作成 ・交渉戦略メモ/説明文書の提供 (※代理人として交渉対応は含まれません) |
| 主な利用者 | ・中小IT企業、受託開発会社、スタートアップ
・大手からの契約書提示を受けた弱い立場の取引先など |
| 弁護士費用 | 1ヶ月当たり5万円(税別)~
※ボリューム、複雑性などにより1ヶ月当たりの単価は変動 ※複数月の交渉期間が必要である場合を想定 |
| 実施方法 | ・契約書の送付と課題確認のためのミーティング
・契約書チェック&修正提案 ・交渉方針確認のためのミーティング |
■スポット(単発)法律相談プラン
| ご依頼内容(例) | ・自社の契約書の免責条項が有効かどうか、一度専門家の意見を聞きたい
・消費者契約法や下請法に違反していないか心配 ・免責条項をめぐってトラブルになりそうだが、どう整理すればいいか相談したい |
| サポート内容 | ・免責条項に関する法的有効性、リスクの見立て
・契約書案や規約の該当部分の簡易レビュー(抜粋ベース) ・条項設計・交渉の方向性アドバイス ・他の契約条項との関係整理の簡易的助言 |
| 主な利用者 | ・まずは専門家に相談してみたい事業者、個人事業主、スタートアップ
・顧問契約、文書作成までは不要だが、方向性を固めたい方など |
| 弁護士費用 | 1回90分当たり15,000円(税別) |
| 実施方法 | ・事前に関係資料の送付、事前検証
・オンライン面談 or 来所での対面 |
<2025年7月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。
- その「免責条項」は本当に意味があるのか?契約リスクを左右する責任条項の考え方
- そのSLA、本当に機能していますか? 弁護士が教えるSLAの法的リスクと設計の勘所
- 契約書は誰が作成すべきか? 作成側・受領側が押さえたいポイントを弁護士が徹底解説!
- 偽装請負に該当するとどうなる? 契約形態・運用・制裁・是正策を弁護士が徹底解説
- IT取引の契約解消トラブル-無効・取消し・解除の実務対応
- 「中途解約で泣き寝入りしない!」WEB制作の未払い報酬を回収する方法
- 利用規約とは?作成・リーガルチェックのポイントについて弁護士が解説
- なぜテンプレートの利用規約はダメなのか?弁護士が教えるテンプレートの落とし穴
- 契約書のAIレビュー・チェックだけで万全!? 弁護士のリーガルチェックとの異同を解説
- アプリ事業者必見!スマホソフトウェア競争促進法で変わるスマホ市場の競争環境