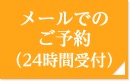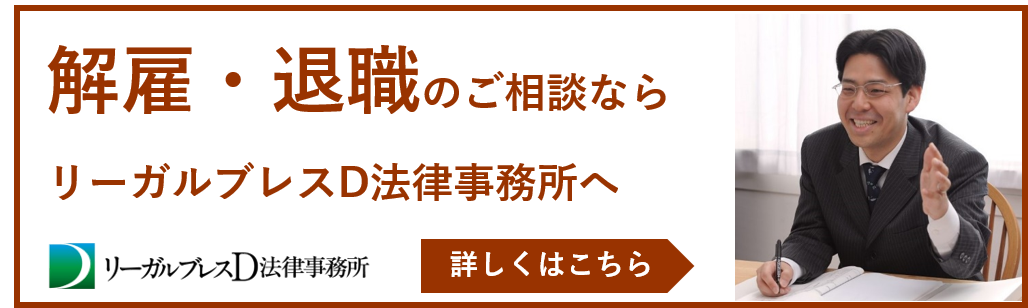試用期間中の能力不足を理由に解雇は可能?会社側における注意点とは
【ご相談内容】
現在試用期間中の従業員がいるのですが、会社が求めるパフォーマンスに達しておらず、このまま会社に残ってもらうわけにはいかないと考えています。
思い切って試用期間中に本採用拒否を通告してもよいのですが、念のため試用期間満了を待って本採用拒否を通告しようと考えています。
上記のような対応に問題はあるでしょうか。
【回答】
まず誤解の無いようご説明しますと、試用期間だからといって自由に本採用拒否(解雇)ができるわけではありません。裁判例等を踏まえた弁護士の実務感覚からすると、通常の解雇=能力不足による解雇が正当と認められる場合に準じた客観的合理性と社会的相当性が必要となります。
したがって、パフォーマンスに達していないというのであれば、会社が求めるパフォーマンスとは何か客観化すると共に、それを従業員に認識させ、かつ労働契約の内容としておかないことには、本採用拒否は違法と判断される可能性が極めて高くなることに注意が必要です。
【解説】
1.試用期間とは
(1)試用期間に対する誤解
多くの会社では「試用期間」を就業規則等に定めているかと思います。そして、その意義として、一定期間(1~6ヶ月の範囲で定めることが多いように思われます)を評価期間して実際に就労させ、その能力や勤務態度等から従業員としての適格性を判断し、適格性なしと判断した場合は本採用を拒否するための制度と位置付けていることが通常です。
しかし、実のところ労働法においては試用期間という用語は定められていません。すなわち、「試用期間」は俗語に過ぎず、試用期間だから××できるといった法的効果が当然に生じるわけではありません。
特に誤解が多いのが、「試用期間中は自由に辞めさせることができる」、「試用期間満了後に本採用拒否をしても、法的には全く問題ない」という点です。
(2)試用期間の法的考え方
試用期間を法的にどのように考えるのかについては、学説はともかく、現場実務では「解約権留保付労働契約」という考え方で運用されています。
要は、試用期間という独立の労働契約が成立していると考えるわけではなく、採用後から既に正規の労働契約が成立していることを前提に、労働契約の内容として、試用期間中において適格性なしと判断された場合は解約権行使が可能、すなわち解雇が可能という考え方になります。
さて、色々な文献やインターネット上の情報探索を行うと、試用期間における解約権行使は、通常の解雇より広く認められる…という記述を見つけることが多いかと思います。
たしかに、理屈の上ではその通りです。
ただ、会社側で現場実務をみている執筆者の感覚としては、試用期間中の解約権行使が、通常の解雇より広く認められるということは全くないというのが正直なところです。はっきり言ってしまうと、通常の普通解雇(能力不足、勤怠不良など)と同じレベルのものが求められるというのが実情ではないでしょうか。
したがって、試用期間中だから自由に辞めさせて良い、理由もなく本採用拒否しても全く問題ないという認識で対応してしまうと、会社は後で痛い目にあってしまうリスクがあること、注意が必要です。
(3)試用期間回避のための方策?
さて、試用期間について、①独立の契約ではないこと、②簡単に辞めさせることができないことを説明した場合、「だったら試用期間って意味がないのでは!?」と言われてしまうことがあるのですが、実際のところ特別な法的意味はないといっても過言ではありません。
もっとも、試用期間についてはまだまだ誤解も多いことから(?)、会社が従業員に対し、「試用期間中にあれこれ観察してみたが、適格性がないと言わざるを得ないので辞めてほしい」と話をした場合、従業員も仕方がない…として受け入れてくれる、すなわち自主的に退職してくれるといった事実上の効果は期待できるかもしれません。
ところで、試用期間を設定する目的を実現するために、あえて試用期間に相当する期間について、独立の有期雇用契約を締結すればよいのではと考える方もいるかもしれません。なぜなら、有期雇用契約であれば、適格性がないと判断した従業員に対し、解雇ではなく期間満了を理由に退職させることができ、リスク軽減ができると考えられるからです。
ただ、こういった手法(抜け道)は既に法の網にかかっており、当該有期雇用契約が締結された目的・趣旨が従業員の資質・能力の適格性を判断するためという場合、実質的には試用期間であるとして、期間満了による雇止めは不適法という裁判例が多数存在する状態です。
したがって、従業員の適格性を評価・判断したいというのであれば、次に述べるように、労働契約締結時において会社が求めている能力・資質は何かを具体的に特定し、その点につき従業員と認識共有を図ったうえで労働契約の無いようとする、そしてその内容を証拠化する(例えば必要な能力・資質を労働契約書に明記するなど)といった方策を講じるべきです。
2.能力不足で解雇ができる場合とは
上記1.で解説した通り、試用期間中及び試用期間満了後に本採用を拒否する場合、実際には普通解雇に準じて解雇可能かという点を検討する必要があります。
以下、従業員の属性に応じてポイントを整理します。
(1)新卒者の場合
・総合職
大企業などで見られる、大学在学中に内定を出し、大学卒業後の4月に一斉入社させるといったパターンが代表的なものとなります。
上記のような新卒入社の場合、ゼネラリストでの採用、すなわち特定の業務を担わせることを前提に採用していないため、たまたま配転された業務について適性が無かったとしても、他の業務については適性がある場合、能力不足と断定することができません。
したがって、試用期間中はもちろんのこと、試用期間満了時点であっても能力不足で解雇することは相当難しいと考えられます。
極論かもしれませんが、会社が行う全て業務を担当させたがいずれも業務遂行に難あり、会社として指導教育を繰り返し行い、数年が経過しても一向に改善の余地がない…といった事情が無いことには、能力不足による解雇はできないと考えたほうがよいかもしれません。どうしても辞めさせたい場合は、会社が求めている能力に達していないことを適切に説明した上で、退職勧奨を行い、何らかの条件を付して合意退職させることが賢明と考えられます。
・職種指定
新卒者であっても、例えば建築・土木やIT・プログラム等の専門学校卒業生を入社させるという場合、入社後に配置される職種・業務内容が事実上指定されており、労使双方の共通認識となっていることが通常です。
したがって、前述の総合職と比較すると、能力不足による解雇は理論上考えられるところです。
もっとも、新卒者は社会経験も職務経験も未熟であることは否めず、意外と裁判所はこの点を重要視しているように思われます。すなわち、ある程度の期間をかけて指導教育したことが重要視されますので、試用期間中はもちろん、試用期間満了時点でも解雇することはやや難しいと考えられます(もちろん、専門学校を卒業した技術者であれば、最低限身につけておくべき技能が無いといった極端な事例であれば別途検討の余地はあります)。
なお、職種指定の場合、能力不足か否かの判断基準を客観化するために、労働契約書に具体的な職種と求められる技術・スキルを明記する等の対策が重要です。
あと、いくら技術者とはいえ、職種及び業務を限定して新卒者を採用することはないかと思いますので、能力不足が露呈した場合、いきなり解雇するのではなく当該職種・業務以外の別の業務(従業員にとっては非専門分野)への配置転換を提示したほうが無難と考えられます。そして、配置転換を拒否した場合に初めて能力不足による解雇を検討するといった手順を踏むことが、解雇無効リスクを低下させるポイントになると考えられます。
(2)中途採用者の場合
大企業・中小企業を問わず、中途採用する場合はいずれも即戦力として採用することが通常です。もっとも、中途採用するに際して、会社がどのような能力・スキルを期待し従業員に表明していたのか、一方従業員はどのような実績をアピールし、自らの対応能力を表明していたかによって、能力不足による解雇の可否について考え方が分かれるように思われます。
以下では、それぞれの属性に応じて検討を行います。
・役職(職務上の地位)の限定
例えば、人事部長や営業部長といった、役職(職務上の地位)を限定して採用する場合、会社はその役職に見合った能力・スキル・経験等を期待する一方で、中途採用者もそのような期待があることを理解し対応能力があることを宣言して入社します。
したがって、役職を担うだけの能力と適格性があることを包含した労働契約が締結されたと考えることになります。もっとも、現場実務では、結局のところは労働契約の内容として、その役職に見合った能力・スキルとはどの程度の者を指すのかで争いとなることから、職務内容につき具体的かつ詳細に明記した労働契約書(例えば営業部長であれば、達成するべき売上額につき具体的な数字を明記するなど)を締結することをお勧めします。
さて、役職を限定した労働契約を締結したものの、能力・適格性がないと判断された場合、試用期間中であっても解雇することは可能ですし、試用期間満了時点で解雇することも可能となります(但し、試用期間中・試用期間満了時といった短期間で十分に見極めることができるのかという別の問題は生じます)。
そして、役職が特定されている以上、理論的には配置転換を提案することなく解雇することが可能ですし、指導教育を行うことも解雇するための必須条件とは考えられません。とはいえ、適格性が無いことを指摘した上で、配置転換を示唆した場合、従業員自ら退職することも現場ではよく見かける光景である以上、解雇リスクを回避するために配置転換を提案することも検討に値します。
ちなみに、役職を限定された労働契約である場合、それ相応の待遇が必要になると考えられます。中小企業の場合、一律の金額ではなく、他の従業員と比較して相当高額の賃金を支払っているといった相対判断になると考えられますが、他の従業員と大して変わりないという待遇の場合、役職を限定した労働契約として取り扱ってよいのかという疑義が生じることもあることに注意を要します。
・スペシャリスト
例えば、特殊な言語を取扱うことが可能なシステムエンジニア、国家資格を保有する弁護士などの専門職などを採用する場合、従業員が保有する高度専門知識を会社業務に活用することを期待して会社は採用することになります。一方で、従業員も自らの専門知識・能力をアピールし、会社の期待も理解した上で入社します。
したがって、前述の役職(職務上の地位)が限定された場合と同じく、高度専門知識・能力・スキルがあり、それを業務遂行において活用することを包含した労働契約が締結されたと考えることになります。なお、高度専門知識についてはどういった知識を指すのか、当該知識を備え活用する場面はどういったものなのか、業務遂行によりどのような成果を達成する必要があるのか等につき、具体的に記載した労働契約書を締結しておいたほうが良いことも前述の役職(職務上の地位)が限定された場合と同様です。
さて、スペシャリストとして採用し、会社が専門知識・スキルを発揮できるよう環境を整えたものの、期待された成果を上げることができない場合、試用期間中又は試用期間満了時に能力不足として即時に解雇してよいかについては、やや検討の余地があります。なぜなら、前述の役職(職務上の地位)の限定された従業員である場合、一種の職務限定契約と考えることができますが、スペシャリストの場合、職務限定契約を締結したとまでは言い切れない場合が多いと考えられるからです。
上記点を考慮した場合、改善指導を行う、改善指導を行っても効果がない場合は専門知識・スキルとは関係のない部門も視野に入れた配置転換を提案する、配置転換に応じない場合になって初めて解雇を検討するといった配慮が必要になるものと考えられます。
なお、配置転換を提案した場合、スペシャリストであるが故に、自らの専門外の業務には従事したくないとして従業員自らが退職を申し出てくることもあります。できる限り合意退職にて処理したほうが会社としてリスクヘッジができること、また配置転換を拒絶したことで解雇の正当性を主張しやすくなることを考慮すると、中小ではなかなか難しいとはいえ、配置転換の提案は重要なポイントになることを押さえておくべきです。
・経歴、職歴経験者
例えば、前職における職務内容や業務実績等を考慮し、××待遇(例えば、役職はつけないものの営業部長並みの待遇にする等)として採用するという場合、従業員の経歴・職歴から相応の能力・経験を保持しているものとして会社は期待することになります。また、従業員も前職での経験等をアピールして入社しますので、会社が経歴・職歴に相応する能力等に期待を寄せていることを理解しています。
したがって、経歴・職歴を踏まえて然るべき能力・経験を活用して業務従事することを内容とした労働契約が締結されたと考えることになります。
もっとも、前述の役職限定者及びスペシャリストと異なり、「経歴・職歴を踏まえて然るべき能力・経験」とは抽象的であり、少なくとも一義的にあるべき能力水準を読み取ることはできません。例えば、現場実務で往々にして生じることなのですが、前職の大手企業で実績No.1の営業成績をあげていたという経歴があることから、転職先である中小企業においても当然にNo.1の営業成績を上げる又は抜群の営業実績を上げることが労働契約の内容になっていると解釈することは困難です。なぜなら、よくある事例として、大手企業であれば営業を行うことだけに集中できたが、中小企業の場合、営業以外に契約のクロージング、社内処理、アフターフォロー等まで担当する必要があるところ、これらの業務については一切経験がないため、会社からすれば採用した従業員の業務遂行に不満を持つ(逆に当該従業員も雑務に負われて営業ができないとして不満を持つ)といったことがあるからです。
このような実情を踏まえると、会社が求めている能力水準と、従業員が認識している能力水準とに相違が生じており、第三者である裁判官からすれば、何をもって能力水準を設定すれば分からないという状態となります。この結果、裁判官が独自に認定した能力水準を前提に能力不足の有無が判断され、会社による解雇は無効であるという判断が続出することに繋がります。
結局のところ、採用時に締結する労働契約書において、会社が求める能力水準につき、どこまで具体的に定めることができるのかということがポイントになってきますが、現実的には定めることが難しいと考えられます。
以上のことから、経歴、職歴経験者を試用期間中又は試用期間満了後に解雇することは相当難しいと考えられます。指導教育を行う、指導教育を行っても功を奏さない場合は経歴・職歴とは結び付かない部門を含めて配置転換の提案を行う、配置転換を拒否した場合は解雇を検討する(但し、できる限り合意退職に持っていく方が望ましいことは言うまでもありません)、といった通常の能力不足による普通解雇手続きを実践したほうが無難と考えられます。
3.試用期間中又は試用期間満了時に解雇する場合の注意点
試用期間中であれば、会社は自由に本採用拒否(解雇)できるとまだまだ考えられているためか、色々な勘違いがあるようです。
代表的な勘違いを3つあげておきますので、間違えないようご注意ください。
①試用期間中であっても原則解雇予告手当の支払いは必要であること。
なお、労働契約開始後14日以内に解雇する場合、解雇予告手当は不要です。
②本採用拒否は会社都合退職扱いとなること。
なお、法的には解雇である以上、当然の結論となるのですが、この点を十分に理解せずに、既に受給している助成金の返還事由に該当したり、今後の助成金の受給要件を満たさなくなる場合があるので、注意が必要です。
③退職強要・パワハラ等の反論を受けないようにすること。
なお、能力不足を原因とする本採用拒否を告げても、従業員本人が納得しないということもあり得る話です。この場合、何とか辞めさせようと交渉することになりますが、一歩間違えると強要された=パワハラを受けたとして、逆に会社が責められる事態にもなります。協議の進め方や方針の組み立てには細心の注意を払いたいところです。
<2022年7月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。