契約書を締結未了の相手とトラブルになった場合、損害賠償等の請求は可能か
【ご相談内容】
当社はシステム開発会社です。
ユーザよりシステム開発に関する問い合わせを受け、商談を進めていたところ、ユーザの希望納期がかなり切迫するものであったため、契約書の取り交わしを行うことなく、先行して作業を開始しました。
ところが、後日ユーザが、「システム開発の必要性が無くなった」と通知し、一方的に商談を中止させました。
当社としては、先行作業分に関する報酬だけでも支払ってもらいたいのですが、ユーザは正式な契約を締結していない以上、支払う必要はないとして対応してくれません。
やはり契約書を締結していない以上、支払いを求めることは難しいのでしょうか。
【回答】
契約書が存在しないこと、たしかに支払いを求める有力な根拠を欠き、不利な状態と言わざるを得ません。
しかし、契約は口頭でも成立するというのが法律上の原則である以上、契約書以外の書類や交渉経過及び内容を明らかにすることで、契約が成立したと評価できる場合があります。
また、契約不成立と評価される場合であっても、商法の規定や裁判例の積み重ねによって認められてきた法解釈論に基づき、一定の金銭請求ができる場合もあり得ます。
契約書が存在しない場合における対処法をまとめると、次の通りとなります。
①口頭又は黙示の契約が成立していないか検討する(なお、本件のような請負又は準委任の事例で契約が成立していると評価できる場合、中途解約した場合は損害賠償請求が可能と定めている民法第641条又は民法第651条で処理することが可能です)
②商法第512条に基づく報酬請求ができないか検討する
③契約締結上の過失に基づく損害賠償請求ができないか検討する
上記の3つの方法を用いた請求を行う場合のポイントや注意点等につき、解説を行います。
【解説】
1.口頭又は黙示の契約成立の可否
(1)契約書の重要性
業務委託契約(請負契約や準委任契約など)は、必ず書面で契約しなければならないものではなく、口頭によっても契約を成立させることは可能です(民法第522条)。
したがって、理論的には、契約書が無くても「契約が成立した」と主張することは可能ですが、一方が契約は成立していないと争ってきた場合、契約の成否については決め手を欠くことになります。そして、裁判例などを見ていると、契約書がないことは契約不成立を推定させる重要な考慮要素になっている点は否めません。
契約書が無いにもかかわらず、契約が成立していることを裏付けることは並大抵のことではありませんが、裁判例を分析してみると、次のような事情を考慮することで、契約が成立しているものとして取り扱われることがあるようです。
(2)契約書に代わる書面の存在
まず、署名押印した契約書は存在しないものの、一方が他方に対して、契約書のドラフトを提示済みである(契約書のデータを送付済みである)、といった事例は現場実務ではよくあることかと思います。
この点、なぜ署名押印が行われていないのかという背景事情を探ることにはなりますが、一般的には契約書のドラフトに記載されている内容につき、双方協議の余地があった(内容検討中である、文言修正を含めた交渉中である等)という状況と考えられます。
したがって、署名押印の無い契約書があることだけを理由に、契約が成立していると取扱うことは難しいと考えられます。
次に、委託者側が何らかの書面を発行している事例を検討します。
例えば、委託者が発注書を交付しているという事例もあり得ます。
この場合、発注書をもって発注意思があったと通常考えることができますので、発注請書や電子メール等で応諾した旨の表明があった場合はもちろん、口頭で応諾した場合であっても契約は成立したと取扱うことは原則可能と考えられます。
ただ、発注書が発行された経緯、例えば、受注者側での社内処理に必要だからという理由で形式的に発注書が交付されただけであり、契約内容について具体的に詰めていなかったというのであれば、契約の成立が否定される場合もありうる話です。
ところで、発注書と似て非なるものとして、内示書と呼ばれるものがあります。
一般的に内示書と呼ばれるものは、正式な発注書を交付する前段階の“つなぎ”の文書(仮発注書とイメージすればよいかもしれません)を意味することが多いとされています。すなわち、内示書が交付された段階では、数ある受託候補者の中より、特定の受託候補者との契約を前向きに検討していること、及び委託者において今後の選考手続きを進める上でより詰めた協議を行いたいことを表明する、という意味に留まるものと考えられます。
したがって、少なくとも委託者は、契約を成立させるだけの確定的意思を有していないといえますので、内示書だけが発行されているにすぎない場合、契約不成立として取り扱うことになると考えられます。
一方、受託者側が何らかの書面を発行している事例を検討します。
例えば、受託者が委託者に対して見積書を提示済みという場合があります。
たしかに、受託者が見積書を作成するに当たり、委託者よりヒアリングするなどして相当の時間・労力等をかけて準備作業を進めている場合もあると思われます。しかし、一般的には、見積書を提示した後に、委託者が発注するか否かの回答を行うというのが商取引の流れであることを踏まえると、委託者が確定的に契約を成立させる意思を有していたとは言い難いと言わざるを得ません。
したがって、見積書だけを根拠に、契約が成立したものとして取扱うことはできないと考えられます。なお、提案書や設計構想書についても、これらの書面提出段階では、契約成立に向けた今後の交渉が予定されていることが通常である以上、やはり見積書の場合と同じく、契約不成立として取り扱うことになると考えられます。
最後に、双方が署名押印済みの確認書や協定書が作成されている事例を検討します。
この点、文書のタイトルにとらわれず、どのような合意内容が定められているのかを見極めることがポイントとなります。例えば、成果物の内容や仕様については双方合意しているものの、報酬については作業納期に応じて別途協議するという内容であれば、契約が成立したと評価される可能性が高いと考えられます。しかし、例えば、双方の申入れ事項を単に記述したに過ぎない書類(一種の議事録といったほうが良いかもしれません)や、××の条件が成就した場合は改めて正式な契約を行うといった記述がなされていた場合、契約が成立したものとして取り扱うことは難しいと考えられます。
結局のところ、当該書面作成以降において、改めて契約締結交渉を行うことを前提にしたと解釈される文書であれば、契約の成立は否定されることになります。
(3)交渉経過
そもそも論として、契約が成立したものとして取り扱うためには、主要な事項につき双方合意したといえなければなりません。例えば、システム開発において、受託者が「××という機能を実装しませんか」と営業提案を行い、委託者が「面白そうなのでやってみよう」と回答したとしても、システム開発の請負契約において主要な事項である、業務内容(業務の進め方や範囲、成果物の概要など)、納期、(確定額ではないが相当程度の)報酬、支払方法が決まり、かつこれらの事項をいつの時点で合意したのかが明確にならないことには、契約が成立したものとして取り扱うことは難しいといえます。
ちなみに、上記は請負契約を例にしましたが、例えば準委任契約の場合、作業内容・処理方法、作業期間、報酬などが主要な事項と考えられ、これらが決まっていないことには準委任契約が成立したとは言い難いといえます。
以上のように、契約が成立したと主張するためには、一連の交渉経過において、当事者双方が、どのような事項について合意しているのかを探求する必要があります。そして、その合意事項が、契約の主要な事項に該当するのか法的評価を行うことが重要となります。
なお、よく巷では、合意内容が具体的であれば契約の成立は認められやすいと言われています。しかし、上記の通り、契約の主要な事項について具体的な合意がなされているのであれば、契約の成立を裏付ける考慮要素とはなりますが、契約の主要な事項とは言い難い事項につき具体的な合意を取り交わしていたとしても、契約の成否判断に大きな影響を及ぼすわけではありません。むしろ、目的物や作業内容・範囲が抽象的あるいは不明確である場合は、契約不成立の推認が働きやすいという程度で押さえておいたほうが良いかもしれません。
ところで、契約の主要な事項について合意しているか否かについては、十分な証拠が残っていないことがむしろ通常です。そこで、一定の言動を足掛かりにして契約の成否が判断できないかという手法が現場実務では用いられます。
例えば、先方が社内稟議・社内決済を理由に契約の成立を否定してきた場合、あくまでも先方の内部手続きにすぎません。そして、社内稟議・社内決済が必要な段階に至っているということは、逆に言えば契約交渉は相当煮詰まっており、(少なくとも担当者間レベルでは)契約の主要な事項についても協議し合意していると推認する重要な考慮要素となります。しかし、社内稟議・社内決済が必要であることを知っていた場合、先方は契約締結の意思を確定させたとは言えませんので、かえって契約不成立を推認する重要な考慮要素にもなり得ますので注意が必要です。
また、一方当事者が契約成立を主張する日以降においても、契約交渉が継続している場合、契約の主要な事項について確定的な合意ができておらず、契約が成立したとは言えないと推認する考慮要素になります。もっとも、請負契約の場合、契約締結時に契約内容が全て定まるとは限らず、企画、設計、仕事の完成、引渡しまで一連の経過をたどる有機的な一体の契約とされ、例えば契約成立後も仕様の確定作業が行われることが実情です。
したがって、契約の主要な事項に関する交渉が継続しているのか、契約締結を前提に作業プロセスの詳細化と策定協議を行っているのかを整理しながら判断する必要があります。
(4)業務遂行、作業の有無・内容
実際の業務や作業に着手し、ある程度進んでいる場合、契約の成立を裏付ける考慮要素となり得ます。
しかし、いわゆる営業・セールス目的で無償対応を実施する場合もあり、業務遂行や作業を行ったという事実だけで、契約が成立していると断定することはできません。また、受託者が行っている業務遂行や作業につき、委託者に有償という認識がない場合、やはり営業・セールス目的での無償対応と考えられる場面もあり得るところです。
結局のところ、営業活動の一環なのか、契約に基づく業務遂行・作業なのかの判断については、その内容及び期間はもちろんのこと(無償で実施することがあり得る業務遂行・作業内容なのか等)、当事者間での認識(交渉経過を踏まえると、当該業務遂行・作業は有償であることが認識できたか)が重要となります。
単に業務遂行、作業さえ着手していれば、契約は成立したものとして取り扱われると考えることは禁物です。
(5)その他考慮したい事項
上記(1)から(4)まで、契約書が無くても、他の事情を考慮することで契約が成立したと評価することはできないか(積極的な契約合意の意思表明があったといえないか)、という観点から解説を行いました。
このようなアプローチとは別に、「黙示の合意」が成立したと評価することはできないか(積極的な契約合意の意思表明までは認められないが、契約内容を消極的ながら受入れているといえないか)という観点からも検討することが有用な場合があります。
ただ、黙示の合意があったというためには、ある程度の長期的な業務遂行・作業が行われ、かつ当該業務遂行・作業が無償で行われる範囲とは言い難い…といった条件が揃う必要があると考えられます。
したがって、黙示の合意があったことを前提にした主張を行う場合は、事前に緻密な検証が必要不可欠と考えたほうが良いと思われます。
ところで、契約の成否の判断となると、どうしても「ゼロか百か」の判断になってしまいます。そして、契約が成立していないと判断された場合、受託者はタダ働きリスクが生じる、委託者は受託者の契約違反を追及できない、という不利益を被ることになるのですが、これらの不利益を回避するために、現場実務の対応として、一部合意という手法が取られることがあります。
例えば、先行着手依頼書等において、業務遂行・作業は有償であり、万一途中で中止となった場合は精算を行う旨記述してもらうといった方法です。
これにより、全体としての契約合意には至っていないが、これから行う業務・作業(工程の一部)に限っては合意している、したがって、双方当事者がその限りにおいて責任を負うということが明確になります。どうしても契約書の署名押印が遅れてしまう場合、一部合意という対応を活用したいところです。
(6)契約が成立した場合の契約内容
ところで、契約が成立したものとして取り扱われる場合、具体的な契約内容をどのように考えるのかを次に検討する必要があります。
この点、例えば、署名押印がないとはいえ契約書のドラフトを提示したことを理由に、当該契約書に記載されている内容にて契約が成立した…と考えるかもしれません。しかし、裁判例を紐解くと、契約書のドラフトに記載されている内容通りで契約が成立したという取扱いは行っていないことに注意が必要です。
結局のところ、交渉内容や取引経過を考慮し、双方当事者が前提にしているであろうと考え得る事項のみ合意したものとして取り扱うというのが裁判例の傾向といえますが、例えば請負契約の場合、もっとも重大な関心事である報酬額については真偽不明であるとして、「相当額(時価相当の代価)」と認定され、裁判官が適当に(?)金額を算出するといったことが起こり得ます。このような認定となった場合、「相当額」はいくらかということで、更なる検証が必要となること注意を要します。
なお、「契約の成否」と「合意した内容」は全く別問題であり、契約の成立を主張する当事者は、どちらについても主張と立証を尽くす必要があることを意識しておきたいところです(執筆者個人としては、「契約の成否」に比重が置かれすぎ、「合意した内容」について疎かになりがちのように思います)。
2.商法第512条に基づく報酬請求の可否
契約の成立が認められなかった場合、受託者は契約に基づく報酬請求を行うことはできません。
しかし、営業・セールス目的の場合もあるとはいえ、如何なる業務遂行・作業についても無償と考えるのは不合理と言わざるを得ません。むしろ、商取引であることを念頭に置くのであれば、事業者がタダで業務遂行・作業することはあり得ないという経験則があると考えたほうが自然です。
このような経験則を前提に、商法第512条は次のように定めています。
| 商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。 |
そこで、契約が成立していなかったとしても、商法第512条に基づき相当額の報酬を請求できないかを検討することになります。
(1)他人のために行為したとき
商法第512条では、「他人のために行為をしたとき」が要件とされています。
受託者からすれば、委託者のために業務遂行・作業を行ったのだから、当然に認められると考えるかもしれません。しかし、そのような考え方は通用しません。
なぜなら、ここでいう「他人のために行為をしたとき」とは、「客観的にみて、事業者が相手方当事者のためにする意思をもって行為をしたと認められることを要し、単にその行為の反射的利益が相手方当事者にも及ぶというだけでは足りない」と解釈されているからです。
例えば、業務遂行・作業を行うために、受託者が協力業者等に声をかけて必要な人員を揃えたという場合、受託者からすれば、委託者のための準備行為であると認識しているかと思います。しかし、上記解釈論を踏まえると、客観的には受託者のための準備行為に過ぎず、人員確保による直接的な利益は委託者に及んでいるとは言い難く、結論として「他人のために行為をしたとき」の要件を充足しないと考えられます。
本来契約が締結されていた場合、受託者は、当該契約に基づいて委託者のために直接提供しなければならない業務遂行・作業を行ったと評価されないことには、「他人のために行為をしたとき」の要件は充足しないと考える必要があります。この観点からすると、契約締結前の交渉段階で、受託者は委託者に対して何を提供する必要があったのかを確定させた上で、どこまで提供済みかという二段構えで検証することが重要となります。
(2)相当な報酬
商法第512条に基づく請求を行う場合に頭を悩ますのが、「相当な報酬」をどのように算定するのかという点です。
例えば、過去に取引があったというのであれば、過去の取引において用いた報酬算出方法を参照し相当額を定めるという裁判例も存在します。しかし、新規の取引である場合や、過去に取引実績があっても取引内容が大きく異なり参照できないという場合は、基準を設定しづらく、具体的にいくらの額であれば相当な報酬と言えるのか予見しづらいところがあります。
受託者としては、見積書等で金額の提示を行っている場合、この見積金額をどのように算出したのか合理的に説明できることはもちろん、業務遂行・作業の進捗状況を客観的に把握できるようにし、その上で相当な報酬額を算出の上、(裁判官や委託者に対して)説得に努めるという対応が必要と考えられます。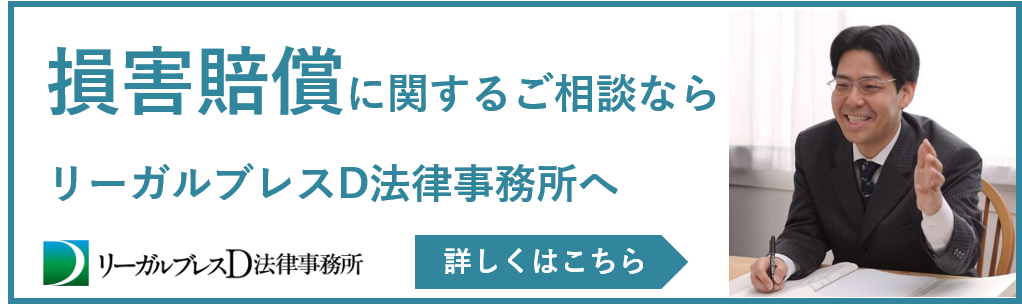
3.契約締結上の過失に基づく損害賠償請求の可否
「契約締結上の過失」という言葉自体聞いたことがないという方も多いかもしれません。
これは法律上の根拠規定がなく、裁判例の積み重ねによって認められてきた法解釈論となります。ここでは、契約締結上の過失とは、契約成立には至っていないが、契約交渉などの準備段階において、相手方に契約成立に関する信頼が生じた場合には、その信頼を侵害したことによって生じた損害賠償責任を負う法理と定義づけておきます。
ちなみに、商法第512条との相違ですが、商法第512条は「他人のために行為をしたとき」という要件があるのに対し、契約締結上の過失は当該要件が無いという点です。
前述した業務遂行・作業を行うために、受託者が協力業者等に声をかけて必要な人員を揃えたという例の場合、商法第512条では報酬請求することが困難ですが、人員を揃えるという準備行為を行った理由が、相手方の言動により契約成立への信頼が高まったからだといえる場合、契約締結上の過失に基づく損害賠償請求が認められる場合が生じます。
(1)成否
契約締結上の過失が認められるためには、契約成立への信頼が生じたことが必要となりますが、この「信頼」は、単に受託者の主観で判断するのではなく、客観的に見て“信頼しても仕方がない(第三者から見ても、一方当事者が信頼するのはむしろ当然と考えること)”という段階に達する必要があります。
要は、法的保護に値する程度の「信頼」が必要となるのですが、一律に判断できるものではなく、ケースバイケースの判断とならざるを得ないというのが実情です。あくまでも一例にすぎませんが、次のような事項が考慮要素になると考えられます。
【信頼が保護される方向に考慮される要素】
・契約書の締結は未了であるが、委託者の要望に基づき、長期間にわたって大量の業務遂行・作業が実施されていること
・受託者が契約書の締結を要望しているにもかかわらず、正当な理由なく拒否し続けていたこと
・複数の候補事業者の中から絞り込まれ、事実上の選定が行われた旨通知されていたこと
・内示書、仮発注書等の文書が提示されていたこと
・契約締結交渉を破棄した理由が、専ら委託者の都合によること(受託者に帰責性が無いこと)
【信頼が保護されない方向に考慮される要素】
・委託者の明確な指示や黙示的に指示した事情がないにもかかわらず、受託者の独断で業務遂行・作業が実施されたこと(受託者が既成事実を作出しようとする意図がみられること)
・業務遂行・作業範囲が不明確であり、多くの交渉事項が残されたままであったこと
・契約を締結するためには、前提条件をクリアーする必要があることにつき、当事者双方で認識共有されていたこと
・複数の候補事業者が存在し、絞り込み及び選定が未了であることを通知していたこと
・社内稟議や社内決済が必要である旨告知されていたこと
(2)損害の計算方法
受託者による契約成立への「信頼」が法的保護に値するとなった場合、次に検討するべき事項は、契約締結上の過失に基づき、いくらの損害賠償請求ができるのかという点になります。
ところで、契約交渉の一方的破棄により、受託者が被った損害の内訳は次のようなものと考えられます。
・業務遂行、作業により生じた実費(人件費、交通費、機材等の購入費、協力業者への依頼費など)
・実施済みの業務遂行、作業に対する(営業)利益
・契約が締結されたことで得られたであろう利益(未実施分の業務遂行・作業に対する逸失利益)
この点、契約締結上の過失による損害賠償の範囲は信頼利益に限定されるという解釈論が優勢であるところ、この信頼利益とは、上記の内訳でいう「業務遂行、作業により生じた実費」を指すと考えられます(なお、裁判例によっては、「業務遂行、作業に対する(営業)利益」相当を認めているものもあります)。一方、「契約が締結されたことで得られたであろう利益(逸失利益)」は信頼利益には含まれません。
したがって、契約締結上の過失に基づく損害賠償請求の場合、受託者が想定している金額よりも低くなりがちであることに注意が必要です。
(3)過失相殺
契約締結上の過失については法律上の根拠規定がなく、裁判例の積み重ねによって認められてきた法解釈論であること、前述の通りです。
要は、妥当な結論を導くための法解釈論であるため、契約交渉が破棄された理由につき、双方にそれぞれ責任ありとされた場合、裁判官は過失相殺という考え方を用いて、双方の責任負担割合(落ち度)に応じた請求に抑え込もうとします。例えば、ある裁判例では、一定期間を経過しても正式発注がない以上、受託者は各作業を中断することで損害発生を防止するべきであったとして、3割の減額を行ったというものがあります。
この過失相殺の割合については、正直予測することが難しく、裁判官の考え方次第というところになります。
なお、契約締結上の過失に基づく損害賠償の場合、損害の範囲が信頼利益に限定され、かつ過失相殺される可能性があることから、訴訟に時間と労力と費用をかけた割には、認められた金額は僅かにすぎないというリスクが付きまといます。結局のところ、巡り巡って、確実に契約書を締結しておくこと(又は契約が締結されたことと同様の書類を入手すること)、勝手な思い込みだけで業務遂行・作業を開始しないことが最良のリスクヘッジになることを十分に理解しておきたいところです。
4.当事務所でサポートできること
事例ではシステム開発やWEB制作に代表される請負契約及び準委任契約を取り上げましたが、不動産や特殊品などの売買契約、建築予定物件の賃貸借契約など、ありとあらゆるタイプの契約で、この種のトラブルは起こり得ます。
当事務所では、契約書を締結しないまま商談を進めたところ、途中で破談となりトラブルとなった事例つき、双方の立場で、訴訟を含めた複数の取扱い実績があり、ノウハウ及び知見を習得しています。
また、本記事では触れていませんが、上記記事で解説したポイントを、どのタイミングでどのように持ち出して交渉するのか等についても色々と検討するべき事項があります。
契約交渉が途中で破談したことに関するトラブルでお悩みであれば、是非当事務所までご相談ください。
<2023年3月執筆>
※上記記載事項は弁護士湯原伸一の個人的見解をまとめたものです。今後の社会事情の変動や裁判所の判断などにより適宜見解を変更する場合がありますのでご注意下さい。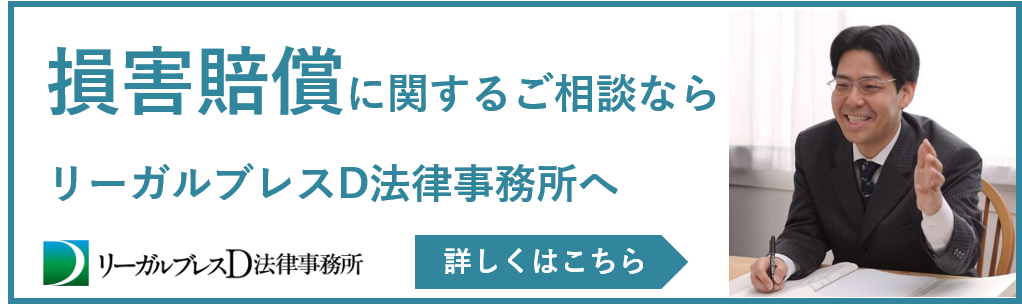
- フリーランス新法のポイントと業務委託契約書の見直しについて解説
- ホームページ、WEBサイトに関する著作権の問題について解説
- 競業禁止・競業避止義務に基づく損害賠償請求の注意点
- 電子メール・チャット等を用いて契約書を取り交わす際のポイントを解説
- IT業界で注意したい偽装請負問題について
- メタバースをビジネス・事業で活用する上で知っておくべき著作権の問題
- 検収完了後にシステム不具合が発覚した場合のベンダの責任、ユーザの対処法について
- 利用規約・約款に免責規定・免責条項を定める場合の注意点
- データ提供契約(ライセンス型)作成に際してのポイントを解説
- 画面表示(UI)は著作権その他法律の保護対象になるのか?


